
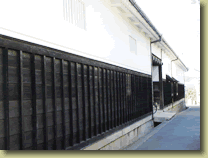
「いたら見てこい北田はんの屋敷。四角四面のよい屋敷」と地元の子守唄にも唄われているのは、昭和54年2月に国の重要文化財に指定された「北田家住宅」です。地元では「北田家住宅」と呼ばれるよりも「代官屋敷」の名前で親しまれています。
主屋(おもや)、表門、乾蔵、北蔵の四棟が重要文化財の指定を受けています。また付き指定として、土塀、撥木納屋、家相図(2枚)があります。
特に、山根街道に東面する表門は、民家の長屋門としては日本最大のものであると言われています。
| ● 代官屋敷 |
| ★ 子守唄にも唄われた「北田家住宅」 | ||
|
|
「いたら見てこい北田はんの屋敷。四角四面のよい屋敷」と地元の子守唄にも唄われているのは、昭和54年2月に国の重要文化財に指定された「北田家住宅」です。地元では「北田家住宅」と呼ばれるよりも「代官屋敷」の名前で親しまれています。 主屋(おもや)、表門、乾蔵、北蔵の四棟が重要文化財の指定を受けています。また付き指定として、土塀、撥木納屋、家相図(2枚)があります。 特に、山根街道に東面する表門は、民家の長屋門としては日本最大のものであると言われています。 |
|
| ★ 北田家の沿革 | ||
  |
北田家の家系図によると、同家は南北朝時代に南朝方に仕えていた北畠顕家の子孫で、南朝没落後は帰農し、その姓をはばかって、北畠の白を除き北田と称したといわれています。 その後、顕家より9代目の好忠の時に私部城主安見氏の重臣となりましたが、元亀元年(1570)の織田信長による本願寺攻めに参戦した安見氏が大敗し、城は大和の筒井勢により攻められ、遂に開城となりました。この時、なお残って最後まで奮戦し、下仕9人と共に壮烈な戦死を遂げたのが北田好忠でした。 それから20年経って、京都の叔父の家に送られていた嫡子の好孝が私部に戻り、現在の場所に家邸を構え、田畑を耕し農業を生業として生活を始めたのが現在の北田家の最初で、そのため好孝が中祖の第一世とされています。 江戸時代に入り、私部村の3分の2が旗本畠山修理太夫の知行地となるに及んで、北田家はこの地の庄屋を務めることになります。その後、18世紀前半、第6世佳隆の代には代官職を担うようになりました。 明治になって、庄屋、年寄り役は廃止され、現在第14世の御当主に至っています。 |
|
| ★建築物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||