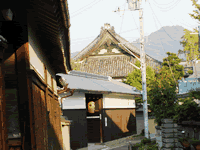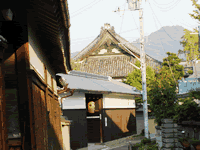| ●
交野の由来 |
|
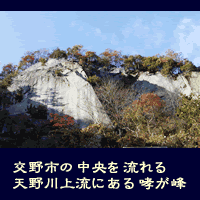 |
|
日本の古代のことを記した「先代旧事記(せんだいくじき)」に、日本の文明の夜明けの頃のこととして、「天祖 天璽瑞宝十種を以って、饒速日命(にぎはやのみこと)に授く。即ちこの尊、天祖御祖の詔をうけ、天の磐船に乗って天降り、河内の国河上の哮が峰(たけるがみね)に座すと」と書かれています。
即ち、饒速日命は、中国大陸から大和に入るため河内の哮が峰に着いたということが記述されています。
饒速日命は、この後、鳥身(とみ・現在の生駒)の酋長であった長髄彦(ながすねひこ)を臣従させ、その地方に様々な大陸文化を伝え、鳥身の君主となりました。
その子孫も代々地方の開拓に貢献し、大和朝廷の信任を得ることとなり、五代目の伊香色雄命(いかしおのみこと)の姉・伊香色謎命(いかしめのみこと)は九代開化天皇の皇后となり、一族に「物部(もののべ)」の姓を賜りました。また、伊香色雄命も大臣(おおおみ)となりました。その子の多弁宿弥(たべのすくね)は交野連(かたのむらじ)となって、天野川流域の開拓を進め稲作農耕を盛んにしました。この頃より、一族を肩野物部(かたのもののべ)というようになりました。
「かたの」の地名は、この肩野物部氏が開拓指導し、永く支配した地域を「かたの」と呼ぶようになったことに由来しているようです。
また、平安時代に歌を詠む人達の優雅な発想で、「人が行き交う野」、「生き物が行き交う野」という意味で、「交野」という字が使われる様になりました。 |
 |
| |
|
|
| ●
私部の由来 |
| |
|
★ 古くは「日本書紀」に私部の記述が |
| |
「日本書紀」巻二十 敏達天皇四年〜六年に
六年春 二月甲辰朔 詔置日祀部私部
という記述があります。
|
|
|
| ★
「私」は「后(きさき)」と同じ意味 |
| |
大和朝廷時代、国の制度は中国に倣って作られました。中国では皇后のことを司る役所を「私府」、それぞれの任にあたる人を「私官」、実際の仕事をする人を「私部」としていました。
即ち、「私」という字は「后」と同じ意味で、「きさき」と読んでいました。
「部」は、朝廷に属する各種職業人の集団ということで、皇后のためのことをする人達は「私部」と言われていました。
交野地方の私部は、皇后のための稲作を行う人達という役職名でした。それが、集団名になって、地名に残されていきました。 |
|
|
| ★
何故、交野に私部が? |
| |
三十代敏達天皇当時、政治の最高の要職にあった大臣(おおおみ)の蘇我馬子と大連(おおむらじ)の物部守屋は、互いに実力を争っていました。
敏達天皇の四年、十一月に廣姫(ひろひめ)皇后が亡くなられた時、蘇我馬子は、自分の姪の豊御食炊屋姫(とよみけかしきやのひめ)を新皇后にすることに成功しました。物部守屋も何か対抗策を考えていた時、天皇が新皇后の御領地として良い稲作地を求めておられることを知りました。そこで、肩野物部が開拓して以来、永年稲作を続けてきた交野の地は、住民も良く、田も肥沃で良い米がとれる所として有名だったので、ここを献上することとしました。
この申し出により、上述の日本書紀の記述の通り、敏達天皇六年(577年)の二月、詔で私部が宣せられ、以降私部の人々により、皇后領地の稲作が行われるようになったのです。
|
|
|
| ★
私部の地は天皇直属の「やまとのみた」へ |
| |
その後、敏達天皇が崩御され、592年に豊御食炊屋姫が三十三代推古天皇になられたことにより、皇后領田は天皇直属の「やまとのみた」と呼ばれるようになりましたが、稲作はそれまで通り、私部の人達によって行われました。今でも、私部には「官田」という天皇直属の田という意味の地名が残っています。 |
|
|