生物がそれぞれ進化して分化していったようすが想像できたでしょうか。
ここで、セキツイ動物が共通の祖先から進化してきたことが推測される類似点を少し考えていきましょう。
発生の初期の胚
セキツイ動物の発生において、初期の胚の形はとてもよく似ています。
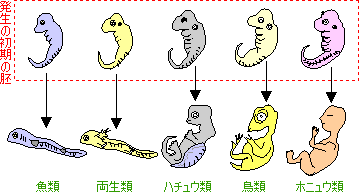
1個の細胞だった受精卵から1個体にまでなる「発生」は、それまでの進化のようすを猛スピードで見ていくようですね。
相同器官
器官をくらべたとき、基本的に共通なつくりが見られるときがあります。
相同器官…現在の形やはたらきが違っても、もとは同じ器官であったと考えられるもの
【相同器官の例】
「ヒトのうで」と「コウモリのつばさ」と「鳥のつばさ」と「イヌの前あし」と「クジラの胸びれ」の骨格は似ています。
「魚類のうきぶくろ」と「両生類以上の肺」もたがいに相同です。これに対し、相似器官ははたらきは同じであるが、もとはちがう器官であったものです。
【相似器官の例】
「昆虫類の羽」と「鳥のつばさ」は飛ぶための器官で形も似ていますが、起源がちがいます。
鳥のつばさはセキツイ動物の前あしにあたるもので、昆虫類の羽は皮膚が変形したものです。相同器官を見ていくと、長い期間のうちに、それぞれの環境に合わせて変化してきたことがわかりますね。