肺(または「えら」)と気管などをまとめて呼吸系(または呼吸器官・呼吸器)といいます。つくりを見ていきましょう。
| 順番にラジオボタンをクリックしてみてください。 |
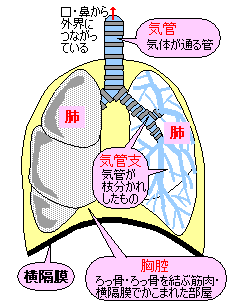
|
|
肺…多数の肺胞が集まってできている 肺胞…小さなふくろのようなつくり(参考:直径約0.2mm) 気管…空気の通り道 枝分かれして気管支となる 横隔膜…胸腔の底部にある筋肉でできた膜 胸腔…「ろっ骨」「ろっ骨の間の筋肉」「横隔膜」で囲まれた空間 |
呼吸系
わたしたちはいつも息をしています。酸素を取りこみ、二酸化炭素を捨てるために呼吸しているのですね。
ここでは、呼吸をするためのつくりやしくみ、なぜ呼吸をしなくてはいけないか、などをつかんでいきましょう。
呼吸系のつくり
肺(または「えら」)と気管などをまとめて呼吸系(または呼吸器官・呼吸器)といいます。つくりを見ていきましょう。
順番にラジオボタンをクリックしてみてください。 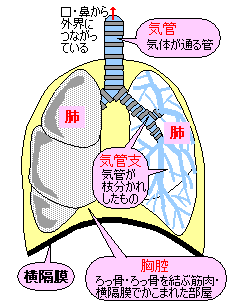
肺…多数の肺胞が集まってできている
肺胞…小さなふくろのようなつくり(参考:直径約0.2mm)
気管…空気の通り道 枝分かれして気管支となる
横隔膜…胸腔の底部にある筋肉でできた膜
胸腔…「ろっ骨」「ろっ骨の間の筋肉」「横隔膜」で囲まれた空間
数え切れないほどの多数の肺胞が集まってできている肺ですが、ひとつずつの肺胞の中で大事なはたらきをしています。
肺のはたらき…酸素と二酸化炭素を交換する 肺は多くの肺胞が集まっている→表面積を広げて物質を効率よく交換するため
肺胞でどのように物質の交換が行われているかつかんでください。先にこちらで肺循環などの復習をしてくるといいですね。
肺胞のまわりには毛細血管がとりまいています。
肺胞1個に気管支1本がつながっていて外界と気体のやりとりをしています。肺の呼吸
酸素は吸気とともに外界からとり入
れられ、二酸化炭素は呼気とともに
外界に捨てられます。物質の交換
心臓からきた静脈血は毛細血管内で
肺胞に二酸化炭素を捨て、
肺胞から酸素をとりこみ、
動脈血となり心臓へ帰っていきます。毛細血管の壁も肺胞の膜も非常にうすいので、酸素や二酸化炭素が出入りできます。
両生類・ハチュウ類・ホニュウ類の肺を見比べてみましょう。
※鳥類はまったく違う肺を持っています。
上の図の動物の肺では、呼気と吸気が混じり合って少々効率が悪そうですが、鳥類の肺の気体の流れは一方通行で効率のよいものになっています。
top > 動物 > 呼吸系・排出系・肝臓 > 肺のつくりとはたらき