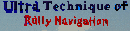
 ナビゲーション ウルトラ テクニック
ナビゲーション ウルトラ テクニック
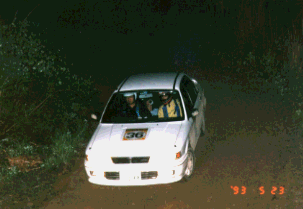 ページ内ジャンプ
ページ内ジャンプ
 Stage4 CP手前PC
Stage4 CP手前PC
 Stage5 内分外分パスコン
Stage5 内分外分パスコン
 Stage6 加速度PC
Stage6 加速度PC
 Stage7 OMCPまでのPC
Stage7 OMCPまでのPC
 Stage8 ウルトラ順不同パスコン
Stage8 ウルトラ順不同パスコン
Stage4 CP手前PC
[CPでわたされた公式通知での問題] このCPより20km/hで走行せよ。次のCP手前1kmより速度を40km/hに変更せよ。
解き方を解法を見ずに考えてみて下さい。(分かってしまうと簡単)
[解法]
CPの位置はわからないわけですから、CP手前は逆転の発想で解くことが必要となります。
すなわち、手前PCと同じ考え方で、先にこのPCを処理してしまいます。以下に実際の手順を示します。
(1)通常どうりCP処理を行い20km/hを入力。(直ぐに(2)から処理しても可)
(2)ラリーコンピュータのPCボタンをすぐに押し、40km/hを入力する。
(3)トリップメーターを見ながら1km走った地点で、PCボタンを押し、再び20km/hを入力する。
(4)オンタイム走行でCPインする。
・公式通知に、他のPCが書かれている場合にはこのPCは最後に書かれているはずですので、一番最後に処理を行います。また、アベは、この区間より前に走っていたアベを(3)で入力すればよいことになります。また、注意点としては、(2)〜(3)の処理は、CP後もしくは、このPCが処理可能になった時点ですぐに処理を行わないと上の例では1kmを走行しないうちに、CPが出現してしまいます。私の知る範囲では、このPCは新潟大学自動車部で発明されたものだと思います。このPCは解き方をしっていると簡単ですが、初めて出くわすと解き方が全くわからないのではないでしょうか。
先頭へ戻る
Stage5 内分(外分)PC
[問題] A地点とB地点を2:1に内分した地点をPCとしてアベを30km/hとせよ。(ここまでのアベは20km/h)
[解法]
このPCはある区間を○対△に内分または、外分する地点をPCとするものです。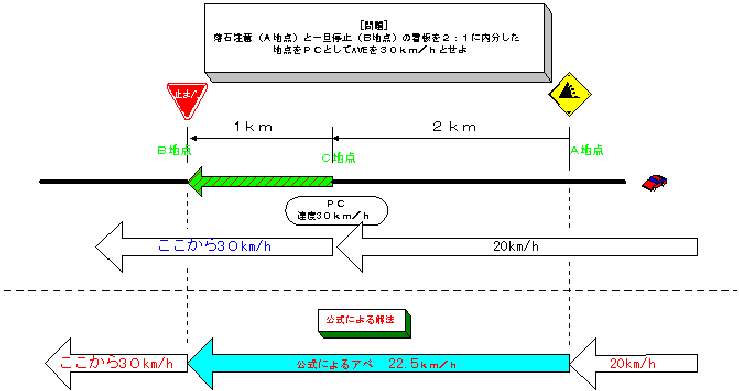
このPCは中間PCと同様で区間を3分割して、はじめの2区間を20km/h、後の区間を30km/hと考えればよいので、A地点(落石注意)から、B地点(一旦停止)までの平均速度をCkm/hとすると
C=3/(1/20+1/20+1/30)=22.5km/h
いう公式で解くことができる。実際の処理としては下記のようになります。この公式を用いると距離を計算する必要がありません。手前PCの応用でも解くことができますが、この方法の方がミスが少ないと思います。
(1)A地点までをアベ20km/hで走行する。
(2)A地点でPC処理して、アベ22.5km/hを入力する。
(3)B地点(一旦停止)で、PC処理してアベ30km/hを入力する。
先頭に戻る
Stage6 加速度PC
[問題] コマ図1を初速10km/hでスタートし、コマ図2で20km/hとなるように等加速度走行せよ。
コマ図間の距離は5kmとします。
これは、指示速度に加速度が用いられているPCです。
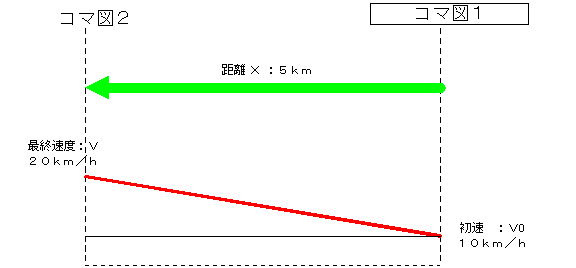 [解法]
[解法]
コマ図からコマ図を序序に加速して20km/hに加速しながら走ることはどんなドライバーでも不可能です。従って、速度または走行時間に変換します。
この加速度問題PCはバリエーションがいろいろあります。加速度問題では「初速:V0」,「最終速度:V」,「距離:X」,「加速度:A」,「時間:T」これらの要素のどれかを不明にして解かせるものです。
この問題では、初速と最終速度及び距離(走ってからわかる場合も)が既知であります。中学校で習った公式を思い出して下さい。
V=V0+(A*T) ・・・ (1)
X=V0*T+(1/2)*A*T*T ・・・ (2)
V*V−V0*V0=2*A*X ・・・ (3)
以上の3つの公式さえ分かればあとは代入して算出するだけです。上の問題では、コマ図間距離:Xが分かっていますから、未知であるAを求めてからTを算出します。
公式(3)に各値を代入すると
20*20−10*10=2*A*5
A=(400−100)/10=30km/h*h
公式(1)に上記Aを代入して、
20=10+30*T
T=10/30=1/3時間=20分
となりますから、コマ図1〜2の間を20分で走行すれば良いことになります。同様に、例えば加速度○○と指定されている場合にも公式(1)〜(3)から計算すれば解くことができます。
先頭に戻る
Stage7 OMCPまでPC
[問題]
スタートから10km/h
1PC:コマ図3より20km/h
2PC:スリップ注意の標識より30km/h
OMCP:Pの標識 スタートより9.000kmであった。OMCPより40km/h
[解法]
これは、学生ラリーなどでよく出題されるODまでPCと呼ばれるもので、通常のナイトラリーでは、絶対にPCの無いOMCPまでにPCが設定されているものです。
処理の方法としては、スタートしたら、PCで処理をせずにどんどん距離を控えて進んでいきOMCPで計算します。その為、図のような表を作成しておきます。この表はこの場合だけで無くラリー中全ての場面で使用できます。赤色部分がこのODまでPCに対応した部分です。このような表に全て記録を残しておくと間違った時や、後で反省したりすることができます。
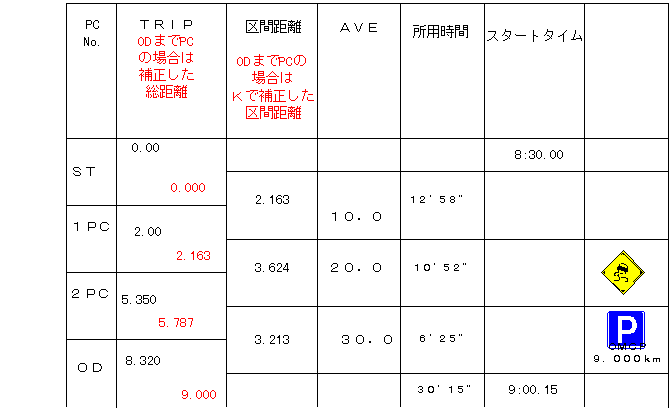 以下このPCの具他的な処理方法を述べます。
以下このPCの具他的な処理方法を述べます。
(1)スタートから順にPCまでの距離を控える。
(2)OMCPに着いたら通常どうりCPボタンを押し、OD処理を行う。
(3)ラリーコンピュータのK(補正係数)を控える。
表では、K=(自車トリップ)/オフィシャルの距離
=8.320/9.000
=0.9244
(4)この係数でTRIPを割ってトータルTRIPを補正します。これから区間距離を算出し、アベで割って所用時間を算出します。スタート時間が8:30だとすると表のように9:00.15がOMCPのスタート時刻となります。
この表は先にも述べましたようにいろいろな場面で活用できますので、必ず作成してラリーに持っていって下さい。この表を活用するため、私の場合は、画板を2枚ガムテープで止めて場所を大きくとって書き込みやすようにしています。
先頭に戻る
Stage8 ウルトラ順不同PC
本当に難しいPCはこれまで、説明してきたPCが組み合わせて出題されて、解く時間が少ない場合が一番難しいPCになります。
特に順不同看板PC、アベの一定距離、時間での増減、時間走行、手前PC等を組み合わせて出題されると非常に難しいものとなります。近畿地方では、今年からD.E地区戦になった姫路工大ラリーでも年々易しくはなっていますが、毎年出題されています。
このようなPCは、こう解くということが一概に説明できないのです。解き方としては、いままで、説明してきました手前PC、中間PC等の公式と上のODまでPCで説明しました表を用いて処理します。また、コンピュータに頼り切らずに、表で計算したスタートタイムでどんどんPCのスタートタイムを入れ替えて計算していくやり方が有効です。
落ち着いて処理を行えばそんなに難しくはないはずです。焦ることが、一番の大敵です。
このPCの解説を新設しました。下のリンクをクリックして下さい。
 一定時間と距離ごとにアベを増減させるPC
一定時間と距離ごとにアベを増減させるPC
先頭に戻る
ここまで、理解して頂けた方には、殆ど怖いPCは無いはずです。くれぐれも安全には留意してラリーを楽しんで下さい。
Thank you, and best of luck in your rallying!
ページ移動
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る
 ナビゲーションの基礎
ナビゲーションの基礎
 ナビゲートテクニック(さあスタートです)へ
ナビゲートテクニック(さあスタートです)へ
 ナビゲーションスペシャルテクニックへ
ナビゲーションスペシャルテクニックへ
 ご意見、リクエストをお待ちしています! nishida@po.aianet.or.jp
ご意見、リクエストをお待ちしています! nishida@po.aianet.or.jp
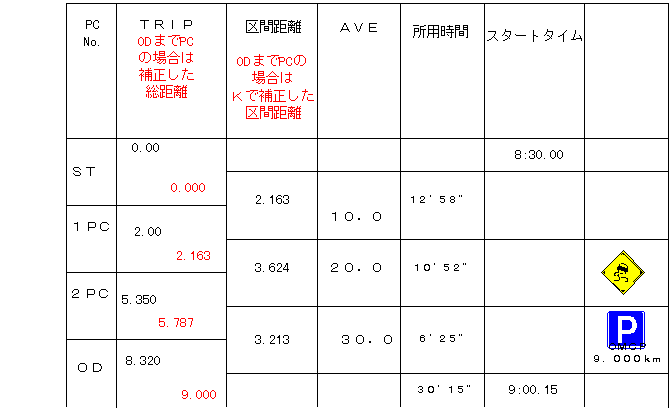 以下このPCの具他的な処理方法を述べます。
以下このPCの具他的な処理方法を述べます。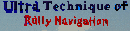
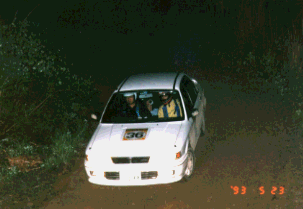 ページ内ジャンプ
ページ内ジャンプ Stage4 CP手前PC
Stage4 CP手前PC Stage5 内分外分パスコン
Stage5 内分外分パスコン Stage6 加速度PC
Stage6 加速度PC Stage7 OMCPまでのPC
Stage7 OMCPまでのPC Stage8 ウルトラ順不同パスコン
Stage8 ウルトラ順不同パスコン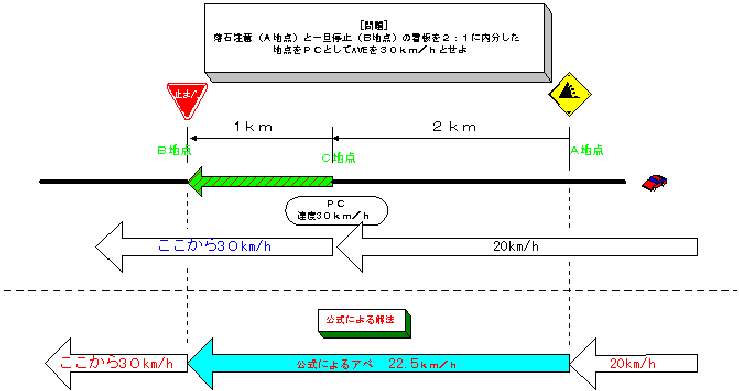
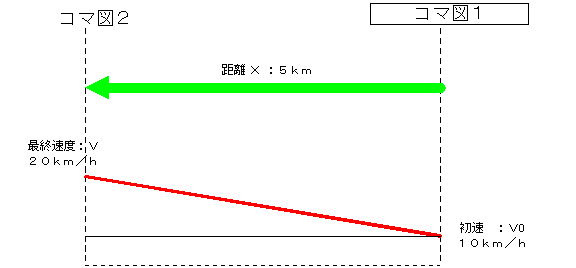 [解法]
[解法]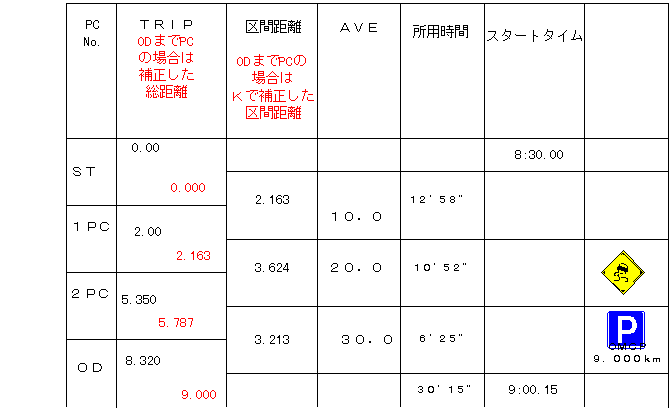 以下このPCの具他的な処理方法を述べます。
以下このPCの具他的な処理方法を述べます。 一定時間と距離ごとにアベを増減させるPC
一定時間と距離ごとにアベを増減させるPC
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る
 ナビゲーションの基礎
ナビゲーションの基礎
 ナビゲートテクニック(さあスタートです)へ
ナビゲートテクニック(さあスタートです)へ
 ナビゲーションスペシャルテクニックへ
ナビゲーションスペシャルテクニックへ
 ご意見、リクエストをお待ちしています! nishida@po.aianet.or.jp
ご意見、リクエストをお待ちしています! nishida@po.aianet.or.jp