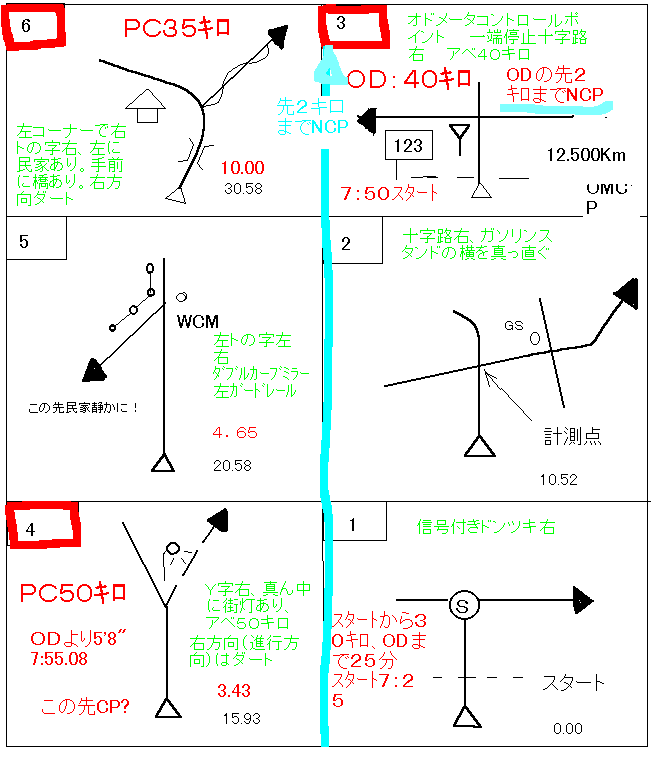ページ内ジャンプ 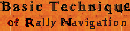
 ラリーへのエントリー
ラリーへのエントリー
 ナビゲータのラリー前の仕事
ナビゲータのラリー前の仕事
 コマ図の処理と読み方
コマ図の処理と読み方
ページ移動

 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る
 ナビゲートテクニック(さあスタートです。。)へ
ナビゲートテクニック(さあスタートです。。)へ
 ナビゲートスペシャルテクニックへ
ナビゲートスペシャルテクニックへ
1.ラリーへの参加
加盟クラブに入会し、B級ライセンスを取得したらいよいよエントリーです。モータースポーツでは中級者層が一番多くひしめいており、申し込んでも受理されないことも多々あります。そこで、参加するには、そのラリーのレベルを知る必要があります。 最近では、近畿ジュニアシリーズなど、ジュニアの付くシリーズから参加して腕を磨いていくのが良いでしょう。初心者向けディラリーと記されたラリーもベターです。 ライセンスを取得したら、JAFから送られてくるJAFスポーツやPD(雑誌:プレイドライブ=インターネットをやっている人のインターネットマガジンのような本)のカレンダーをに載っているラリーオーガナイザーに電話して特別規則書を送ってもらいます。送られてきた特別規則書は全てに目を通して下さい。特にスペシャルステージの扱いやチェックカードの受け取り方法、指定持参物、スタート時間などは忘れずにチェックして下さい。
申込書を返送する際の必要書類は完全を期してから返送するようにしましょう。書類不備の場合参加台数が多いと真っ先に参加拒否されます。中級ラリーでなかなか受理してもらえない場合にはシリーズのなかでスペシャルステージ(SS)の無いラリーが狙い目です。また、シリーズ初戦から申し込んで入賞してポイントを稼ぐと以降殆ど受理してもらえます。また、シリーズ戦に入っていない単発ラリーと呼ばれるラリーも狙い目です。
2.ラリー競技会出走前の準備
受理されて出場することになるといろいろ準備するものがあります。競技会当日は準備物を整え早めに出発しましょう。走行しながら、ナビはラリーコンピュータのチェックとラジオで時計を正確に合わせます。特に忘れ物には注意しましょう。「ライセンス、運転免許証、ヘルメット」は忘れると出場できませんので注意して下さい。(ドライバーも同様、ドライバーは参加受理書、車検証、自賠責保険、ラリー保険も忘れずに)また、「画板、ラインマーカー、両面テープ」なども忘れずに。また、人間のガソリン(食料)も忘れず購入していきましょう。
スタート会場に到着したらラリーオーガナイザー(主催者)から封筒に入った書類一式を受け取ります。ここで必ず内容物をチェックして下さい。また、疑問点はメモしておきドライバーズミーティングで説明がなければ躊躇せず質問するようにします。
- 公式通知の確認 受付場所周辺に公式通知(変更連絡など)が張り出されていることがあるので、メモします。ゼッケンやステッカーの張る位置も指定されていることもあるので、全部を転記しておきます。
- 渡されたコマ図に指示書(パスコントロールポイント=速度変更点)やチェックポイントからの指示速度、OD(オドメータチャックポイント)などについての指示があります。これを全て、コマ図に転記して下さい。チェックポイントからの指示速度はコマ図に記載できないので、別に表を作ってダッシュボードに張り付けます。(指示書を切り抜いてもよい) コマ図の書き方は非常に重要なので、3.で詳細に説明します。
先頭に戻る
- 3.コマ図の処理
ホームページでも述べましたが、ナビゲータの仕事の第1は道案内です。ミスコースはラリーでは一番やってはいけないことです。特にドライバーも初心者である場合には「道なり」の規定がよくわからず勝手に曲がっていったりすること多いので要注意です。「ここはどっち」とドライバーから聞かれた場合すぐどちらへ曲がるか判断してあげてください。また、ナビははじめのうちはPCよりコマ図の方を重視してミスコースを招かないようにして下さい。ミスコースしてそれを取り戻そうとして事故になることも少なくありません。また、ドライバーが最もやる気を失うのがミスコースです。常にコマ図のキョリを読み上げ(あと100m、50m、20m、ここ右という感じ)でドライバーにコマ図のキョリを伝えて下さい。
−−− [道なり規定]−−−
- 真すぐ方向
- センターラインの続く方向
- 舗装から舗装、ダートからダート
- 登りから登り、下りから下り
-
−−−コマ図の処理の仕方−−−
「指示書の内容」>>指示書の一部を下記に転記したものと考えてください。自車のゼッケンはNO.25とします。
OMCP:本ラリーの基準距離は下記条件のもとで行った。
スタートラインから3図OMCPまで12.500kmであった。
- 使用車 三菱ギャランVR4−RS(E38A)
- タイヤ ダンロップ SP83R 195/65R15
- 空気圧 2.4kg/cm2
- 測定器 グランツ GR−999
- 天候 晴れ
- 試走条件 オンタイム試走
速度変更点(PC:パスコントロールポイント)
- スタートより30km/h
- OMCPより40km/h
- 4図より50km/h
- 6図より35km/h
- 7図より40km・h
NOCP(ノーチェックポイント)区間
スタートより3図先2kmまで。
-
-
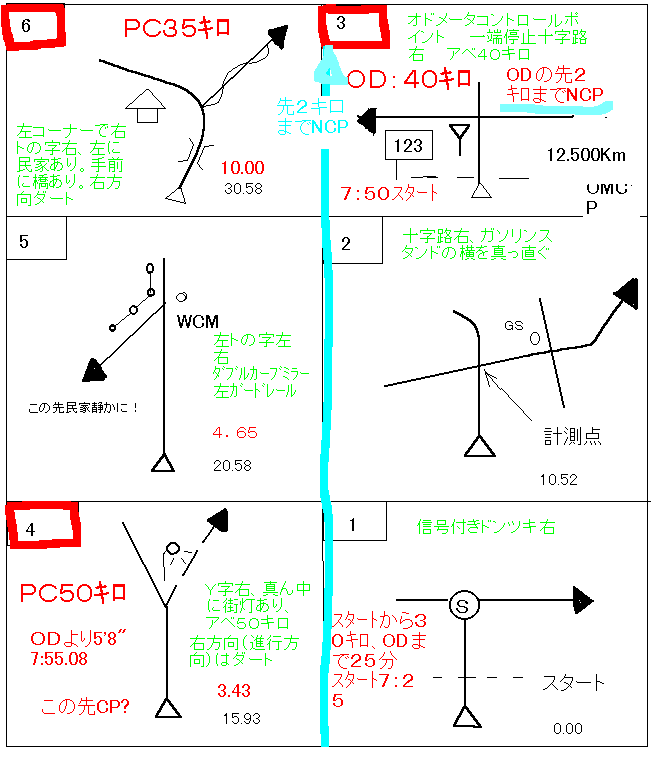
−−−コマ図への記入方法−−−
白黒で書かれた部分が配布されたオリジナルと考えて下さい。
これに、色をつけた部分がスタート前の処理して記入する項目です。緑色は地図のドライバーへの伝え方を示したもので、実際には記入しません。ラリーコンピュータへの数値の入力は機種によって違いますので説明書を参照して下さい。
{全体の処理}
- 各区間距離を計算して記入(図にはトータル距離が書かれていることが多い)
- 指示書の内容をコマ図に写す。PC、NOCP区間、OMCP
- コマ図をみて全体の流れを読む(この辺でCP(チェックポイント)がでできそう)
{記入例}
-
- [コマ図1](右下:上から順に書かれている場合もあるので注意)
-
- ・スタート時間を記入(ラリーコンピュータにも入力する)>>7:01に1号車スタートとするとゼッケン25のスタート時刻は7:25
・スタートからのアベ(アベレージスピード)30km/hを記入
[コマ図3]
・OMCPとはコースを作った車と自分の車のトリップメータの狂いを合わせる為のもので、この処理を行うと以降補正係数が算出されて距離がオフィシャルの距離と合致するようになります。
・OMCPまで12.5kmを30km/hではしるので25分かかります。(実際には図3先までノーチェックポイントなのでどんどんノーチェックポイントの終わりまで走ってかまいません。)
ここでOMCPでのスタート時刻を7:25+0:25で7:50と算出しておきます。
・NOCP(ノーチェックポイント):チェックポイントの設定が無い区間。この区間をラインマーカで水色に塗っておきます。この区間は普通ヘルメット着用不要です。また、ノーチェックポイントは交通の流れにのって早めに進みます。(工事で片側交互通行の為や渋滞する為ノーチェックポイントにしている可能性があるため) ただし、PCの処理を忘れないようにします。
[コマ図4]
・ここはPC(速度変更点)なので赤色で塗っておきます。また、ここの図でのスタート時間も計算しておきます。そうすることでラリーコンピュータのボタンを押すキョリの誤差をなくすことができます。
・また、破線はダートと舗装の区別をする場合のダートです。図6の波線も同様です。(地域によって違います)
・アベレージが50km/hに上がっているのでこの手前または、後にチェックポイントがある可能性が高いのでオンタイム(指示された速度どうりで進む、ラリーコンピュータ上の遅れ進みが0)で走行します。
[コマ図5]
-
- ・このコマ図は舗装とは限りません。ダートの中では舗装とダートを区別する場合以外破線や波線ではかかれていないかもしれないからです。注意しましょう。
先頭に戻る ホームページに戻る ご意見、感想をお願いします。
-
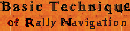
 ラリーへのエントリー
ラリーへのエントリー  ナビゲータのラリー前の仕事
ナビゲータのラリー前の仕事  コマ図の処理と読み方
コマ図の処理と読み方
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る
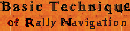
 ラリーへのエントリー
ラリーへのエントリー  ナビゲータのラリー前の仕事
ナビゲータのラリー前の仕事  コマ図の処理と読み方
コマ図の処理と読み方
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る ナビゲートテクニック(さあスタートです。。)へ
ナビゲートテクニック(さあスタートです。。)へ
 ナビゲートスペシャルテクニックへ
ナビゲートスペシャルテクニックへ