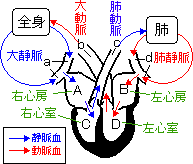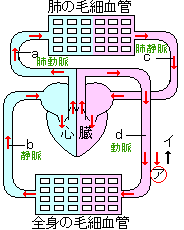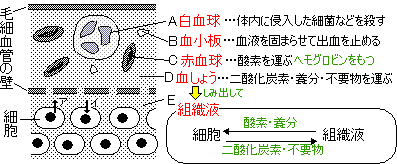解答と解説
1.
(1)ウ
(2)全身に血液を送るため
(3)ア
(4)c…肺動脈 B…左心房
(5)b d B D
|
心臓のつくりとはたらきの問題です。心臓の各部屋とまわりの血管の名称や血液の流れ方を思い出しましょう。
参考ページ…心臓のつくり 心臓のはたらき
(1)
正面から見た図とは問題文に書いてありませんが、Dの部屋の
筋肉が厚くなっていることから、Dが左心室であることがわかり、
正面から見た図であることが判明します。
血液の流れ方を覚えていれば、ここで解けますが、心臓の弁の
向きからでも判断できます。
心房は血液を吸い込む部屋、心室は押し出す部屋です。
大静脈(a)→右心房(A)→右心室(C)→肺動脈(c)→肺
→肺静脈(d)→左心房(B)→左心室(D)→大動脈(b)→
全身→a→A→C→c→肺→d→B→D→b→…
という流れなので、ウを選びます。
|
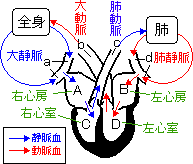 |
(2)
血液を押し出す部屋は右心室と左心室ですが、右心室は肺(心臓の近く)まで血液を押し出せばよいのに対して、
左心室は全身に血液を送らなければなりません。
全身に血液を送り出すため、強い力が必要なので、左心室の壁の筋肉はとくに厚くなっています。
(3)
心房と心室が交互に「縮む」「ふくらむ」をくり返して、血液をからだ中に循環させるポンプの役割(ア)をはたしています。
イはじん臓のはたらき、ウは肝臓のはたらき、エは肺のはたらきですね。
(4)
動脈は心臓から出ていく血液が流れる血管、静脈は心臓へ帰ってくる血液が流れる血管です。
cは肺へ出ていく血液が流れる血管なので、肺動脈です。
心房は上の部屋、心室は下の部屋です。Bは向かって左にある上の部屋なので、左心房です。
(5)
動脈血は酸素を多くふくんでいる血液のことです。
肺で二酸化炭素を捨て、酸素をとりこんだばかりの血液は肺静脈(d)を通って心臓の左心房(B)に帰り、
左心室(D)に押し出されて大動脈(b)を通り、全身へ枝分かれした動脈を通って送られます。
各部分の毛細血管で細胞に酸素を渡して二酸化炭素を受けとると、静脈血になります。
参考ページ…血液の循環
2.
(1)ア
(2)d
(3)bとd 体循環
(4)c
(5)a
(6)b 血液の逆流をふせぐ
|
よく見る、肺循環・体循環の模式図ですね。
参考ページ…血液の循環
(1)
血液の流れは一方通行です。心臓の弁を見れば、
アの向きに流れるのがわかりますね。
(2)
血圧は血液を押し流す圧力です。全身に血液を送るため、
強い力で左心室が押し出しているので、動脈(d)の血圧が
いちばん大きくなります。
(3)
酸素を渡し、二酸化炭素を受けとるための循環は体循環
ですね。肺循環は「二酸化炭素を捨て、酸素を受けとるため
の循環」です。
体循環は「心臓→全身→心臓」の流れで、肺は関係ない
ので、通る血管は心臓から全身へ向かう動脈(d)と全身から
心臓へ向かう静脈(b)となります。
|
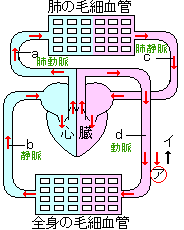 |
(4)
肺で酸素を受けとったばかりの血液は肺静脈(c)を通って心臓に行き、全身へ送られます。
(5)
肺で二酸化炭素を捨てる直前の血液は肺動脈(a)を通っている血液ですね。
(6)
動脈内の血液は左心室に押し出されて勢いがあるので、全身に送られていきますが、
心臓へ帰ってくる血液には勢いがありません。
そのため、末端に近い手足の静脈(b)には、血液の逆流をふせぐために弁がついています。
参考ページ…心臓のつくり
3.
(1)組織液 D
(2)A…体内に侵入した細菌などを殺す
B…出血したときに血液を固まらせる
(3)a…イ b…ア c…イ d…ア
(4)C ヘモグロビン
|
血液の成分とその役割、細胞との物質のやりとりの問題です。
参考ページ…血液の成分
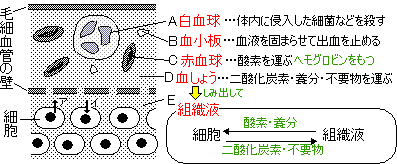
(1)
血液の液体成分である血しょう(D)が毛細血管の壁をしみ出して細胞間をみたす組織液(E)となります。
組織液は細胞と物質のやりとりをし、また毛細血管にもどって血しょうとなります。
(一部はリンパ管に入ってリンパ液となります)
(2)
Aは白血球で、からだ中の細菌の浸入を見張っています。細菌を見つけると食べて細菌を殺します。
Bは血小板で、万が一血管が破れ、出血した場合には集まって血液を固まらせ、出血をふせぎます。
(3)
アは細胞から組織液内へ出ていく物質の流れです。
細胞にとっていらないものを捨てているので、二酸化炭素(b)と不要物(d)の移動する向きですね。
イは組織液内から細胞へ入る物質の流れです。
細胞がほしいものを届けているので、酸素(a)と養分(c)の移動する向きです。
(4)
酸素を運んでいるのは赤血球(C)で、赤い平らな円盤状の血球です。
細胞のそばで酸素を血しょうにあずけ、組織液に細胞まで酸素を届けてもらいます。
赤血球がふくむヘモグロビンという赤い色素が酸素を運ぶ役目をしています。
top
> 実戦問題解説 > 2年 > 循環系