|
動物は生きるためにえさを 緑色植物は光合成で 草食動物はその緑色植物 食虫植物のような特殊な例を |
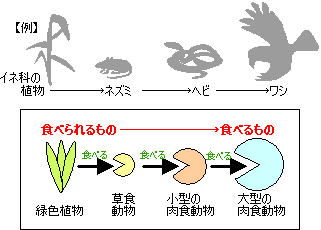 |
|
食物連鎖…食べる・食べられるという、食物による関係での、生物どうしのつながり 食物連鎖のはじまりはいつも緑色植物 | |
いっぱんに動物は、からだの大きいものが、からだの小さいものをえさとします。
(食物連鎖の上位にくるものほどからだが大きい)
※食物連鎖の矢印は「食べられるもの」から「食べるもの」へ引きます。
生物どうしのつながり
地球上にはたくさんの生物がいます。それぞれ、いろいろな地域・環境にすみ、ある程度の範囲で生活しています。
その範囲内でほかの生物とも関係を保ちながら繁栄して生きていますね。
わたしたちヒトは少し特殊ではありますが、やはりこの地球の生物の一員です。ここでは、まわりの生物との関係をつかんでいきましょう。
食物連鎖
動物は生きるためにえさを
食べなければなりません。緑色植物は光合成で
自分のえさとなる養分を
つくっています。草食動物はその緑色植物
を食べ、肉食動物に
食べられます。食虫植物のような特殊な例を
のぞいて、緑色植物がほかの生物
を食べるということはありません。食物連鎖…食べる・食べられるという、食物による関係での、生物どうしのつながり
食物連鎖のはじまりはいつも緑色植物
いっぱんに動物は、からだの大きいものが、からだの小さいものをえさとします。
(食物連鎖の上位にくるものほどからだが大きい)
※食物連鎖の矢印は「食べられるもの」から「食べるもの」へ引きます。
生産者
その地域でどんな生物がどんな食物連鎖をつくっていようと、はじまりはいつもえさを必要としない緑色植物です。
えさのかわりに、光合成によって、自分で有機物を生産しているので、自然界の生産者と呼ばれます。
※光合成についてはこちらで復習してください。
生産者…無機物を利用して有機物をつくる緑色植物
消費者
生産者は、有機物を生産して生きるためのエネルギーを得たり、自分自身のからだをつくっています。
動物たちは生産者のつくった有機物を直接または間接的に食べて(消費して)生きているので、自然界の消費者と呼ばれます。
消費者…生産者のつくった有機物を直接または間接に食べる動物
※緑色植物を食べる草食動物を第一次消費者、草食動物を食べる肉食動物を第二次消費者、それを食べる肉食動物を第三次消費者、それを食べる肉食動物を第四次消費者…と、消費者は何段階もあります。
食物連鎖の数量関係
えさとなる生物のほうが捕食する生物
にくらべて、個体数が多くなります。これを図で表したものが、よく見る
「生態ピラミッド」と呼ばれるものです。緑色植物を底辺とし、
最上位の消費者(大型肉食動物)
を頂点とします。底辺に近い生物ほど、個体数・全体の質量が多い
個体数のつり合い
生物間の数量関係は生態ピラミッドのように、つり合いが保たれていますが、何らかの原因でその関係がくずれるときがあります。
数量関係がどのように変化していくのか、えさとなる生物の数・自分を食べる生物の数に注目して考えてみましょう。
例としてCの生産者が
ふえたときを考えてみます。えさ(C)がふえたBの生物は
しだいに増加していきます。
ふえたBに食べられたCは
しだいに減少していき、
えさ(B)がふえたAは
しだいに増加していきます。
ふえたAに食べられたBは
しだいに減少していき、
自分を食べるBが減ったCは
しだいに増加していきます。
えさ(B)がへったAは
しだいに減少していき、
最終的にはもとのつり合いが
もどります。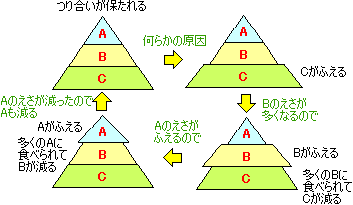
えさとなる生物がふえる…その生物は増加していく
自分を食べる生物がふえる…その生物は減少していくえさとなる生物が減る…その生物は減少していく
自分を食べる生物が減る…その生物は増加していく数量のつり合いがこわれても、食物連鎖によって長い時間をかけてもとにもどり、ふたたびつり合いが保たれる
※ただし、あまりに大きな環境破壊だったときや、人間によって新しい種類の生物が持ち込まれたとき、ある動物のみを大量に殺したときは、もとにもどらないときもあります。
top > 生物のつながり > 生物どうしのつながり > 生産者・消費者