ほとんどの有機物には炭素と水素がふくまれています。
このため、有機物が酸化すると水と二酸化炭素を生じます。
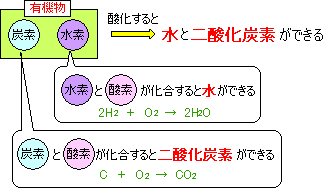
【例】
・石灰水を入れた集気びんの中で有機物を燃やすと、石灰水が白くにごり、びんが白くくもる
。
実験図
エタノールの燃焼では二酸化炭素と水が生じます。化学反応式のつくり方はこちらで紹介しています。
・細胞の呼吸とは、養分(有機物)と酸素からエネルギーを得ることである。
そのとき、水や二酸化炭素などの不要物も生じる。
こちらで思い出してください。
物質の分類はいろいろな観点がありますが、「有機物・無機物」という分け方もできます。
ここでは有機物とは何か、燃えるとどうなるのかをおさえましょう。
有機物とは
いっぱんに有機物は「人間が実験室で人工的につくるもの」というより、「生物がつくるもの」「生物のからだをつくるもの」または「生物を原料とするもの」が多いです。
有機物は「生物的」、無機物は「無生物的」というイメージですね。
ただ、有機物と無機物の決定的な定義はなく、今までの慣習で有機物と無機物が決められています。
有機物…炭素をふくむ化合物
燃えて二酸化炭素を発生するもの、加熱するとこげたりするもの【例】 ろう エタノール 砂糖 紙 木 プロパンガス 天然ガス プラスチック など
有機物は燃料になるものが多いですね。有機物以外の物質は無機物です。
無機物の例…食塩、水、鉄、アルミニウム、酸素、水素、ガラス、石など
注意!
二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)、炭酸ナトリウム(Na2CO3)、炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)は、
炭素をふくんでいますが、無機物です。
また、炭素(C)自体は燃えると二酸化炭素を発生しますが、無機物です。
有機物のつくり(参考)
有機物をつくっている原子の種類はわりと少ないです。
炭素(C)は必ずふくみますが、その他に水素(H)、酸素(O)でできているものとか、さらにその上、窒素(N)、硫黄(S)、リン(P)などが結びついていることもあります。どのようなつくりをしているか、具体的な物質の化学式をいくつか紹介しましょう。もちろん、今は覚えなくていいです。
化学式やモデル図で、「炭素原子(C)と水素原子(H)がふくまれていること」に注目してください。
ほとんどの有機物には炭素と水素がふくまれています。
このため、有機物が酸化すると水と二酸化炭素を生じます。
【例】
・石灰水を入れた集気びんの中で有機物を燃やすと、石灰水が白くにごり、びんが白くくもる 。
実験図
エタノールの燃焼では二酸化炭素と水が生じます。化学反応式のつくり方はこちらで紹介しています。
・細胞の呼吸とは、養分(有機物)と酸素からエネルギーを得ることである。
そのとき、水や二酸化炭素などの不要物も生じる。
こちらで思い出してください。
top > 化学エネルギー > 酸化と還元 > 有機物の酸化