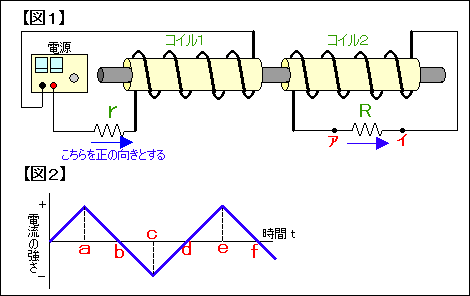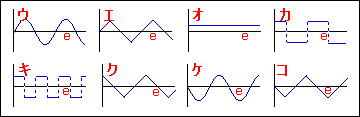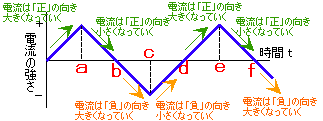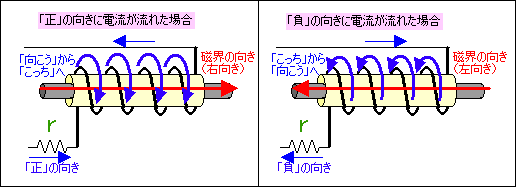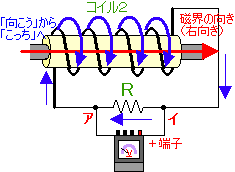|
図1のように、コイル1と2を共通の鉄心に通し、コイル1には抵抗
r と、
図2のように変化する電流(図1の矢印の向きを正とする)を流す電源とをつなぐ。
コイル2に抵抗Rをつなぐとき、次の各問いに答えなさい。
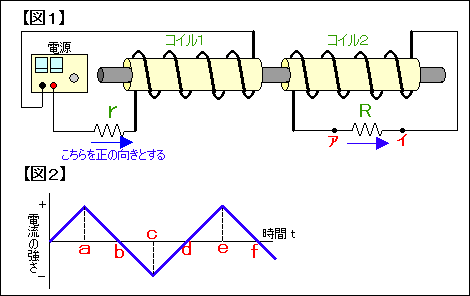
(1)コイル1によってできる、図1の鉄心の中を通る左向きの磁界がふえて
いるのは、図2のどの時間帯か。a〜b、a〜cのように答えよ。
(2)a〜bの時間に,Rの両端の電圧をはかるとすると、アとイのどちらを
電圧計の正端子につないだらよいか。記号で答えよ。
(3)Rに流れる電流のおよそのようすを示すものは下の図のどれか。
ウ〜コの中から選んで、記号で答えよ。
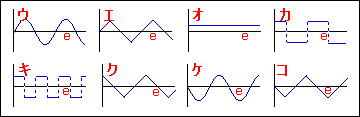
ご質問: keiichiroさん(2003/1/6)
|
(1)
交流電流のように電流の向きと強さが定期的に入れ替わる場合でも、
コイル1がつくる磁界の向き…電源の電流の向きで決まる
コイル1がつくる磁界の大きさ…電源の電流の大きさで決まる
|
ということだけ、まず考えましょう。まだコイル2のことを考える必要はありません。
図2をもうちょっと詳しく見ていきます。
電流の大きさは絶対値で考えます。(「負」の向きなら下にいくほど電流は大きくなります)
【図2補足】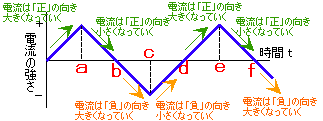
今度はコイル1に電流が流れた場合、どんな磁界ができるか考えてみます。関連ページ
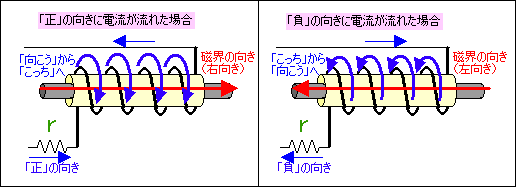
「左向きの磁界がふえている」=「負の向きの電流が大きくなっている」ということなので、
ひとつ上の【図2補足】で 電流は「負」の向き 大きくなっていく という部分をさがすと、
b〜c、または f 以降ということになります。時間帯の始めと終わりの記号があるのはb〜cです。
(2)
今度はコイル2も関係してきます。コイル2にはどの向きに電流が流れたか、という問題ですね。
コイル1に電流を流すと、コイル1は磁界をつくります。
この磁界は鉄心によってコイル2の中にも生じています。
コイル2は磁界の変化にさからうように磁界を新たにつくろうとし、誘導電流がコイル2に発生します。
これが電磁誘導という現象でしたね。関連ページ
a〜bの時間にコイル1がつくった磁界にどんな変化があったか考えてみれば、
コイル2がどちらに電流を流したいと思ったか、わかります。
上の【図2補足】で、a〜bの時間帯には電流は正の向きで小さくなっていきますね。
コイル1は右向きに磁界をつくっていますが、磁界そのものは小さくなっていきます。
右がN極の棒磁石を離していくときと同じ状況ですね。
|
コイル2は小さくなっていく磁界をもとにもどそうと、
もとと同じ右向きの磁界をつくろうとします。
コイル2に「イ→ア」の向きに誘導電流が流れるので、
電圧計をつなぐなら、+端子は「イ」のほうにつなぎます。
(+端子は電流が流れ込む端子です)関連ページ
|
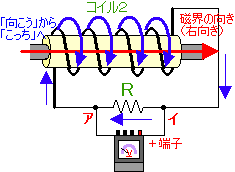 |
(3)
電源の電流の変化→コイル1がつくる磁界の変化→コイル2がつくろうとする磁界→誘導電流
という感じで考えていきましょう。
この場合、コイル2の誘導電流の大小は、「磁界の変化の割合」で決まります。
誘導電流は磁界が変わったときだけ瞬間的に生じるもので、磁界が安定するともう電磁誘導は起きません。
この問題の場合、常にコイル1の磁界は向きが変わったり大きさが変化していますが、図2のグラフより、
コイル1の各時間帯での磁界の変化の割合は一定です。(グラフが直線的)
このことより、そのときコイル2に生じる誘導電流の大きさも一定である、といえます。
コイル1の磁界の変化にさからうように一定の大きさの誘導電流が発生する、ということですね。
以下にまとめました。時間帯ごとに確認していってください。
| 時間帯 |
電流の変化 |
コイル1の磁界 |
コイル2の磁界 |
誘導電流 |
| 原点〜a |
正の向き・強くなる |
右向き・強くなる |
左向き |
正の向き(ア→イ) |
| a〜b |
正の向き・弱くなる |
右向き・弱くなる |
右向き |
負の向き(イ→ア) |
| b〜c |
負の向き・強くなる |
左向き・強くなる |
右向き |
負の向き(イ→ア) |
| c〜d |
負の向き・弱くなる |
左向き・弱くなる |
左向き |
正の向き(ア→イ) |
| d〜e |
正の向き・強くなる |
右向き・強くなる |
左向き |
正の向き(ア→イ) |
| e〜f |
正の向き・弱くなる |
右向き・弱くなる |
右向き |
負の向き(イ→ア) |
| f〜 |
負の向き・強くなる |
左向き・強くなる |
右向き |
負の向き(イ→ア) |
よって、誘導電流が
正→負・負→正・正→負・負
と変わっていくグラフを探すと、「カ」のグラフですね。
|
 |
答え
問題データベース目次へ