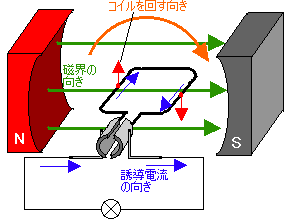|
電磁誘導…コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電流が流れる現象 誘導電流…電磁誘導によって流れる電流 |
|
コイルと検流計をつないで、
コイルに棒磁石を近づけたり 遠ざけたりし、 検流計の針のふれを調べる。 | 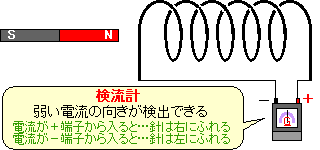 |
|
N極をコイルに 近づけた場合 コイル内の磁界が変化するので、反発するためにコイルの磁石側にN極が生じる | 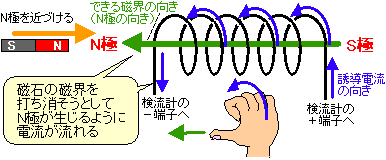
※S極を近づけた場合は磁石側にS極が生じる(針は右にふれる) |
|
磁石を止めた場合
コイル内の磁界の変化がないので、誘導電流は流れない | 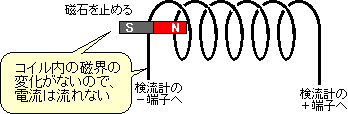
※磁石をゆっくり近づけたり遠ざけたりしても誘導電流は流れません。 |
|
N極をコイルから 遠ざけた場合 コイル内の磁界が変化するので、もとにもどすためにコイルの磁石側にS極が生じる | 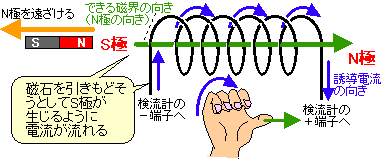
※S極を遠ざけた場合は磁石側にN極が生じる(針は左にふれる) |
コイルはコイルの中の磁界の状態をそのまま維持しようとしているだけです。
磁石が近づくと反発するように、遠ざかると引きもどすようにコイル内部に磁界をつくろうと誘導電流を発生させます。
コイルの巻き方と検流計のふれ方
↑の例の場合、磁石のN極を近づけた場合に検流計の針が左にふれ、磁石のN極を遠ざけた場合に検流計の針が右にふれましたが、近づけた極と針のふれをこのまま覚えてはいけません。
コイルの巻き方によって針がどちらにふれるかが決まるので、コイルによって結果が反対になります。
巻き方が逆になった2個のコイルの例を見てみましょう。
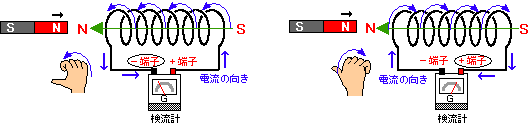
どちらも「コイルにN極を近づけたとき」ですが、検流計の針のふれは逆になっていますね。
どちらもコイルの左側がN極になるし、コイルを流れる誘導電流は「こちら側から向こう側」になっていますが、回路を流れる誘導電流の向きが逆になっています。
コイルによって違う結果になるんですね。
「コイルの端に磁石のN極を近づけたら検流計の針が左にふれた」などと条件を提示されてから、「ではS極を近づけた場合どうなるか」という問題なら簡単ですが、コイルの図しか与えられていない場合は、
|
1.磁石側のコイルの端には近づけた極と同じ極が、遠ざけた極と違う極が生じる 2.コイルの端の極が1になるように誘導電流の向きを右手で調べる 3.誘導電流が検流計の+極から入った場合右に、-極から入った場合左にふれる |
となるようにして検流計の針のふれ方を求めましょう。