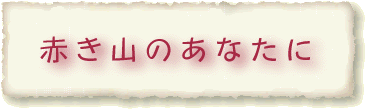
2002.5.15
――冷たい……!
冷水を浴びせかけられたような気分で目が醒めた。
いや。
本当にびしょ濡れだ。
ご自慢の長いストレートの髪が、顔に張りついている。
体中が寒い。
凍えそうだ。
せめて顔をぬぐおうと手を動かそうとして、なにかに引っかかるのを感じた。
もう一度動かす。
ほの暗い中、前に暖炉の火が見える。
これは、懐古趣味な……。
やはり、手は動かない。
どうも真上で冷たい金属製の手かせをはめられているらしい。
動かすと、チャリチャリと鎖の音が響き、ゆらりと円弧運動をする。
おおかた、この手かせは上から鎖で吊るしてあるんだろう。
目だけでぐるりと室内を見渡す。
円筒形のほの暗い小部屋。
あたりに転がっているいくつかの器具を見る限り、ここは中世趣味の拷問部屋だ。
右側に、アリアドネ=うめ、ルー、JDがあたしと同じ恰好でぶらさがっていた。
宇宙服(スーツ)を脱がされ、中の薄いインナーだけの、ちと情けない恰好。
まるで丸焼きを待つ、毛皮を剥がれたウサギの図。
だから、インナー業界にも、もうちょっとデザインに力入れてほしかったのに……。
それらを、実は一瞬で見て考えたのだ。
一応プロだからね。
そして、目の前には、あの人が水道のホースを持って立っていた。
これで、あたしをびしょびしょにしてくれたらしい。
「気がついてくれたかい?」
白い歯を見せて、あの人は笑った。
黒い巻き毛、低い声。
あの日あの時のそのままに。
でも、その開いた唇は、あまりに形よかった。
「ニセモノ……ね」
あたしはつぶやいた。
あの人は食べ物を左で噛むクセがあり、だから左顎が発達してしまって、唇だって左の方が余計に開いたのだ。
そのいびつさが、目の前のこの男には、ない。
「君たちが見かけた方がニセモノだよ」
ニヤッと、その男が笑った。
「ヤツは今、どこにいるんだい?」
あたしはプイと横を向いた。
横目でちらりと見るこの男の表情は、やはりあの人のものではない。
あの人の目は、こんなに鋭くない。
もっと野暮ったくて、もっと目尻の笑いじわが多い。
バシュッ。
冷水がほとばしった。
うっぷ。
氷水のようだ。
「君たちが見かけたのは、私の弟クローンだよ。あいつの方が三年遅れて作られた。
あいつは私を裏切った。ここを自分のものにしようとした」
遠い目、恍惚として表情。
「だが、形勢は逆転し、あいつは脱出を図った。宇宙空間に出たあいつを、私は人を雇って撃たせた。そのつもりだった。だが、生きていたんだな。
君たちが見かけたのは、それだ」
?
なんのことだ?
「あいつは、ここを奪いかえそうとしているんだな? それで君たちを雇ったんだな?
おまけに、君はヤツに惚れてるときた。
君はヤツのなんだ? 恋人のつもりか? それともタダの信奉者か?」
「……あんた、火星独立の英雄の何代目かを気取ってるそうだけど?」
カマをかけてみる。
「あいつが、自分こそは正当な継承者だと言っているんだな? ふん。くだらん。
あいつの人間離れした頭脳と肉体を見て、君もそれを信じたんだろう。
だが、あんなもの、私だって持っている。
我々は、見かけこそくだらん人間どもと同じだが、ここで作られた優れた新人類だよ。
我々こそが、真の火星人だ。
そして、その火星人の王が、私だ。わかるかい?
もう、くだらん人間どもの時代は終わりだ。
私は手始めに、人間どもの手から、この場所を取り返してやった。
ここを拠点に、火星全体を手に入れてやる。人間どもが勝手に作った火星政府なるものがあらがってはいるが、偉大な火星人の力の前に、為すすべもなく、じきにひざまずくだろう。
次は地球、やがては、ソル星系も、外宇宙も、私たち火星人のものになる」
そうか。
こいつのおしゃべりのおかげで、状況がわかってきた。
こいつは、ここで開発された人類の亜種なんだ。
そして、同じく開発された亜種の一体と覇権を争ったが、敗れたその一体とあたしらが協力してここを取り戻しに来たと思っているんだ。
あたしのあの人は、遺伝子操作の元になった素材でしかない。
「……あんたたち、なにを好んで歴史上の人物の姿なんかしてんの? もうちっとマシな姿はなかったんかい?」
「独立の志士を鼓舞したあの詩の作者の姿というのも、そう悪いものではない」
うれしそうに笑う。
丸い鼻先、小さな小鼻、ぽってりした唇。
あの人のかわいい表情そのままに。
……若干の違いはあるにせよ。
「君たちは幸せだよ。新しい火星人の未来のために貢献できるんだからね」
「どういう意味よ」
目をそらせながら訊く。
「君たちの遺伝子を使って、真の火星人が生まれるんだ。考えてもみるがいい、君たちにそっくりな火星人たちが、街を闊歩(かっぽ)し、この宇宙に君臨するさまを」
「そりゃ贅沢がすぎるってもんだ。あたしそっくりの美女が大勢いるだって?」
男は肩を揺らしながら笑った。
まるであの人そっくりに。
「意地を張るのはやめたまえ。すばらしい新人類の祖と、君の名は残り、称えられるんだよ」
「名前なんか犬にでもくれてやるわよ」
「意地を張らずに、そろそろ教えてほしいな。あいつはどこにいる?」
そんなもの、知らないのである。
「自白剤や薬は使いたくないんだ。たいせつな素材だからね。特に、女性は手厚く扱いたい」
「……孕(はら)ませるためにね」
「下品な言い方はやめてくれないか。さあ、そろそろ教えてくれ。あいつはどこにいる?」
何度訊かれようが、知らないものは知らないのである。
だいたい、そいつって本当に死んでるんじゃないのか?
「しかたないな」
男はため息をついた。
「結城くん、来たまえ」
「はい」
暖炉のわきで影が動いた。
こちらに歩み寄ってくる。
結城マサキだ。
「あの子をやれ」
アリアドネ=うめを指差した。
細長い針を手渡す。
「目を一突きだ」
「はい」
結城マサキはためらいもせず、アリアドネ=うめの前に立つ。
ぎくっ。
洗脳されているのか?
「ちょっと、あんたの妹でしょ!」
ムダかもしれないと思いつつ、叫ぶ。
結城マサキは首を傾げた。
「穢(けが)れを防ぐのは、兄として当然の行為です」
「穢(けが)れ? 目をつぶすことが?」
「そうです。これ以上穢(けが)れてしまうのはかわいそうです。ぼくだって研究がなければ自ら目をつぶしたいくらいだ」
「なんなのよ、その穢(けが)れって」
スッ。
指があたしに向かって一直線にのびた。
「あなたです」
「あたし?」
い、いや、確かに今汚れて真っ黒だけどさ、でもそれは風呂入ってきれいにすれば、元の美女に……。
「その赤毛が最悪だ」
「はあ?」
「赤毛といえばおさげ! 可憐なアン・シャーリーにしか許されない純情美少女アイテム! こんな怖いオバサンがふり乱していいものじゃないっ! ああ、穢(けが)れている! 目がつぶれてしまう!」
「こぉのあほんだら〜!!」
あたしの絶叫が効いたのか、アリアドネ=うめとルーが目を醒ました。
「あ、おにいちゃま。無事だったのね?」
「ああ。今、穢(けが)れから解き放ってあげるからね」
結城マサキはやさしく話しかけ、アリアドネ=うめに手を伸ばした。
「おっ、おにいちゃまっ! なにするのっ!」
「怖がることはないよ。ぼくが今……」
「いっ、いっやあ〜っ!!」
ゴフッ。
形容しがたい音が響いた。
ドタッ。
結城マサキが崩おれる。
気を失っているようだ。
あああ……。
そりゃ、アリアドネ=うめの足の、あの場所への、あの一撃をまともに食らっちゃあなあ……。
合掌。
「おやおや。元気のいいお嬢さんだね。これは楽しみだ」
笑ってやがる。
あたしは黒髪のそのエセ・コピーをにらみつけた。
と。
「このイカサマ師! おにいちゃまになにさせるのよ! ペテン師! スケベ! アンポンタンのコンコンチキのチンチクリン! ――(以下倫理規定により削除)――」
アリアドネ=うめがとてもお伝えできないよう罵詈雑言(ばりぞうごん)を浴びせかけた。
これでも、お嬢さまなのか?
「そうだ。こっちの方が君には楽しいかもしれないね」
ドクター・ジュニアはくすくす笑った。
「おいで、コピーF一一〇六二」
やはり暖炉のわきで影が動いた。
歩み寄ってみれば、もう一人のドクター・ジュニア。
「あいつとうりふたつのコピーがお仲間に手を下すのを見るのは、どんな気分かな?」
ニヤッと笑う。
なんて汚いヤツ!
「ふん。あたしを直接痛めつけた方がてっとり早いんじゃないの」
「それじゃつまらないじゃないか」
いまいましいコピーもどきが肩を揺らして笑う。
「君自身の痛みに、他人の痛みが加わる。その方が、君もしゃべりやすいかと配慮したまでのことだよ」
なんて! なんて汚いっ!
「試しに、さっき代わりにそちらのレディに話してもらったんだが、夢のような話でごまかされてしまってね。どうしても、君に話してもらいたいんだよ、真相をね」
ルー!?
「……だって、おねーさん、しかたなかったんだよ……」
ルーが泣き声で言う。
たぶん、事実を語ったのだろう。
が、それをこの目の前のニセモノ野郎は信じなかったのだろう。
「すごく叩かれたんだよ」
「いいよ、ルー。わかってる」
ルーが痛みに対して耐性がないのはわかっている。
「違うの。わたしじゃないの。JDなの。叩かれて、気を失ってもムリヤリ起こしてまた叩いてのくり返しだったの。見てられなかったの」
JD?
ずぶ濡れになりながら、ぐったりと吊るされている小さな少年。
「そうだ。この坊やにしよう」
ドクター・ジュニアは勢いよく冷水をJDに浴びせかけた。
JDの体がぶるっと大きく震えた。
わずかに顔をあげる。
「コピーF一一〇六二、やれ」
「はい」
あの人そっくりの人形が、JDの前に立つ。
「来んじゃねえ」
かすれた声がイキがった。
が、もはや力尽きているのか、人形の力に逆らえない。
インナースーツはボロボロになっていたらしい、薄暗くてよく見えないが、腕のところから服が引きちぎられ、上半身があらわになる。
まだ成長過程でありながら、ほれぼれするような筋肉質の体。
あたしがひきとってからは、いっそうその鍛練に拍車がかかったようである。
まだ一年も経たないというのに、よく鍛えたものだ。
「彼はなかなかいい体をしているね」
ドクター・ジュニアがペロリと口の周りをなめた。
「一つ一つそぎ落としても、おもしろそうだ」
こいつ、目だけじゃなく、指や足までもぎ取る気か?
「近寄んじゃねえ」
アゴを抑えられてあらがうが、ケンカにならない。
JDと初めて会ったのは、とある富豪の大邸宅だった。その富豪の愛人としてかこわれていたのだ。
その昔は男娼として街頭に立っていたという。
客の中にはアブナイヤツもいて、さんざん痛い目にも遭ってきている。
だから、こういうことには馴れている。
でも、こいつは、あたしにその手の話をされることが大嫌いだった。
過去を捨て、生まれ変わったのだと思いたかったのかもしれない。
なのに、今あたしの前でこんな醜態をさらしたら。
「姐さん」
うす暗くてよく見えないはずなのに、JDが目をつぶっているのがわかった。
「なにも話すことはありませんよ。こういうことは、オレ、馴れてますから」
ツッキィィィーン。
胸ン中を鋭い痛みが貫いた。
「ウチの子に手を出すんじゃないよっ!」
あたしはドクター・ジュニアに蹴りを入れた。
充分に距離をとっていたはずなのに。と、そのクズ野郎の目に驚愕が走った。
そのスキを、あたしは逃さなかった。
トドメだっ!
もう一度、眉間に違わず踵落としを入れた。
ドクター・ジュニアがその場に崩れる。
首が妙な方向に折れ曲がり、眉間の割れ目から白い物が流れ出ていた。
「ふうーっ」
あたしはコキコキと手首の関節を入れた。
うう〜っ。痛つぅ〜。
これ、あんましやりたくなかったんだよな……。
関節を外して、いましめを解いたのである。
こんな芸当がやれるとは、予想だにしなかったのだろう。
暖炉のわきに控えていたらしいコピーたちが一斉に向かってくる。
主人を守れとでも教えこまれているんだろう。
どれもこれもがレイフの顔だ。
でも、どれもこれもが人形でしかない。ただのでくのぼうだ。
あたしの相手なんかじゃなかった。
一個のコピーが鉄の棒を振りまわしてきた。
飛んで火に入るなんとやら。
あとは簡単だった。
その獲物を奪いとり、あとはせっせと撲殺に励めばよかった。
最後に、火星人の王を気取るエセ・コピーの前に立った。
死んでいるのか、気を失っているのか。
「あばよ」
頭に打ち降ろすと、生命を司る白いモノがぐしゃぐしゃに飛び散った。
くそっ。なにが新人類だ。
気分が良すぎて涙が出るぜ。
そのドクターとかであったものの体を鉄棒でまさぐると、固いものに当たった。
レーザー銃だった。
あたしたちが常用しているものより、出力は劣る。
でも、ルーたちを束縛している鎖を断ち切るには充分だった。
「JD、歩けるかい?」
「歩けますよ」
気丈に言うものの、少年はふらふらだった。
鮮やかなメタリックブルーの髪が、あたしの頬に触れた。
「おにいちゃまを」
アリアドネ=うめが言った。
「おにいちゃまを連れて行って」
「あんた、自分がなに言ってるのかわかってんのかい? あんな目にあっといて」
「おにいちゃまが悪いんじゃないわ。そそのかされたのよ。そりゃあ、私のかわいい唇に触れようとはしたけど、でも、連れて帰ったらきっと元のおにいちゃまに戻るわ!」
あたしは苦笑した。
このお嬢さまは、自分がなにをされそうになったのか、正しく把握してないらしい。
が、ここでそれを指摘する気にもならない。
「了解。依頼人の要求には応えますとも。エルファーレンの名にかけてね。ルー、JDをお願い」
「姐さん、足手まといになるくらいなら、置いてってください」
「ばぁか。あんたみたいな小生意気なガキ、こんな腐れ研究所だってもてあましちまうよ」
あたしはJDをルーに預けて、結城マサキを肩に背負った。
「ほら、行った行った。とっととこんなゴミ溜め、トンズラするよ」
ドクター・ジュニアが命令しておいたのか、通路には、たくさんのコピーたちが待ち構えていた。
だから、獲物を屠(ほふ)るのには申し分なかった。
途中でそいつらの銃をしこたまガメて、次のコピーたちを迎え撃った。
あんまりレーザーを撃ったものだから、まぶしくて目が潤んだ。
照準がズレちゃマズいので、何度も何度も袖で目を拭いた。
袖は、さっきかぶった冷水のせいか、いつまでも乾いてくれなかった。
つづく
![]()