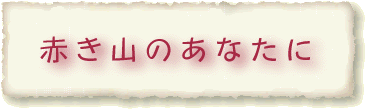
2002.5.8
「ねえ、おにいちゃま、ここから外に出るのには、どこが近道なの?」
アリアドネ=うめが訊いた。
「さあ。外に出たことがないからわからないよ。
ここは理想都市なんだ。外に出なくとも、自給自足で生活できる。
そのうちスペース・コロニーも、ここのシステムにこぞって倣うだろうね」
「すっご〜い」
「ボクのフォアグラ工場も、そうした研究の一環なのさ。すべて人類の未来につながっている。世界はボクらの手によって発展していくんだ。
この研究所を仕切っているドクター・ラルフレッド・フロイ・ジュニアはすごい人だよ」
ギクッ!
ラルフレッド……フロイ……ジュニア……?
「誰なんです?」
JDが訊いた。
「偉大な人だよ。人類のすばらしき時代への指導者だ。
この研究所に人類の未来縮図を展開している人だ。
あの、火星の偉大な指導者ラルフレッド・フロイの何代目かの子孫にあたるそうだ」
ぶるっと肩が震えた。
子どもだって?
そんな話は聞いていない。
あたしが知らないだけか?
それとも、何者かが名前を語っているだけか?
「ボクはここを出たら、彼のすばらしい偉業を外の人々に伝えるよ。そして、彼と外との橋渡しをしよう」
「え? でも、ここに閉じこめられてたんでしょう? おにいちゃま」
「そんなことあるものか。あんまりすばらしいんで、今までボクが出ようと思わなかっただけさ。だって、外の世界はそうとうくだらないらしいからね。
フォアグラ工場を見たんなら、うめも見たんだろう? 彼の実験場。たくさんの新しい生命があったろう?」
「おにいちゃま……。あれは……」
「うめも遺伝子学者なら、あのすばらしい実験の成果を見ただろう。
ここにはヘンなタブーがない。自由なんだ。すばらしいよ。これで、どこのコロニーも飢えることがない。ボクらのコロニーで昔あった人肉さえ食べたというようなどうしようもない飢えは、もうあり得ないんだ。
いいかい? 太陽光と水と若干の葉緑素があれば、簡単にじゃがいもができるんだよ。内臓移植用に、内臓の一部分だけをクローンすることだってできるんだ。すごいだろう?」
「……おにいちゃま。それはどっちも、もうとっくに実用化されているのよ」
「なに寝ぼけたことを言ってるんだい、いいかい……?」
「おにいちゃまは小さいうちにここに閉じこめられたから知らないのかもしれないけど、そんなの、何十年も前から常識なのよ。
あの実験場の実験体だって、無意味なものばかりよ。遺伝子研究の参考なんかにはならないわ」
「なに言ってるんだい。ドクター・ラルフレッド・フロイ・ジュニアがムダなことなんかするもんか。彼は常に外の世界に目を向けてだね……」
すっかり、そのドクター・ジュニアとかいうヤツに洗脳されているらしい。
施設の上のあれだけの警備を見る限り、彼が言う、その気になれば外に出られたというのは不可能だ。それを、彼はまったく知らないのだ。
ムリもない。
苦労しらずで神童と持ち上げられていた両家のお坊っちゃんが一〇年以上も閉じこめられていたのである。
「そうそう。出て行く前に、ドクター・ラルフレッド・フロイ・ジュニアに挨拶していかなくちゃ」
バカか、あんたは。
ツッコミたいのに。
ラルフレッド・フロイの名を訊くと、腕の震えが止まらない。
「ドクター・ラルフレッド・フロイ・ジュニアは、この先の研究室にいるはずだよ」
「おにいちゃま。やめましょう」
「やめるって、なにを?」
「このまま外へ出ましょう?」
「なに言ってるんだい。散々お世話になっておいて、黙って出るわけにはいかないだろう?」
「いくらなんでも、私にだってわかるわ。そのドクターなんとかっていう人は、おにいちゃまを外に出したりはしないわ」
「おいおい、ドクター・ラルフレッド・フロイ・ジュニアを疑ってるのかい?」
結城マサキは笑う。
「おにいちゃま、私がここまで来るにはたいへんだったのよ」
「いろいろと苦労したのかい? たいへんだったね。でも、研究には機密保持がつきものだからね。わかるだろう?」
「おにいちゃま!
私が自分自身でここに来たのは、ひいおばあさまが昔、ここで化学兵器の開発をしていたって、手紙に書いてあったからなの。たくさん人体実験をして、兵器の威力を試したっていうわ。
そして、その途中でひいおばあさまも実験体にされそうになって、ここを脱出して、ひいおじいさまに助けられて結婚して、その知識を使ってたくさんの兵器を作って、それで結城家は巨額の富を築いたのよ!
そのことを知った時、私はどうしてもその元になったものをこの目で見なくっちゃって思ったわ。
わかる? ここはそんな罪深い場所なのよ! そこで引き続き人体実験なんかやってる人を、どうして信じられるの!」
そうだったのか。
このお嬢さまはお嬢さまなりに、よく考えてきたんだ。
二年間も親を説得し、承諾させるほどに。
「考えすぎだよ、うめ。会えばわかるよ。ドクター・ラルフレッド・フロイ・ジュニアはすばらしい人だよ」
「失礼」
JDが動いた。
結城マサキのみぞおちに手刀を入れる。
「うっ」
うめいて、気を失った。
「な、なにするの!」
アリアドネ=うめが悲鳴をあげる。
「ちょっと眠ってもらったんですよ。説得はムリのようでしたからね」
結城マサキの体を肩に担ぐ。
「急ぎましょう」
「あ、ああ、うん」
あたしは不器用にうなずいた。
小走りに来た道をたどる。
他の道は知らない。
確実にVTOLまで帰るには、これが一番早い。
「おねーさん、あのドクター・ジュニアとかって、ほんとに彼の……?」
「知らないわよっ」
ルーの問いに乱暴に答える。
ルーもまた、あの屍を見た一人だ。
あの人の恋人だったあたしと、その妹であるルーは、当時、地球から追われていた。
あたしたちの兄貴ってヤツは地球の科学者で、結城兄妹のひいばあさんのように、兵器の開発に携わっていたのだ。
その兄貴がスパイの嫌疑をかけられ、実家に帰ってるところを殺された。両親とともに。
あたしが駆けつけた時には、すでに遅し。
家具類はメチャメチャに切り裂かれ、兄貴も両親も無惨に転がり、動くものはなかった。
ただひとつ、あたしが道楽で買った柱時計だけが、表面を傷つけられただけで済み、時を刻み続けていた。頑丈なだけが取り柄の、よく狂う時計だった。
その扉を開けた時の驚き!
真っ赤に目を腫らし、すっかり筋肉がこわばって動けなくなった妹が、息をひそめて隠れていたのだ!!
あたしは妹を連れて火星へ戻ったが、けっきょく、地球の傀儡(かいらい)である火星政府に連行されかかり、一緒に火星を逃げ出したのだ。
そして、土星の衛星で長いこと、眠っていた。
冷凍睡眠から醒めたのは、二〇〇年以上を経た現代だった。
あたしとルーは二人きりの姉妹だが、いろんな意味でも二人きりだった。
「ちょいお待ち!」
とっさに肌が総毛立って、ルーの手を引いた。
「え? なに?」
問うのと同時に、ルーがいた場所に一筋の光が閃いた。
ジュッ。
床が溶ける。
レーザー銃だ。
慌てて、廊下を曲がり、身を隠す。
「君たちは、ここから生きて出られはしないよ」
低音の、やわらかな声が、廊下いっぱいに響いた。
ゾクッ。
背筋に凄まじい悪寒が走った。
「誰だっ」
JDが叫んだ。
「ラルフレッド……。そうだな。愛称で呼んでくれて構わないよ。レイフ・フロイと」
嘲るような響き。
レーザー銃が乱射される。
くっ。敵は複数か?
チラリ、とそちらを見やると、黒い巻き毛の短髪。やや痩せぎみの体。
たくさんの、レイフ、レイフ、レイフ。
アンドロイドかもしれない。
が、外見は、あの人そっくりだった。
肩が、腕が、足が震え始める。
「なに、あれ!」
ルーが叫ぶ。
JDが応戦する。
正確に頭部を粉砕される、アンドロイド。
いや、違う。
飛び散る肉片。
「ちょっと、まさかヒト?」
「クローンかもしれませんね。それとも、整形を施されているのかも。催眠状態にあるのか、それとも命令をきくだけしか能がないのか。少なくとも、敵であることに変わりはありませんよ」
ルーの問いに、冷静に答えるJD。
「そ、そーよね。たしかにレイフは死んだんだから」
ルーがつぶやくと、
「死んだ方がニセモノかもしれないよ」
どこからともなく聞こえる低い声がからかうように言った。
「整形を施された他人の死体に立ち会ったのかも」
「……死んでない?」
あたしは思わずつぶやいた。
「あの人は、死んでない?」
「さっきの君の愁嘆場はおもしろかったよ。私のできそこないのコピーに絶叫して。また、楽しませてくれないかな?」
ふざけるな、と思った。
思ったが、この声を聞くと、なにも言えなくなった。
「貴様、どこにいるっ!?」
JDが怒鳴った。
「目の前にいるだろう。私のコピーが」
嘲笑。
攻撃が激しさを増した。
JDとルーが必死に応戦する。
この嘲笑。
厭だからやめてと何度も頼んだのに、あの人の唇から時々漏れた笑い方。
あの人は……、生きてるの? 死んでるの?
「姐さん、行きますよ」
JDがあたしの腕を引いた。
いつしか銃撃はやんでいた。
「姐さんっ!」
「あ、ああ……」
腕を引かれるままに、角を出る。
散らばった、たくさんの、あの人の、かけら。
めまいが、した。
「そうそう。いい眺めだ。もっと私を楽しませてくれ。近頃、退屈してたんでね」
「ちくしょう。どっから見てやがる」
JDが歯ぎしりした。
「姐さん、目をつぶって」
「ああ……」
「ったく、もう!」
JDは首に巻いていたバンダナをあたしの頭からかぶせた。
「それとっちゃダメですよ! ほら、手を引きますから、ついてきて」
JDがあたしの手を引いて、小走りに駆け出した。
肩に結城兄を背負っているというのに、なんてガキだろう。
血の匂いが鼻に突き刺さる。
あの人の、血の、匂い……。
涙があふれて、止まらなくなった。
三年一緒に暮らした。
ルーを守らなければならない立場でなかったら、あの場であたしも自害して果てていただろう。
半身を失った痛みというのは、こんなことかと思った。
「ほらほら気をつけて」
声とともに、あたしの足元の床が抜けた。
「危ないっ!」
あたしの腕を、二人の手がつかんだ。
ルーとJD。
アリアドネ=うめもその後から来て、あたしを引き上げるのを手伝う。
バンダナは下へ落ちてしまったようだ。
視界が開けている。
「姐さん、しっかりしてください!」
引き上げられると、JDが言った。
「姐さんがしっかりしないと、みんなおだぶつですよ! アリアドネさんも、そのおにいさんも、ルリーズさんも!」
「そうよ! おねーさん、わたしたち、二人きりなんだからね! わたし一人にしないでよ!」
そうだ、しっかりしなくては。
よろよろと立ち上がった。
「そうそう。がんばれ」
トーンの低い嘲笑。
「行きましょう」
JDは、あたしを引き上げるのに一旦降ろした結城兄を担ぎ直した。
ガタンッ。
ガタンッ。
いきなり、後ろの床が一斉に抜け始めた。
「走れっ!」
ぼんやりしているあたしの手を、JDが引いた。
後ろからだんだんに抜けてくる床。
走らなければ、逃げられない。
あたしたちは、走った。
息が切れても、なお走った。
このまま走ったら、あの、忌まわしい実験場に追い込まれてしまう。
予想がついたが、他に手はなかった。
実験場の扉を目にしても、打つ手はなかった。
扉の壊れたその中に飛びこむ。
「ようこそ。実験体の諸君」
嬉々として、その低い声は言った。
よくあの人はこんな声を出した。
愉快そうに身を揺らしながら。
「たくましい素材が入って、うれしいよ。知能の高い素材はかなり集まったが、すぐれた肉体の素材はまだまだ少ないからね。
特に若くて健康な女性は大歓迎だよ。大事な母胎として優遇させてもらうよ」
「どこにいるのっ!? 出てきなさいよッ!」
ルーが叫んだ。
「メットをかぶってください、ルーさん」
JDが言った。
「うめさんも。姐さんも」
「おにいちゃまは?」
「今はしかたありません。催眠ガスでもかがされたら、おしまいでしょう?」
「用心深いことだ」
嘲るような笑い声。
あたしたちは急いでメットをかぶった。
用心にこしたことはない。
「だけどね、その用心も意味がないこともあるんだよ」
不意に、床が抜けた。
あっと手掛かりを探したが、いかんせん、穴が大きすぎた。
為すすべなく、あたしたち五人は、奈落の底に落ちていった。つづく
![]()