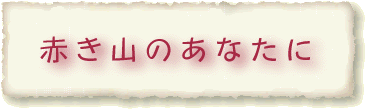
2002.4.24
薄暗い研究施設内を、赤外線スコープで見渡しながら、そろそろと進む。
下へ行けば行くほど、施設はアヤシくなっていく。
「聞きそびれたけど、あんたの兄貴って、ここでなにやってんの?」
あたしはアリアドネをエスコートしながら訊いた。
通信機を通じて、ルーも、別行動のJDも聞き耳を澄ませているだろう。
「一二年前、兄がとつぜん行方をくらましてしまったんです」
アリアドネは語り出した。
「当時兄はまだ一三歳で、前途有望な神童と呼ばれていました。
人まで雇って探したんですけど、今まで見つからなかったんです。
でも、家の改装の時、ひいおばあさまの手紙を見つけて、これだってピンと来たんです。
兄は歴史が好きでした。
地球と火星の歴史が特に好きで、小さい私によく話を聞かせてくれました。
それで、おとうさまに調べてもらったら、兄らしい子どもを火星の第四キャナルシティで見かけたという証言が複数あったんです。
ひいおばあさまの手紙の入ったディスクも、箱の中から出しておかれていました。兄が読んで、そのまま置きっぱなしにしたんだと思います。
だとしたら、ここに向かったに違いありません。
きっと、この中に兄は閉じこめられているんです。
ムリヤリ働かされているんです。
助けてあげないと……」
「で、なんであんたがわざわざ行くわけ?」
「だって、兄なんですよ? 女の子なら誰だってすてきなお兄ちゃんがほしいと思うでしょう? それが自分の手でかなえられるんですよ?」
両手を胸の前で組み合わせ、瞳はキラキラ、まるで少女マンガ。
あたしは肩をすくめた。
「ま、いーけどね……」
「おねーさん、わたしはちっともよくない……」
ルーがぶーたれた。
「ちとお待ち」
ふと気がついて、レーザーの照準を合わせる。
狙いを定めて、発射。
「行こ」
研究施設内は、機密保持のためか、警備の人間をまったくと言っていいほど見かけない。
その代わり、厳しいセキュリティ・システムが働き、こちらを攻撃してくる。
たぶん、侵入者の存在はとっくにバレているのだろうが、幾重にも張り巡らされたシステムの中でいつかくたばると思ってるに違いない。
もしかしたら、あたしたちのさまをおもしろがって眺めてるかもしれないのだ。
でも、おあいにく。
こんな古いシステム、あたしにはどこになにがあるかなんてお見通しなのだ。
昔の火星人の思考パターンなんかたかがしれてる。
いくつものテレビカメラ、いくつもの武器を破壊して、奥へ奥へと突き進む。
「おねえさまとルーさんは、もともと火星の方なんですか?」
ふと、アリアドネが思い出したように訊ねた。
「地球だよ。火星には三年いたの」
「ルー!」
あたしは短く制した。
「レイフさんって、誰なんですか?」
鈍感なのか、アリアドネはまだ訊いてくる。
「そんなことよりアリアドネ、ここじゃ、なんの研究してんだい?」
「見てもらえばわかります」
りーが。さらに奥にある部屋の入り口のセキュリティボックスをレーザー銃で破壊し、ドアに手をかける。
「お待ち」
あたしは銃身でその腕を叩いた。
「不用意に開けるんじゃないよ。ここにはね」
銃でドアのわきを二箇所撃った。
しかけられた攻撃システムがあらわになる。
ヒュウ。
ルーは短く口笛を吹き鳴らした。
「さ〜すが、おねーさん」
「まあね。もっと褒めな」
あたしはドアをおもいっきり足で蹴飛ばした。
金属の重たいドアが向こう側に倒れ、中が丸見えになった。
「!」
言葉を失った。
無数の檻。
強化ガラスのようなものでできたその檻は墓標にも似て、広い室内のどこまでも広がっている。
そしてその中には…………。
無数の奇怪な生物が…………。
「ヒト……?」
見まわすと、入口の壁にフックがあり、そこに薄いディスプレイがぶらさがっていた。
手に取ると自動的に画面が明るくなった。ファイルが表示される。
カタログ?
醜悪な!
しかし、あたしのアシは引き寄せられるように、ふらふらと奥へと向かった。
いつ、ルーたちとはぐれたのか、覚えていない。
カタログには、火星独立戦争の際に作られた人体実験場だと記してあった。
奥へ進めば進むほど、実験体は奇異なものへと変化していく。
気づいていた。目を覆いたくなるようなこの醜悪な光景に、実は魅入られてしまっているあたし自身に。
誘われるように、檻の周りをめぐる。
足が五本もあるヒト、妙に右半身だけが肥大しているヒト、目が五つもあるヒト、腕から触手のようなものが生えているヒト、首から下が豹のヒト……、それらがガラスの檻からじっとあたしの方を見ている。
あたしも、見つめ返す。
水槽の中で生きているヒト、巨大な首と猫ほどの大きさの体を持つヒト……。
そして。
あたしの足が止まった。
息が、そして、時が止まった。
黒髪の短い巻き毛。ダークブラウンの、切れ長の目。短い鼻。
背丈は人並み。やや痩せ型。
彼は、あたしを見つめていた。
そして、そのふくよかな唇を開いた。
「青き星を後にして。
我は来ぬ。
赤き砂漠のこなたに」
その、低い声。やわらかい、響き。
誘われるように、あたしも唱えた。
「君よ
ともに行かん。
風は誘いぬ。
遠き山のあなたに。
水もなく、
糧もなく、
我が胸にただ一輪の赤き薔薇あるのみ」
彼はまた繰り返した。
「青き星を後にして。
我は来ぬ。
赤き砂漠のこなたに……」
文才はないけど、気持ちだから。
そう言ってあの人は、照れながらこの詩を贈ってくれたのだ。
「君よ
ともに行かん。
風は誘いぬ。
遠き山のあなたに……」
火星においで。
あの人はただそれだけを、この詩にこめたのだ。
「水もなく、
糧もなく、
我が胸にただ一輪の赤き薔薇あるのみ」
『ローズ、一緒にこの星に住もう。一緒に土を耕して、この星のジョニー・アップルシードになろう』
そして、あの日、あの人は捕らえられ、拷問の末に死んでしまったのだ。
あの人はただの農業青年だったのに、殉死とみなされ、英雄の一人として名を連ねたのだ。
あの人の、ボロボロの屍。
ムゴいムゴい屍。
火星の大地、記念碑という名の墓の下に眠る、あの屍。
忘れた時はないのに。
目の前に、あの人が、いる。
生きて、動いて、あの人が、いる。
この目も、この髪も、この声も、この指も、あの人だ。
紛れもない、あの人だ。
「……フ。レイ…フ……」
その黒髪の人は、あたしをじっと見た。
「地球の搾取からこの星を取り戻し、豊かな大地となすのだ。
人はパンのみに生くるにあらず。ただ、胸に赤き薔薇を抱くのみ」
ちがう……。
赤き薔薇は、決して火星の独立の志なんかじゃない。
あれは、あれはあたしの……。
「……姐さん……。姐さん」
誰かに肩を揺さぶられた。
心配そうなブルーグレイの眼。
JD?
「姐さん、どうしたんですか?」
変声期の終わらない声。
鮮やかなメタリックブルーの髪。
背の伸びきらない、過去より未来の方が多い少年。
……あたしは……、あたしはなにやってんだろう……?
セピア色の過去の人間なのに、こんな鮮やかな未来に生きているなんて。
「姐さん!」
「あ、ああ、どうしたの?」
「どうしたのはこっちのセリフですよ! しっかりしてください!
いくら姐さんが惚れっぽくたって、どっかの誰かのコピーの前でタダの女みたいな顔してほうけてないでください!」
「そ、そうね……」
「風は誘いぬ。
遠き山のあなたに……」
低い、声。
壊れたレコードのように何度も何度も繰り返す。
JDがあたしの手からディスプレイをとった。
「ただのコピーですよ、やっぱり。
人間から採取した細胞から、人為的に脳に障害をもたせた、傀儡として使えるクローンを作る実験の失敗作だそうです」
! ! ! ! ! !
「……じゃあ、この細胞は……、この細胞は…本物……。本物の…本物の…レイフ……」
「姐さん!!」
JDは激しく揺さぶった。
よろけて、あたしはドスンと尻持ちをついた。
「我が胸にただ一輪の赤き薔薇あるのみ……」
「レイフ! レイフ! レイフ! レイフっ!!!」
涙がどっとあふれた。
忘れたことなど一度だってない。
火星にとって二〇〇年前でも、あたしにとってはたった四年前のこと。
と、メタリックブルーがあたしの前に立ちはだかった。
「姐さん、失礼」
鮮やかな光が閃いた。
ガラスの檻に空く穴。
ほとばしるレーザーが切り裂く人肉、そして鮮やかな血の……色!
「ウォ〜〜〜〜ッ!」
なにか吠えるような声が響き渡った。
それが、あたし自身の声だとは、長いこと気づかなかった。
JDがギュッとあたしを抱きしめていた。
内臓から絞り出すようなその慟哭(どうこく)が出尽くされるまで、なにも言わず抱きしめていた。つづく
![]()