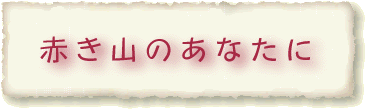
2002.3.20
「ずいぶんと、ここも荒廃してしまったものね」
火星ドームの出口に向かって車を走らせながら、あたしはつぶやいた。
「浸ってないで、なんとかしてよ!」
ルーが車の窓から応戦しながら言った。
「いやあ、少しは感じが出るかなと思ってさ」
てへへ、とあたしが笑うと、
「そんな暇あったら、わたしの身にもなってよ!」
ルーが怒鳴った。
ヤツら、人の多い場所では手が出せないらしい。
まあ、火星政府がからんだ、ヤバそうな話である。あまり公の場は好まんだろう。
しかし、一般大衆の目のないところとなると、容赦はしない。
宇宙港は治外法権だから問題なかったし、街に出てレンタカーを借りるまでは順調にいった。
が、最初の難関は、ここ、ドームの出入口に設置された検問所である。
ヤツらいきなり銃で撃ってくるから、検問を車で強行突破したのだ。
「ルー、追っ手の方はもういいから、宇宙服着て」
「え、なんで?」
「もうすぐ出口だからよ! 死にたいのっ?」
「げっ。わかった!」
ルーが頭を引っ込めるなり、銃声が減った。
ムダな弾は使いたくないのだろう。
なにせ、向こうの狙いは、生きたままアリアドネをとらえること。
効率よくあたしたちを抹殺したいんであって、やみくもに撃ってもラチがあかない。
早く決着をつけたいのはヤマヤマだが、まだ先は長く、持久戦なら彼らの方に分があるのだ。
「おねーさんは? ヘルメットかぶんないの?」
「かぶったら、判断力が鈍んのよ!」
宇宙服(スーツ)の本体はすでに着込んでいる。あとはメットだけだ。
ルームミラーにアリアドネの不安そうな顔が一瞬映るが、激しいハンドルさばきのため、たちまち視野から消える。
「行くよ! 気張んな!」
言ってあたしはアクセルを思いっきり踏みこんだ。
どぉ〜〜〜〜んっ!
轟音と激しいショックと共に、車はポォ〜ンと火星の裸の大地に踊り出た。
「ぐえっ!」
聞こえるうめきは、ルーのものか、アリアドネのものか。
いくら外地仕様のクッションばっちしの車だからって、数メートルすとーんと落ちれば相当のショックである。
火星の荒野をそのまま走り出すと、ほどなく、
「おねーさん、酔った……」
情けないルーの声。
「しゃあないわね。メットん中にチューブがあるから、そこに吐きな!」
「ううう………」
ルームミラーに目をやると、アリアドネが心配そうな表情で背をさすっている。
シロウトのアリアドネが酔わずにルーが酔ったからといって、情けないぞそれでもプロかなどと思わないでもらいたい。
アリアドネには前もって、酔い止めの強力なヤツを一発飲ませておいたのである。
あたしとルーは判断力が鈍るとマズいので、飲めなかったのだ。
緊張している時はいいが、ひとたびその糸が切れるとこんなもんだ。
あたしだって運転してる身じゃなきゃ酔ったかもしんない。
ゲーゲーいうルーを尻目に、ひたすら走り続けてほどなく、火星の大山脈が見えてきた。
デキすぎたシチュエーションというなかれ。
あたしたちのいた第四キャナルシティは、かつて火星の鉱山の発掘で栄えた古い街で、現在ではこの山脈の観光収入で食っているのである。
だからあたしは登山のために、ルーは観光と抱き合わせの娯楽施設で楽しむために、ここへ来たのである。
この山脈を目あてに来たアリアドネと出逢ったのは、単なる偶然だけの産物ではない。
巨大な、赤い山脈。
あたしは車を走らせながら思った。
長い時間風にさらされ、深く険しさを増した雄大な山と谷。
こいつから見れば、あたしなんて蚊や蝿程度のものなんじゃないか?
――それとも、巨牛の背中のノミ一匹。
昨日登山中に、そんなことを考えたりもした。
もろい岩盤、豊富だった鉱物。
雄々しい岩壁のすぐ裏は、哀れな醜い採掘場跡だった。
人は使えると思ったら、どうとでも使う。
そして、しまいには食いつぶすのだ。
そう。
地球のように。
山脈は険しく、外地仕様車でも通れぬ場所へ、ほどなく出た。
「ルー、ここに残ってるかい?」
車を停め、吐き続けですっかり青ざめているルーに問う。
「……おねーさん、わたしが一人でいられないの、知ってるでしょ」
「じゃ、山に登るよ」
ザックを背負い、ザイルを肩にかける。
「……岩に登るの?」
うんざりしたようなルー。
「必要があればね。まあ、シロウト相手に、できるだけムチャはしたくないけど」
「おねーさん、一人で荷物持ってくの?」
ルーもアリアドネも空荷である。
「あんたたちに持たせちゃ、すぐくたばるでしょ。あたしが持ってった方がマシじゃん。行くよ」
あたしが歩きだすと、二人は後をついてきた。
険しい山道で、足元の不安定なザレ場である。
「きゃっ」
かわいらしい声をあげて、アリアドネが地に両手をつく。
砂に足をとられ、バランスを崩したのだ。
砂が下へ下へと流れていく。
「ほら、つかまんな」
やっとのようすで登っているルーを横目で見ながら、あたしはアリアドネに手を差し出した。
アリアドネはあたしの手につかまり、腰を上げかけて、さらに砂に足をとられた。
「あっ」
グッ。と、力をこめて、彼女の手を引き寄せる。
「土踏まずにギュッと力入れな。踵(かかと)に力入れると、砂に流されるよ」
「は、はいっ」
ゆっくりと立ち上がる。
「そしたら、そのまま上がってくる。土踏まずを中心に、足全体に力を入れるようにして歩くんだよ。足先とか一部に力入れると落ちるからね」
「はい」
口で言ったところで、こんなお姫さまがすんなり歩けるわけもない。
ただ、さっきよりはいくらかマシになったようだ。
彼女の腕を引きながら、山道を登り続けた。
二人は早くもゼイゼイ言っている。
無事に連れていけるんだろうか?
いくら火星の重力が小さいからって、荷物の上に二人を重ねて背負っていくわけにはいかない。
チッ。
JDを連れて来るんだった。
そしたら、二人を背負わせてやるんだが。
――姐さん〜。またムチャ言わないでくださいよぉ〜。
くすっ。
JDの情けない声が思い浮かんで、おもわず笑った。
いいんだ、JDだから。
「どうしたの?」
通信機から聞こえるルーの声に我に返る。
「なに笑ってんの?」
「なんでもないよ。ちょっと、思い出し笑いさ」
「余裕あって、いいよね〜」
うらめしげな声。
「わかったよ。もう少し歩いたら休もう」
アリアドネの激しい息づかいが、通信機ごしに聞こえる。
急なザレ場を、彼女を引き上げながら、しばらく歩いた。
休憩を入れると、ルーもアリアドネも、その場に倒れこんだ。
「だ〜らないわねえ〜」
あたしがせせら笑うと、
「わ、わたしはっ、おっねーさん、みた…いにっ、に…くたいっ派じゃ、ない…のっ」
「ほほう。まだ憎まれ口を叩く?」
山にくればこっちのもんだ。
砂の感触を確かに足に感じ、赤い砂の巻き上げられた赤い空を見上げる。
どこまでも吹き上げられる砂。
唇から詩がもれる。
「青き星を後にして。
我は来ぬ。
赤き砂漠のこなたに。
君よ
ともに行かん
風は誘いぬ。
遠き山のあなたに……」
「火星の、国歌、ですね?」
アリアドネが言った。
まだ息が切れている。
「なかなか教養あんじゃない」
あたしはピュッと短く口笛を吹いた。
「これでも、私、世界史、得意、なんですよ」
息を切らしながら、メットの中で得意そうに笑う。
「学校のサブテキストに載ってました。確か……、火星の独立戦争の初期に詠まれた詩ですよね。独立の気運が高まる中の民衆の心情を表現するものだって解説してありました」
「ふうん……」
あたしは遠くまで連なる赤き山の峰々を目でたどった。
遠き山のあなたに。
――戻ってきたよ。
心の中でつぶやいた。
「水を飲んだら行くよ」
「えーっ。おねーさん、もっと休もうよぉ」
「はん! だーらない。体を鍛えるいい機会だと思いな」
「……鍛えるんなら、エアロビクスの方がいいもん……」
ルーはメットの中でふくれっつらを作った。
その夜は砂漠で過ごした。
巻きあげられた砂でかすんだ空に二つの月がぼんやりと浮かんでいる。
フォボスとディモス。
火星の二つの月。
その両方に巨大な軍事基地がある。
「おねえさま」
疲れて眠っていたはずのアリアドネが、いつのまにか目を覚ましていたらしい。
宇宙服(スーツ)のまま砂上にゴロ寝だ。
寝苦しいのもしかたがない。
「おねえさまは、お強いんですね」
「あんたに比べりゃ誰だってそうだろうよ」
「ルーさんはおねえさまの本当の妹さんなんですか?」
「なんで?」
「だって、雰囲気も顔もあまり似ていませんもの」
「どっちだって、あんたにゃ関係ないだろ」
「それはそうですが……」
アリアドネはいったん言いよどんだ。
「……DJさんは弟さんなんですか?」
「DJじゃなくて、JD。あんた、なにを気にしてんの?」
横たわったままのアリアドネを、あたしは立ったまま見下ろした。
「きょうだいって、普通、どんな感じかと思って……」
「普通もなにも、いろいろなんじゃない?
……あんた、きょうだいいないの?」
「います。でも、おねえさまたちのように仲良くはありません」
「そーゆーうちもあるけどね」
「血筋……なんでしょうか……?」
ぷっ。
あたしは吹き出した。
「吠えない犬種とか小さい猫の血統とか、そーゆー話をしてんのかい、あんたは」
「そっ、そんな! 茶化さないでください!」
「くだんないこと考えてないで、さっさと寝な。明日もしんどいよ」
「私、おねえさまたちがうらやましいです。強くて、仲良しで……」
「寝なって言ったのが聞こえなかったのかい?」
アリアドネは沈黙した。
――うらやましいのはどっちだ。
あたしは思った。
――平和にぬくぬくと暮らしていけるお嬢さんが。
月は、いつまでも沈まなかった。
朝が来て、メットの中にチューブを出し、そこから流動食を摂ると、また歩き始める。
「おねーさん、このペースで、あとどのくらい歩くの?」
ルーが早くもぜいぜい言っている。
「あたしの足なら数十分。あんたの足なら、永久につかないわね」
「おねーさん! 冗談はやめて! わたし、筋肉痛で足が痛いんだよ!」
「翌日に筋肉痛が出るのは若さの証拠! 歩け歩け!」
夕方、日が傾きかけるころ、ようやく目的地が見えた。
「……おねーさん、なんか、人がいっぱいいるね……」
「……………」
「おねーさんてば!」
う〜〜〜む。
こりは………。
想像してなかったのだ。
ここが武装されてるとは。
一見、なにもなさそうな場所に、明らかに軍服とわかる宇宙服をまとった多数の人々の群れ。
ヤバヤバ〜〜〜。
もちっとマシな武器持ってくればよかったよな〜。
「ん〜、あのさあ……」
岩陰に身を潜めながら、あたしはアリアドネを見た。
「あんた、よく一人で来ようと思ったね」
こんなお嬢一人にボディーガードの二人もつけりゃ来られるところと踏んだから、軽い気持ちでつきあってきたのだ。
そりゃ、ボディーガードくん、しょっぱなに殺(や)られてるけどさ。
ありゃ単に、このお嬢んとこのシークレット・サービスの質が低いんだと見くびっていたのだ。
「そんなにたいへんなんですか?」
アリアドネが小首を傾げる。
「ま、ね〜。なんてったって、こっからまず地雷源突破して、ヤツらのレーザー銃とレーザー砲をかわすだろ、その向こうにもたぶんなんかあんだろうなあ……」
「そんなにたいへんなんですか?」
「装備がありゃあね、たいしたこたないけど、手持ちのもんじゃムリだね。出直すか」
「……おねーさん、また車のとこまで戻るの?」
うんざりした声でルーが言う。
「じゃ、今の装備であいつらに勝てると思ってんの?」
「それをなんとかするのがおねーさんの仕事でしょ!」
「役立たず二人をどう使えっての」
「おねーさん!」
「あの……」
おずおずとアリアドネが言った。
「仲間割れしている場合じゃないのでは………?」
「カーーーーーーッ! こーなったのもあんたのせいじゃないのっ!
あんたのオヤジさんってば、こーゆーとこに、ボディーガード二人ぽっちで行けって言ったの!?」
「あ、いえ…。人を頼むようにと……」
「じゃ、なんで頼まないのっ!」
「あ、あの、知らない人たちより、せっかくおねえさまたちが行ってくださるんですから、そっちの方がいいかな……なんて……。うふふっ♪」
「うふふっ♪じゃな〜〜〜いっ! そーやって金を節約しようって魂胆かいっ! あんたはっ!」
「そ、そんな……」
アリアドネが泣きそうになる。
「節約だなんて……。おねえさまには後でお仕事代、お支払いしようと思ってたんですぅ。
だって、見も知らない人に頼むよりいいじゃないですかぁ……」
ぶちぶちぶち。
「……私だって、そんなにたいへんなことと思わなかったし…。
おねえさまたちだって、私が頼む前に、行くって言ってくださったんじゃないですか……」
いかん。
グチグチモードに入ってる。
「……で? 頼れって言われた相手って?」
あわてて話題を変える。
「シークレット・サービスの人に情報屋さんに連れて行ってもらって、連絡をとれって。
確か相手は、セブンス・ヘヴンとか、ブラッディ・アレスとか、シスターズ・エルファーレンとか……」
「ぶっ!!」
あたしとルーが同時にハモった。
「そっ、それを先に言え〜〜〜っ!」
「え? え? どうかしました?」
アリアドネはおっかなびっくりに、ルーとあたしの顔を交互に見た。
「それって、かなりヤバい稼業のヤツらの名前ばっかしじゃん!
それに! エルファーレンはあたしたちのことよ!!」
そう!
ここいらでは、ちょっぴし有名なのである。
エルファーレン姉妹とそのおまけ。
美しいウルトラマリーンの愛機セイレーン号を駆り、豹のようにしなやかに、どんな剣呑な仕事でもさらりとこなす美しき姉妹と、おまけのガキんちょぼうず。
と言えば、あたしたちのこと以外にないっ!!
だから!!
それならそーと始めっから言ってくれりゃよかったのだ。
いくらオフとは言え、大富豪のお嬢がお客とあっちゃ、そこは商売だ、引き受けないこともない。
なにより!
仕事の危険度がかなり高いかも、と最初から重装備かつ計画的に臨んだぞ!?
「しゃあーない。料金上乗せで許してやるか」
あたしがつぶやくと、
「えーーっ? やっぱやるのぉ〜!?」
イヤそーなルーの声。
「そりゃ、やるっしょ。指名されといてできないとあっちゃ、エルファーレン姉妹の名折れだかんね」
「じゃあ、どーすんのよ、具体的には」
「んーーーーーー」
あたしは腕組みをした。
「んーーーーーー。そーだ」
人差し指を立てる。
「なに?」
勢いこむルー。
「待つ」
にっこり。
コケッ。
ルーがコケたようだが、気にしない、気にしない。
「ま、待つぅ〜?」
「そっ。待つのみ。果報は寝て待てってね」
「そんな悠長な!! 酸素だって食料だってそんなにないんだよ!!」
「だぁ〜いじょうぶ、だいじょうぶ。
『遠き山のあなたに。
水もなく、
糧もなく、
我が胸にただ一輪の赤き薔薇あるのみ。』
ってね!」
「あ、あの国歌の続きですね」
アリアドネが顔を輝かせた。
「そ」
あたしは意味ありげにウィンクして見せた。つづく
![]()