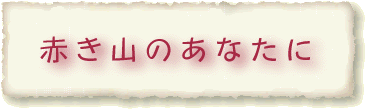
2002.3.13
「あーあ、すっかり汚れちゃったわね」
風呂あがりに牛乳を一杯飲みながら、ルーがうらめしそうに言った。
もちろん、手は腰。
天を仰いでぐぐぐっと一息。
基本である。
クローゼットからは、ほこりで真っ黒になったピンクの丈の短いドレスがのぞいている。
「しゃあないでしょ。抜け出せただけでもめっけもんよ」
あたしは自慢の長いストレートの髪をていねいにタオルドライしながら言った。
時折、日にすけて金色に輝くこともある、淡い赤みがかった髪は、あたしの自慢だった。
「すみません……」
ひたすら恐縮こいてるアリアドネ。
黄色のふわふわドレスから、ホテルに備えつけのガウンに着替えている。
ふわふわ金髪がキラキラ輝き、どんな恰好をしても、お嬢さま然としている。
たぶん、筋金入りのお嬢さんなんだろう。
「クリーニングで落ちるかな……」
つぶやくルー。
あたしはアリアドネを見た。
彼女は、すがるような目であたしを見つめていた。
……弱いんだよなあ、こういう目。
捨てられた子猫みたいな目。
――いかん、いかん。
情に流されると、子どもの頃秘密基地作って捨て猫飼って増えすぎて近所から総スカン食った時と同じになるぞ。
あの時はマジで、一家夜逃げの寸前まで行ったからな……。
ンンーッ。
咳払いをひとつ。
ここは威厳を……。
「なんでもいいけどさあ、あのお兄さんたち、あんたのなんだったの?」
「その……、シークレット・サービスさんたちで……」
「シークレット・サービスぅ〜?」
ちょっと待て。
なんなんだ、この展開は。
いきなりアヤしくなったぞ?
「なんでシークレット・サービスなんかがあんたの周りうろついてたの?」
「その……。そういうものだと思ってましたが。違うんですか?」
ピュッ。
ルーが短く口笛を吹き鳴らした。
アリアドネとかいうこの女の子、たいしたお姫さんかもしれないぞ。
「一人で帰るのも危なそうだね。家まで送ったげようか?」
と、あたし。
家まで送り届けただけで礼金が出るかもしんない。
相手が金持ちなら構うことはない。もらえるだけもらっちゃえ。
「それは……、ちょっと……」
「どしたの?」
「事情があって、その……」
「家出でもしたの? どういう事情だかしんないけど、命あってのものダネだよ。おとなしく帰んな」
「いえ、あの……、家、遠いんです……」
遠い?
って……。
「あんた、もしかして、火星の外から来たの?」
「はい……」
「じゃ、火星外務局の保護センターにでも連れてってあげるよ」
「それもちょっと……」
「なんなの、いったい! はっきりしないね!」
「すみません……」
うつむくアリアドネ。
うーっ。
これじゃまるで、あたしが苛めてるみたいじゃないか。
「悪いけどさ、あたしたちも暇じゃないの。かと言ってさ、あんたを一人にしとくのも不安だし。いいとこのお嬢さんなんでしょ? とっとと帰んな」
ボロッ。
アリアドネの目から大粒のダイヤモンドが……。
まいったな。
……泣かしとくか。
あたしは椅子から立ち上がり、シャワー室へと向かった。
まだほこりだらけなのだ。さっさとシャワーを浴びて着替えたい。
「おねーさん、この人、泣いてるんだよ?」
ルーがとがめる。
「泣かしとけば。あたしはさっさと風呂入りたいの」
「おねーさん!」
ルーは心やさしすぎる。
そのおかげで、今までどれだけ貧乏クジひかされたかわかりゃしない。
まったく懲りない御仁だ。
肩をすくめて、あたしはシャワー室へ入った。
翌日、アリアドネを連れて、火星外務局の保護センターへ行った。
昔、火星移民局と呼ばれていたところだ。
が、現状にそぐわないとして、名称も新たにリニューアルしたらしい。
火星の植民地時代は長い。
地球の各国家間の熾烈(しれつ)な覇権争いが、この赤い惑星上で延々と繰り返されてきたのだ。
その間に、月の独立戦争が勃発した。
地球は勝利したものの疲弊し、火星は軍需産業で潤った。
そして、今度は火星が独立を求めて蜂起したのだ。
戦争は約一〇〇年の長きにわたり、地球は地表のほとんどを焼き尽くされて惨敗した。
地下や地表のドーム都市に住む者はいるものの、行き場を失った大多数の地球人たちは、皮肉にも敵国の火星に引き取られることとなった。
それが、今から一〇〇年前の話である。
そういうわけで、保護センターは元々火星外からの難民を受け入れる窓口だった。
現在では、ただの迷子センターみたいなもので、アリアドネをつき出せば、一時的に預かって、無事おうちに帰れるよう手配してくれるだろう。
「ほらほら、ぼやぼやしない。シャカシャカ歩くっ!」
気のりのしないアリアドネの背中を強く押すと、
「シャカシャカって……。おねーさん、ゴキブリじゃないんだから」
と、ルー。
「言うなっ!」
火星にも、ゴキブリはいる。
ヤツらの繁殖力は絶大なのだ。
ヤツらを絶滅させてくれるというんなら、あたしは虎の子のへそくりを全部出したってかまわない。
だが、この世にヤツらを殲滅させる手段など、ありはしないのだ……。
「おねえさまもゴキちゃん、嫌いなんですか?」
アリアドネが顔をパッと輝かせる。
「あの歯ごたえ、ガシャガシャして悪いですよね。足のところで、くちびる時々切っちゃうし。
ああ、よかった。私だけが好き嫌いしてるんじゃなくって」
…………。
なんだか、ものすごいことを聞いてしまったような……。
いや、なにも聞かなかったことにしょう。
歯ごたえなんて、歯ごたえなんて、歯ごたえなんて…………!
うっぎゃあ〜〜〜っっっ!
ざあーっと鳥肌が立つ。
「茶色のはまだ小さくて食べやすいですけど、黒いのは大きくて困りますよね。時々飛んできて顔に当たるんですよね……」
「まだ言うかぁっっっ! この口は〜〜〜っっっ!」
おもいっきりアリアドネの口に指をつっこんで舌を引っぱる。
「ほ、ほえ〜はは、ひゃ、ひゃへれくらはい〜。へろは、ふへはいまふ」
おねえさま、やめてください。ベロが抜けちゃいます。とか言ってるようだが、聞いてやんない。
「二度と言うな、ヤツの話は二度とするな。今度したら、舌を引っこ抜いてやる!」
引きずるようにして、保護センターの門をくぐる。
そこで、あたしはようやく彼女を解放してやった。
ここらで警備員が来て、身元確認をするはずだからだ。
果たして、門のわきの詰め所から、二人の人影。
ざわっ。
――殺気!
頭より体が反応した。
アリアドネを押し倒す。
一条の光が頭上を過ぎ去った。
ジュッと後ろにあった樹木の幹を焼いて貫通する。
直径一〇センチはあろうかという穴が残る。
あたしはアリアドネを抱きしめたまま、地面を転がる。
門の柱の影にたどり着くと、ルーが中に向かって光玉を投げこんだ。
「走るよ」
まばゆい閃光が辺りを包む。
そちらを見ないようにして、あたしたちは走り出した。
光玉はその名の通り、放ると閃光を放つ、目くらましの玉だ。
爆発力はたいして大きくない。人間に直撃しても、軽く火傷するぐらいだ。
だが。
「あいつら、レーザー使いやがった」
あたしがつぶやくと、
「タダ者じゃないね」
ルーがうなずいた。
低出力のものは別だが、あれほどの出力のものは、火星のドームを傷つける恐れがあるとして持ち込み禁止のはずだ。
ここ、火星の大気は薄い。
そのため、人類はドームを造り、その中に空気を満たして都市を築いたのだ。
そのドームを傷つけることは、すなわち中の空気を失うこと。人々を死へ誘(いざな)う行為となる。
自然、火星ではそうした武器の取り締まりが厳しい。
だが、どこにでも、そうした網の目をくぐりぬける輩がいる。
あたしたちは、そのとんでもない連中にぶちあたったらしい。
「あいつら、追って来ないね」
と、ルー。
「表沙汰にしたくないんでしょうよ」
あたしはアリアドネの腕をぐいと引き寄せた。
「あんたかい? 原因は。昨日のことといい、今日のことといい」
間近い距離でにらみつけりゃ、少しは吐くかとおもいきや……。
ポッ。
頬を赤らめ、うるんだ瞳。
「おねえさまって、腕が細いのに力強いんですね……」
パコォォーン。
「あいたたたたた……」
アリアドネが頭を押さえている。
「おねーさん、なにも殴らなくても……」
「これが殴らいでか! 人が命張って守ってやってんのに、なんにも話せません、挙げ句にポッ。だあっ? ざけんじゃないよ!」
「……すみません……」
消え入るようなアリアドネのかわいらしい声。
泣きそうに震える細い肩。
潤んだ薄いブルーの瞳。
可憐な美少女、イジワル姐(ねえ)さんにイジメられる之図。
「あ〜、もう!
しけたツラしてんじゃないの。さっさと行くよ!」
「行くってどこへ?」
と、ルー。
「もちろんあたしたちの宇宙船(おふね)へよ」
センターがグルってことは、どこまで手が回ってるかわからない。
一つ出直してくるか。
あたしはルーに向かってウィンクした。
宇宙船(ふね)に戻ると、我が家に帰ったような心地よさを覚えた。
「ん〜。やっぱり宇宙船(うち)はいいねえ」
船室(キャビン)に入ると、冷蔵庫を開ける。
「運動するとおなかすくよね〜」
「おね〜さん、つまみ食いばっかりしてると太るよ」
ルーが白い目で見る。
「腹が減っては戦はできぬ〜」
もぐもぐとハンバーガーを食べる。
アリアドネはソファに腰をかけてうつむいている。
くちびるをキュッと引き結び、こぶしをギュッと握りしめている。
「アリアドネ、なんか飲む?」
「……私……!」
顔をあげた彼女の、なにか決意したような表情。
「とりあえず話はきくけど、飲み物ぐらいはいるっしょ?」
あたしが軽い口調で言うと、
「あ、はい」
彼女の肩の力がいくぶん抜けたような気がした。
よしよし。
「コーヒーでいい?」
「私、紅茶の方が……」
「紅茶ね。砂糖とミルクいる?」
「砂糖はいりませんが、ミルクはデボンジャー産のジャージー種のにしてください。それから、紅茶はロハッズのナンバー一七か、フォイトメムナーソンのブレックファストか、ログウッドのスペシャル・ロイヤルミルクティー・アタック! がいいです」
「…………」
あるか、ンなもん!
叫びそうになるのをこらえる。
紅茶といえば、リットーかニプトンかボルックブンドのいっちゃん安いティーバッグに決まってる。
黙ってリットー紅茶を淹れ、クリーミーパウダーを注ぎこむ。
手渡すと、アリアドネは、くん。と匂いを嗅いで妙な顔をした。
くっと一口含むと、なんともいえない顔をした。
「……腐ってるんですか?」
上目使いに見る。
「腐ってなんかいないよ!」
「でも、渋いし、エグいし、ミルクはしつこいし、ノドにからむし、紅茶本来の甘みがないし……」
「黙って飲みな」
アリアドネはもてあますように紅茶のカップを膝に載せた。
「さて、どこから話してもらおうか……」
あたしがハンバーガーをかじりながら言いかけると。
不意に船室(キャビン)のドアが開いた。
「ああ、姐さん」
まだ変声期の終わっていない少年の声。
淡いメタリックブルーの、一目で染めたとわかる髪。
淡い淡いブルーグレイの鋭い眼。
甘いマスクの美少年。
「なんだ、JD(ジェイディー)か。あんた乗ってたの」
「火星(ここ)は厭な知り合いが多くて。どうしたんです? その人」
JDはひょんなことから拾った宇宙船(うち)の居候である。
その顛末は機会があったら話すとして、現在宇宙船(うち)のメカニックを担当している。
やっこさん、どういうわけかその手の知識や経験が豊富だったりするのだ。
「ん、ちょっとね」
「またまた厄介ごとですか?」
チラチラとアリアドネを見ながら、さっさとコーヒーを淹れる。
「あー、また黙って飲みましたね、オレのマンデリン」
「……知んないわよ」
「だって、一杯分、確かに減ってますよ! あーあ、コツコツ貯めた金で買ったのに……」
「ちまちましてんじゃないの! 細かい男は嫌われるわよ!」
「そんな問題じゃないですよ! 人のもの盗ったら、立派な犯罪ですよ!」
「ほほう。じゃ、あんたが居候してんのはどうなんのかな〜? 食事は? 空気は? ショバ代はどうなんのかなあ?」
「姐さんの方がよっぽど細かいじゃないですかっ!」
「あたしはいーの!」
ちょいちょい。
いきなり肩をつつかれた。
「……おねーさん……。だんだん話がズレてくんだけど……」
ふりむくと、疲れたようなルーの顔。
「あ……。あっはっはっはっ。そ〜ゆ〜こともあるかもしんない」
とりあえず、笑ってごまかす。
「それでさ、アリアドネ、事情聴きたいんだけど」
アリアドネは落ち着かなげにJDを見る。
「ま、こいつのことは、空気かなにかだと思って、無視してくれていいから」
あたしが手を振ると、
「……空気……」
JDがふくれたが、JDだから気にしないっ。
「あの……、私……」
アリアドネは相変わらずJDを見る。
まだ信用できないのか?
いや。この眼は……。
――嫌悪している?
「JD、席外して」
「え?」
「いいから、早く!」
「は、はいはいはい」
アリアドネはJDが確かに部屋の外へ出ていくのを見送って、それからため息をついた。
「あの子、苦手?」
「……だって……」
アリアドネは口の中でもごもご言う。
「なに? はっきりしゃべんなさい」
「……だって、あんなかっこで……」
「あんなかっこ……?」
別に、ヘンな恰好をしてきたわけではない。
いつものようにタンクトップに七分ズボンといういでたちだった。
「おねーさんの鈍感。タンクトップだからマズいんでしょ」
ルーがあきれ声で言う。
「ああ、なるほど。裸同然ってことね」
あたしは手を打った。
「いやぁ、この年になると、上半身ぐらい裸でもビクともしなくってね。若い子はいいなあ〜、じゅるるるるって眺めちゃうもんね。はっはっはっ」
「おねーさん……。そんなにあからさまに言わなくても……」
アリアドネが赤くなったり青くなったりしている。
この年頃は、肉体というものが恥ずかしかったり、不潔に思えたりするものなのかもねー。
まあ、からかうのはこのくらいにして、と。
「さて、もういいでしょ。聴かしてくんないかな、あんたの諸事情ってヤツをさ」
あたしはアリアドネに向き直った。
――実は――
と、アリアドネはとつとつとしゃべりはじめた。
彼女は、スペース・コロニーを複数所有する、ある富裕な家のご令嬢だという。
それまで住んでいた屋敷を改装することになり、長い間開かずの間だった部屋を開けたところ、中から古い古い手紙が出てきたというのだ。
むろん、手紙といっても、紙ではない。データディスクの束である。
そして、その中に興味深い事柄と、地図が入っていたという。
アリアドネは、ぜひそこへ足を運びたいと思った。
すると、両親は自分たちのスペース・コロニーのシークレット・サービスをつけて、彼女をこの火星に送ってよこしたのである。
「――火星の政府は信用するなと言われました」
アリアドネは初めはうつむきがちに、しまいにはあたしの目を強く見つめて話した。
「私が火星に入れば、政府ぐるみで私を誘拐して、身代金を要求するだろうって。とにかく、困ったことがあればシークレット・サービスの人たちがなんとかしてくれる、心配するなって」
「はぁ〜ん。ずいぶんおもいきったことする親だね。危険を承知で娘を送りこむなんざ」
「初めは大反対でした。でも、どうしても行きたかったんです。説得するのに、二年かかりました」
ひゅっ。
思わず口笛を吹く。
「そいつぁ、たいしたもんだ。で、どこへ行こうってんだったの?」
「オリンポス山なんですけど……。場所は地図に描いてあります」
「で、地図は?」
「ここに……」
アリアドネは胸を叩いた。
?
どういうこと?
あたしがいぶかしげな顔をすると、ルーが笑った。
「おねーさん、旅行の基本よ。おなかに旅行用のウェストポーチ巻いてるのよ。薄くて、ポケットのついてるヤツ」
「へえ〜。そんなもんあるんだ?」
「基本中の基本よ」
「じゃ、それ見せてもらおうか。出して」
アリアドネは明らかに戸惑い、ためらった。
「えっと……、あの……」
「なによ。連れてったげようというのよ。さっさと出しなさい」
「えっと……」
アリアドネは真っ赤になった。
「おねーさん」
またしても、助け船を出したのはルーだった。
「それって、一度服脱ぐっていうか、スカート緩めて、ブラウスもボタンも外さないととれないのよ」
「ん? 別に問題ないじゃん。女同士なんだから」
「おねーさん! おねーさんには、青春ってものがなかったの!?」
「ルー、なに怒ってんの?」
「おねーさんみたいなフツーと違う人にはわかんないんだよ! この年頃はいくら女の人の前だって恥ずかしいんだよ! ほら、外に出て!」
ルーはひどい剣幕であたしを船室(キャビン)の外に押し出した。
廊下に出ると、後ろでドアが閉まる。
一応断っておくが、あたしだって、遠い昔の思春期には人一倍恥ずかしがり屋だったのである。それを、長年の放浪生活で、すっかり忘れてしまっただけなのである。
そのことをルーに話そうと思ったが、こちらをにらみつけるような形相に、なんだか疲れてやめてしまった。
「……おねーさん、あの子、まさかオリンポス山に連れていくつもり?」
ルーがおもむろに訊いた。
「そうだよ〜ん」
あたしが簡単に答えると、いきなりそばまで詰め寄ってくる。
「あんなに危ない目に遭ったんだよ? せっかくのオフだっていうのに、なんでそんなことするの! お金のため? あの子がお金持ちの子だから?」
あたしは頭をカリカリ掻いた。
「いや……。だって、二年もかけて親説得してきたんだから、そのまま帰しちゃかわいそうでしょ」
「なんで今さら、そんないい人みたいなこと言うの!」
あたしは応えず歩きだした。
「どこ行くの?」
ルーがついてくる。
「もう、おねーさんったら、また山に登れると思ってんのね?」
それもあるが。
「火星名物はどうなるの?」
無論、食いたいさ。
「おねーさん!」
あたしは艦橋(ブリッジ)に入った。
「JD!」
サブパネルに向かっていたJDがふりむく。
「ああ、姐さん」
サブパネルに映っているのは、もっか着替え中のアリアドネ。
「どう? 按配(あんばい)は?」
「胸を手術して、ディスクを入れる場所を造ったみたいですよ。ここんとこ」
JDが、ポインタでサブパネルに映ったアリアドネの右胸を指し示す。
なるほど。胸の表面がふたになっており、そこが開いて、中にディスクが収納できるほどのすきまが見える。
「腹巻きに入れてたんじゃないんだ?」
「ええ。そっちはそっちでしてますけどね」
「ふうん。体に手を加えるっちゃあ、気合いが入ってるなあ」
あたしはJDの隣の座席に身を沈めると、コンソールに両足をあげた。
「で、やっこさんの身元はわかったの?」
「うちのデータには、近いものはありませんね」
JDが金色の髪を一本ひらひらさせた。
アリアドネの髪だ。
このDNAから身元を調べているのだが。
「裏のルートからデータもらってきます?」
「そうして」
「じゃあ、連絡取れ次第、外出しますけど」
「うん」
あたしは目をつぶった。
アリアドネ。
彼女の会いたがっているもの。
彼女をすべて信用したわけではないが、あの深窓のご令嬢が危険を冒してまでも会いたがったもの。
それに、あたしも会いたいと思ったのだ。
「彼女、着替えが終わりますよ」
JDが言った。
あたしは目を開いた。
甘いマスクの、でも肩やら腕やら筋肉質の男の子。
「あのさあ、JD」
席を立ちながらやさしくささやきかけた。
「はい?」
宇宙焼けした赤銅色の顔の、二つのブルーグレイの眼が、無警戒にこちらを見上げる。
「外出した時さあ、帰りに大タコ焼き買ってきて」
「火星名物、大タコ焼きですね?」
「そうよ〜ん。頼んだわよ」
くしゃくしゃっと彼のメタリックブルーの髪をかきまわす。
「うわ〜っ。せっかくセットしたのに、台なしじゃないですか」
「へっへっへ〜っ。もっとかきまわしちゃるっ」
「わ〜っ」
――ほんの、コミュニケーションである。
たとえ、JDが涙目になってたとしても。
艦橋(ブリッジ)を出ると、ルーが言った。
「あーあ。あの年で女の子の着替え見てもなんともないなんて。ぜ〜んぶおねーさんのせいだからね」
「いいじゃん。大タコ焼き食べられるんだし」
「そういう問題じゃないでしょ! それに、火星の夜景とか見に行きたいとこいっぱいあるのに……」
「はいはいはい」
あたしは船室(キャビン)に向かう足を速めた。つづく
![]()