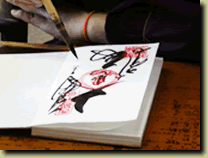
観音霊場といえば西国三十三所観音霊場が最も有名ですが、その歴史は古く奈良時代までさかのぼります。
伝えられている所では、養老2年(718年)大和長谷寺の徳道上人が病にかかり生死をさまよった時、夢の中で閻魔大王に会ったところ、「お前はまだ死ぬことを許さない。帰って三十三所の観音霊場があることを人々に知らせ、世の悩める人々を救いなさい。」といわれ、起請文と三十三の宝印を授けられました。しかし、当時の人々はこの話を信用せず、上人はやむなく授かった宝印を摂津中山寺の石棺に納めたといわれています。
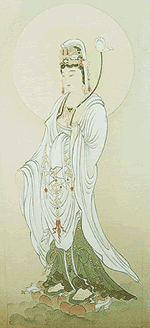
白衣観音
仏絵師 藤野正観氏作
約270年後、それまで途絶えていた観音巡礼を再興されたのは花山法王でした。
先帝円融天皇より帝位を譲られ第65代花山天皇となられますが、在位わずか二年で皇位を退き、寛和2年(986年)19歳の若さで法皇となられました。その後、出家した花山法皇が、書写山の性空上人と紀州熊野那智山に参籠し、三十三所観音霊場巡礼を発願されました。河内石川寺の仏眼上人、摂津中山寺の辨光上人を伴い巡礼、観音霊場を復興されました。
室町時代までの観音巡礼は僧侶の修行としての性格が強かったようですが、室町時代後期になると一般の民衆にも深く浸透するようになりました。
この頃には関東でも、坂東三十三所、秩父三十三所などの霊場が開かれています。その後、観音信仰は全国的な広がりを見せ、河内にも三十三所観音霊場が開かれました。