2007年の暮れ、フジテレビの朝の番組「とくダネ!」で丸の内合唱団と私が主宰する男声合唱プロジェクト YARO会が全国に紹介された。
YARO会が全国に紹介された。
丸の内合唱団は女声だけで第九を歌うという丸の内ビジネス街のイベント合唱団、いっぽうYARO会はその名のとおり男声合唱団の集まりである。番組のコンセプトは「いま合唱が熱い!」だった。
テレビで取り上げてもらえるのはとてもありがたいことである。ところで「いま合唱が熱い!」とはいうものの、果たして巷の合唱熱はどのくらいの温度になっているのだろうか。少々気になるところである。
埼玉県はたしかに他県より合唱熱が高いようには思うが、それでも中学・高校の活発な活動がそのまま大学→社会人へとスムーズにはつながっていないところが悩みである。埼玉県には短大も含めると40以上の大学があるのではないかと思うが、県連に加盟しているのはごく僅かである。さらに社会人合唱団では若い人がすくなく、とくに男性が不足していて、おまけに高齢化の波が押し寄せている。年代層で見れば20〜30代の中間層が抜けている。
大学グリークラブの衰退が叫ばれて久しい。しかし、好転の兆しはなかなか見えてこない。名門といわれる大学でも、高校時代から合唱を経験している人ばかりが入ってくるわけではない。入団希望者が減少しているうえに初心者も少なからずいる。それを一定のレベルに短期間で引き上げるのは容易なことではない。そして、一所懸命育てたとしても4、5年もすれば卒業してしまう。もっとも、在籍可能年数一杯まで何年も歌ってくれる人も中にはいるだろうが…。このような状況が長く続くと、定演がままならないどころか存続自体危ぶまれるところも出てくる。比較的学校の規模が大きく、歴史があるところは、OBの組織力やバックアップが期待できるが、それもままならない学校ではなすすべがない。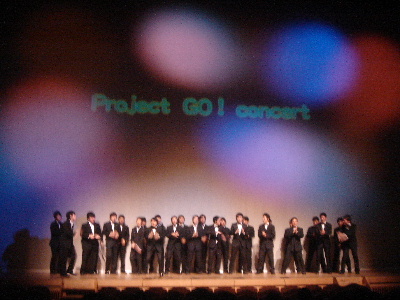
しかし、このような窮状に手を拱いてばかりでは何も解決しない、何か手はないかと立ち上がった学生たちがいた。
新しいスタイル、新しい可能性、新しい合唱を提案し「男声合唱を盛り上げよう」と、早稲田を中心とした、麗澤、お茶の水、外語大、学習院、学芸、武蔵工、東大、医科歯科などから有志が集まった。
名付けてProject
GO!(プロジェクト・ゴー:略してプロゴ)。G=Glee、O=Orchestra、男声合唱とオーケストラを融合させようというところからのネーミングである。
プロゴは、そもそも2003年5月に行われた東京六大学合唱連盟定期演奏会(東京六連)の合同演奏でポップスを演奏したことがきっかけとなって発足した。しかし、自由参加のため当初からさまざまな難問に直面し、開催が危ぶまれたときもあった。さらに人間関係や自分の所属する団との折り合いなど、よくある軋轢から去って行った人もいたという。しかし船出した以上、あと戻りはできない。そんな決意から、当時流行っていたNHKの「Project
X」をもじって命名し、成功に向けてお互いに鼓舞し合った。
このような状況──すなわち生みの苦しみとでもいうか、新しいことを立ち上げようとするには、それなりのエネルギーが必要なのである。このあたりは男声合唱プロジェクトYARO会の経緯とも一脈通じるところがある。思わぬ難局にぶつかったとき、そこはオトコ同志、オトナ同士、最後は目標達成に向け、些細なことにはお互い目をつぶったものである。おそらく学生たちも目標に向かって大同団結したことであろう。
そのプロゴも2回目のコンサートを迎えるまでになった。2006年3月15日、大田区民ホールアプリコ大ホールで行われたコンサートは、すべて編曲モノで構成されていた。プロゴは、基本的にポップス中心である。
毎回新たに編曲した曲を演奏するのが原則、つねに新しい曲をやるので演奏するほうもけっこうたいへんにちがいない。YARO会と異なるのは、すべてのステージが合同演奏で構成されている点である。したがって、練習もすべて合同でやらねばならないはずだが、自身の学校の活動との両立など、参加者の負担はけっこう大きかったことだろう。
1st. Stageは、“Let’s play Classicapella!”と題された22人によるア・カペラの男声合唱。バッハ「主よ人の望みの喜びよ」、モーツアルト「トルコ行進曲」、ベートーヴェン「第九 第四楽章」が演奏された。編曲は「Jolly Rogers Collection」の編曲集でもお馴染みの田中宏さん。どの曲もなかなか楽しいアレンジだったが、メンバーのすくなさはいかんともしがたく、声が聴こえにくい箇所もあり、全体として十分表現しきれなかったのではないかと惜しまれた。プログラムのメンバー紹介欄には27名が登録されていたが、全員がオンステすることはできなかったようである。

声が通りにくかったのは、緞帳が下りたステージの前で歌ったことも大いに関係していたと思う。ステージ上はすでに2nd. Stageのオケ用の椅子などがびっしりと並んでいて使えなかったためであろうが、とにかく合唱にとってはかなり厳しい条件である。緞帳の前だからそれだけ客席に近いとはいえ、うしろが反響板ではなく布の幕ではやはり声は飛びにくい。しかし、そんなハンデにもめげず、学生指揮者星雅貴さん(早稲田)の指揮のもと若々しく好感の持てる熱演であった。
2nd. Stageは、オーケストラだけの“Welcome to Disney Orchestland♪”。指揮は小久保大輔さん。
アラジンメドレー、カリブの海賊メドレーと、お馴染みの曲をさまざまな照明やスモークやらをふんだんに使っての演出でステージを盛り上げた。曲調に合せたカラフルなステージは、なかなか楽しめるものである。しかし、あれだけの照明をやるとかなり経費がかかるはずで、学生諸君のサイフの中身がつい心配になってしまった。
最後の合唱+オケ+バンドの合同演奏、3rd. Stage“Stay tuned☆Disco Hour”は、70年代のディスコナンバーをアレンジしたもので栗田信生さんの編曲であった。小野友樹さんのデイスクジョッキースタイルによる曲の紹介でステージが進められたが、このDJの声のよさには驚いた。なかなかのものである。
このステージではミラーボールなども効果的に使い、ダンスミュージックとしてビジュアル的にも面白かったし、聴衆の反応もよかった。けっこうな盛り上がりを見せたのだが、ひとつだけ問題を指摘するなら、肝心の歌が聴こえなかったことである。合唱団がオケの後ろに配置されていて、なおかつ照明効果を上げるために反響板がないから、ほとんど歌詞が聴こえて来ない。
オケとエレキバンドに対抗するには22人の合唱ではとうてい無理である。せめて人数が倍くらいか、あるいはポップスなのだからマイクを使っても良かったのではないだろうか。それでも、楽しい雰囲気は十分に出ていた。
最後に、コンサート全体を通しての感想をまとめてみよう。
いくつもの大学が集まって多くの困難を乗り越え、あそこまでまとめた努力は称賛に値する。ただ、客入りがいまひとつだったのは惜しまれるし、身の回りの合唱仲間でもプロゴの活動を知る人はすくない。世の男声合唱団を中心に広く声を掛けるなど、もっと広報活動が必要だったのではないか。まずは名前を知ってもらうのが先決である。
それにしても、本番に至るまでは平坦ではないイバラの道だったと想像するが、今後の合唱界やオーケストラ界に一石を投ずるものになることを期待したい。