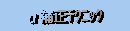 α補正テクニック
α補正テクニック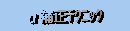 α補正テクニック
α補正テクニック

 α補正 for 初級ナビ編
α補正 for 初級ナビ編




 山口励さんのメールアドレスは下記の通りです。(山口さんも御多忙ですので、その辺を留意の上メールを差し上げて下さい。)
山口励さんのメールアドレスは下記の通りです。(山口さんも御多忙ですので、その辺を留意の上メールを差し上げて下さい。)


各自でデータを取ってがんばって下さい。。。というだけでは、練習走行禁止の昨今、難しいでしょうから私の秘蔵データを参考にして下さい。
各車とも標準的なラリー仕様ですが、E−38AはフロントデフがビスカスLSDです。また、補正率は合わせてあります。実走行は8km強と7km弱ですが10kmに換算してあります。AVEは50〜60km/h位です。また、m単位は四捨五入です。
駆動方式の差によるダートでの距離の出方(10km)
| 走り方 | 上り、下り | 4WD(E38A) | FF(AE92) | FR(A175) |
| グリップ | 上り | 0(基準) | +180m | +120m |
| 全開 | 上り | +110m | +850m | +530m |
| グリップ | 下り | −100m | −50m | −120m |
| 全開 | 下り | −140m | +200m | +160m |
| 走り方 | 上り、下り | 4WD(E38A) | FF(AE92) | FR(A175) |
| グリップ | 上り | 0(基準) | +130m | +50m |
| 全開 | 上り | −30m | +230m | +120m |
| グリップ | 下り | −50m | +50m | −30m |
| 全開 | 下り | −150m | +60m | +20m |

山口さんから問題の解答を頂きました。山口励 さんは書きました:
> 「α補正をどの様に各ナビゲーターが処理しているのか」という国内ナビゲーターの永 >遠の課>題について、全日本戦をベースに思いつくまま問題形式で書いてみます。 >但し、私の経験してきた時代と現在のラリー運営方法(CP間の距離規制、コマ図への距 >離記入及び競技車両(私が使用したのはファミリア4駆までです。一部ランサーも含まれ >ますが)の違いにより、現在ではかなりずれたものになると思います。 > 「小田切順之君の弁によれば、ラリー区間の減点はよりシビアになっており」、各ナビ >ゲーターの奮闘が勝負のベース(ラリー区間の減点が人より大では勝つことが困難)とな >ってきているようです。ナビゲーターの技術がより重要視されてきていると思います。 > > 「円盤または手回し式計算機」でどこまで正確にできるかですが、TE27、37、ミ >ラージュで優勝した場合で、各CPでの平均誤差はほぼ3秒以内です。現在では、1秒以 >内にとの要求がドライバーから出ているそうですが。 > 昔の「DCCSウインター(スパイクタイヤを使用)」では、1CPで必ず5秒以上の >誤差を生じていました。 >2CPからはあまり補正の問題はありませんでした。数年この問題に悩 >まされましたが、ある時期から解決しました。3人のナビが協力して正規の補正値にαを >いくらにすれ >ばよいか発見したからです。原因と解決方法については考えてみてください。・・・問1 >
> 車のセッティングによっても大幅な違いがあります。「アンダーステア」と「オーバー >ステア」では、一度痛い目に遭いました。ハイアベの途中でいつもと車の動きが変わって >いるので伸弥君に尋ねたところ違うとのことでした。もうあとのまつりでした。・・・問2
> PMCSクリサンテーモでは、つなぎ区間ではアメリカ式CP、ハイアベ区間ではヨー >ロッパ式CP、という混在したラリーがあり非常に楽しいものでした。ドライバーとナビ >はない知恵を絞りながら、また各チームは狐と狸と化かし合いながら戦いました。 >特に綾部選手とはその当時のNo.1かけ闘いました。 >どの様な作戦が良いか。ただ作戦を間違えれば、最初のハイアベ区間で脱落します。 >・・・問3
> あなた方が、記載されましたナビゲーションのいろいろな問題を楽しくまた懐かしく拝見させて >いただきました。約30年前の学生時代にナビゲーション練習のために色々な問題を考え、友人 >達と過ごした時間を思い出しました。
> この時代には、現在のナビゲーション用コンピュータはなく、手回し式のタイガー計算機やパイ >ロット計算機、円盤またはクルタ計算機を1台または2台使用して実際のラリーを行っていまし >た。だから計算方法を考えながら、また素早く計算できるようにいつも下宿で練習していたもの >です。
西田→私も自動車部に入部した当時ラリコンなるものは部に無く、電卓か円盤とKSカ ウンターがあるのみでした。そこで、先輩から円盤の使い方を教わりましたが、 実際には、デジタル世代ですので、PC8200?だったでしょうか、当時発売された ばかりのハンドヘルドコンピュータにプログラムを組んで何メートル遅れという ような計算でラリーを行っておりました。 >あなた方が考えられた記載の問題も、私たちが練習したり、大学ラリーで出題されていた問題か >らあまり複雑に(難しく)なっていないようですね。
→そうですか。ラリコンを使っている割には、新しい問題は、あまり出来ていな いのかもしれません。そのためでしょうか、大先輩ナビ(40才以上の)方々は、 簡単に手計算で解いてしまわれます。若い世代は、基本的な計算能力が落ちているのかもしれ ません
>あなた方の回答は、すべてラリコンを使うようになっていますね。 >初期(開発途上)のラリコンは現在のような仕様ではなく、もっと扱いにくいものでした。 >例えば、PC処理でPC発見前に時速をラリコンに前もってインプットしておき、PC発見時に >エントリーボタンを押すことになっていました。この場合の不都合はよく理解できると思います >が。
> 私としては、ラリコンが発達したおかげで多数の人がラリーを楽しむことが可能になりましたが >、勝負としては面白みが半減したと思います。(但し、国内ラリーに関して) >海外ラリーの場合は、つなぎの処理が非常に楽になりましたが。
>内心としては、ラリコンを誰でも簡単に使用できるように開発すべきではなかったと思っていま >す。
>初期発売当時は、私の基本給が8万円位でラリコンは25万円しましたが!
> − 山口 励 −
西田→同感です。私は、ドライバーからラリーに入りましたので、最初はナビゲー ションについて考える余裕も無かったために、実際には、ラリコンからナビの世 界に足を踏み入れました。この経験から言うと、ラリコンが無ければ、ナビを やっていなかったかなとも思います。 しかし、後輩達にナビゲーションを講義するようになり、円盤や電卓で計算し ないと計算能力が身に付かないことを痛感しました。そこで、ラリコンなしクラ スの設定されている新潟大学市民ラリーによく出場しましたし、後輩達にも出場 するようにさせました。 ところが、JAFの公認ラリーでは、このようなラリーテクニックも生かす場 が無く、あくまで補助計算の演習的になってしまいます。いろいろ考えた末、現 実的にラリコンを使うことを前提にHPを作りました。 この電卓、円盤での計算方法もHPに掲載しようと思っていたのですが、需要 が殆どないため後回しにしております。現実的にメールで頂く意見などでも補正 は、どうするとかいった話題ばかりです。 実際のラリーでラリコンを使わない(使わせない)ラリーが無いためだと思い ます。 このあたりが、HPを作っていて一番ジレンマを感じたところです。分計時で ラリコンなしでラリーを楽しむようなラリーは、今では、はやらないのでしょう か?


 メール送信 nishida@po.aianet.or.jp
メール送信 nishida@po.aianet.or.jp