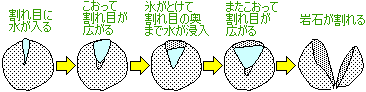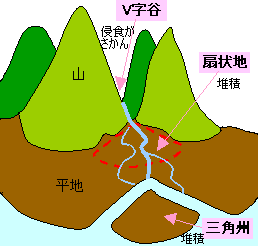長い間日光や空気や風雨などにさらされることによって、岩石が変質したり細かくくだけたりすることを風化といいます。
物理的風化と化学的風化が両方ともからみあって風化が進み、岩石がこわれていきます。
岩石は一部を除いて、いろいろな種類の鉱物が集まって固まっています。鉱物についてはこちらで確認してください。
| 機械的 (物理的) 風化 |
・気温の変化によるもの 岩石をつくっている鉱物の種類によって熱による膨張の割合が違います。 気温の変化のくり返しで、鉱物どうしはお互いに離れていき、 岩石に割れ目ができたりこわれたりします。 ・水がこおることによって起きるもの ・生物によるもの ・風の作用によるもの ※昼と夜の温度差が大きい砂漠地帯や、 |
|---|---|
| 化学的 風化 |
雨水や地下水などにいろいろな物質がとけているために
・岩石の中の鉱物が雨水や地下水と化学変化を起こす などの変化が起き、岩石がこわれていきます。 ※湿潤で高温の地域で起きやすい |