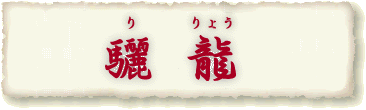
〜 リュウイン篇 〜
額にじっとりと浮かんだ汗が冷えていく。闇の中で、リュートは身を起こした。
静まりかえった家の内外に、殺気はない。気配はいたって穏やかだ。
窓を開くと、青白い雪明かりが射しこんだ。西の空に細い月が傾き、森の黒い影に沈みつつある。
ここは国の北西部。国境に近いフジノキ村だ。王都から早馬で七日、すなわち一シクルと二日のところにある。徒歩なら三〇日弱、すなわち一ルーニー弱といったところか。追っ手は東端のモイラの森で巻いた。彼らは自分たちが隣国へ逃亡すると踏んでいる。よもや、西の外れに逃れたとは思うまい。
いや。
黒髪が揺れた。
逃れたのは自分ただ一人。母はもう亡い。
額の汗をぬぐう。
追っ手はいつ気づくだろう。執拗なあの男があきらめるとは思えない。この辺境の小さな村にも追跡の手が伸びるだろうか。
固い雪を踏む音が聞こえた。
子どもにしては大きな白い手が枕元に伸びた。使い馴れた長剣をつかむ。
『女の子が、こんな危ないもの振り回しちゃいけません』
シズカは刀剣類をすべて取りあげたが、今は留守である。出産が間近に迫り、本村の実家に宿下がりしたのだ。その隙にリュートは家中を探し、シズカたちの寝室や物置などに隠されたそれらを取り戻していた。
雪を踏む音は近づいてくる。白い顔を窓辺に寄せ、黒い眼でそっと外をうかがう。
馬の鼻息が聞こえた。
「葦毛か」
白地にグレーの斑点のある馬面が、窓から飛びこんできた。鼻から白い息が激しく吹きだす。
「変わったようすはないか?」
つぶらな黒い眼はおっとりとした眼差しを向けている。鼻筋を撫でると冷たかった。
「今、水と飼い葉をやろう。厩で待っておれ」
馬首を追いだし、窓を閉めると、ふたたび闇に閉ざされた。
『そなた自身の生を生きよ』
さきほど夢で聴いた声が胸に甦る。そこでもまた現実と同じように、腕の中で消えていく命の炎をただ手をこまねいて見つめるほかなかった。
わからぬ。
心中でつぶやく。
私自身の生とはなんだ。母を失い、葦毛とともに、これからどうして生きていけばよいのか。
膝までの長い寝間着を脱ぎ、男物の上衣とズボンを身につける。ユキの古着を直したものだ。シズカは
「女の子なんだから、女の子らしくしなくちゃ」
と自分の古着を着せたがった。年齢とサイズとで着られなくなったが、まだまだ使用に耐える、刺繍とフリルのたくさんついたエプロンドレスだった。
しかし、ユキは即座に却下した。
「そんなもん着ちゃ仕事にならん。おまえみたいなお嬢さまとはわけが違うんだからな。オレのをやる」
ユキの古着は厚みのあるしっかりした木綿の服だった……かつては。今では着古されて生地は薄くなり、透けるのも時間の問題だった。
「なあに、子どもはすぐに大きくなる。新しいのをやっちゃもったいないだろう。それより、これでオレの服は一着減ったわけだ。新しいのを縫ってくれよ」
こうして譲られた衣服は、寒風にさらされると体温を無抵抗で明け渡した。
でも、まだマシだ。この家には食べ物があり、薪もある。寒い冬を越すことができる。
リュートは両手をこすり合わせ、息を吐きかけた。暗い家の中を記憶の通りにたどり、中庭に出た。母屋と離れの間には植えこみがあり、まるで垣根のような役割を果たした。その西の端には井戸が掘られていた。井戸から水を汲み、母屋の東に位置する厩へと運ぶ。ミヤシロ家の騾馬とリュートの葦毛が水を待っていた。彼らに水を飲ませ、飼い葉を与え、敷き藁を替える。ブラッシングを済ませると、今度は人間の食事の支度である。
薪を持って台所に入り、ストーブの火を熾して炊事をする。スープとハムエッグができあがると、パンをのせてユキの寝室へ運ぶ。
「もう朝か」
寝室のランプを灯すと、布団の中からユキが顔だけ出した。おっくうそうに腕を伸ばし、ナイトテーブルからパンを取る。固くなったパンをナイフでそぎ、熱い湯気のたつスープに浸し、柔らかくして食べる。
その間に、リュートはストーブの火を熾した。
「おまえのメシは、シズカよりはマシだな」
ユキは渋い顔でつぶやいた。
「お嬢さま育ちはいかん。一人前に働けもしないクセに人一倍食いやがって、言うことは人の二倍だ。二言めには『私の実家では』『実家の父が』とくる。女はすなおで働き者で器量よしがいちばんだ。あいつにそういうところがひとつでもあるか?」
「後で片づけにくる」
リュートは答えずに台所に戻った。新たにスープとパンと湯を盆に載せ、今度は離れに運ぶ。
離れは母屋より古く小さかった。元はきこり小屋だという。不要になったものをタダ同然でもらい受けたのだという。数十年前までは、この辺り一帯は林の中だったのだ。家の周りでは積もった雪がところどころ小山になっているが、それらは後に残った切り株である。この家の持ち主は開墾しなかったのだ。農民ではなかったから。
離れの扉を開けると、足下に仔猫たちがまとわりついてきた。白地に茶色や黒の斑点のある猫である。かわいいさかりは過ぎ、猫らしい形をとりつつあった。
母猫は細々と燃えているストーブの前に寝そべっていた。やわらかな古着に半ば体を埋め、時々細く眼を開けて、仔猫たちのようすをうかがっている。
「博士どの、朝食をお持ちしました」
リュートは仔猫を巻きこまぬように扉を閉め、ストーブのそばのテーブルに盆を置いた。
「ありがとう」
木枠に布を張ったついたての向こうから小さな声が聞こえた。しわがれてはいるものの歯切れのいい、よく通る声だった。端々にパーヴ北部の訛りがある。
リュートは戸口に戻り、わきの納戸を開けた。仔猫がにぎやかに鳴きながら足にまとわりついた。母猫までが駆けつけ、後足で二本立ちになりながら、前足を上に伸ばしてくる。
納戸の中は独特の匂いがした。天井からは、干し肉や干し魚、干した果物などが吊り下がっている。床には漬け物の壺が置いてある。
壺をひっくり返さぬよう、猫を踏まぬよう、リュートは注意して歩を進めた。備えつけのナイフで干し魚をそぎ取る。
猫を追いだしながら納戸から出、ストーブわきの餌皿に小さくそいだ干し魚を入れてやる。猫たちはリュートの手元を狙っては伸びあがり、落ちたものに群がっては次を待ちきれないようにまた伸びあがる。うなりながら餌にありつくさまは、かつて野生にあった獣であったことを思わせる。
リュートは次々に餌を与えた。干し魚がなくなると、餌場の上にあつらえた棚の上から粉ミルクの缶を取り、盆の上の湯に少量溶かし、猫に与えた。
「よい食べっぷりだ」
ついたての陰から、白髪の老人が現れた。リュートがミヤシロ家で目覚めた日、飛びだすのを押しとどめた老人だった。
「どれ、わしも食事にしよう。肉と野菜を取ってくれぬかの」
「はい」
リュートは納戸に戻り、干し肉と漬け物を少量取ってきた。肉はストーブの上に載せる。軽くあぶった方が旨い。
老人はパンを二つに割った。
「今日の天候は穏やかそうだ」
老人はパンの半分をスープに落とし、スプーンでその頭を叩いた。
「昼頃には晴れ間が見えるかも知れん。気温も上がりそうだから、川の上は歩かないようにしなさい」
「はい」
「ひとつあがっていきなさい」
漬け物の皿を指し示した。
「菜漬けなら、いらぬ嫌疑も招かぬだろう」
「いえ」
リュートは微笑し、首を振った。
シズカがまだ家にいた頃の話だ。リュートが初めて老人に食事を運ぶと、老人は薄く切った干し肉を幾枚か分けてくれた。
「あがりなさい。育ち盛りにはいくらあっても足りぬだろう」
その場で口にし母屋へ戻ると、ユキの嗅覚がいち早く察知した。
「オレのハムを盗み食いしたな!」
手が飛んだ。しかし、壁に叩きつけられたのは哀れにも家長のほうだった。考える間もなく身についたクセで、リュートの足はユキの腰を蹴っていた。しばらく王都帰りの名医は動けなかった。
シズカがあわてて間に入り、リュートに事情を聞いてユキに説明したが、ムダだった。
「あのクソオヤジが菜の一枚、粉の一粒だってくれるもんか!」
「じゃあ、きっと、スープに使った煮干しの匂いね!」
シズカは両手を腰に当てて、座りこんでいる夫の頭上からまくしたてた。
「煮干しもハムもちょっと変わった匂いだもの。だいたい、あなたの服からは薬草の匂いがぷんぷんするわよ。それで鼻がすっかり曲がってしまったんじゃないの。そうじゃないなら、風邪でも引いてるのね。私には、肉の匂いなんかぜんぜんしませんとも! 親も親戚もないたったひとりぼっちのかわいそうな女の子にいきなり手をあげるなんて、どうかしてるわ。そもそもあなたの稼ぎがよければ、私もこの子も毎日たっぷり肉が食べられるんですからね。恥を知りなさい! 私の実家では、この子ぐらいの育ち盛りの子には毎日肉を食べさせたものよ。実家の父がこのありさまを見たらなんていうか!」
「……わかった。わかったから」
「いいえ! ちっともわかってません!」
横暴な亭主をこってりしぼった後、シズカはリュートにこっそりささやいた。
「ユキとお義父さまには事情があってね、それですなおになれないの。許してやってね」
ミヤシロ家の食卓は、ユキの稼ぎだけでは立ち行かなかった。現にスープには、老人からもらった野菜が半分入っていた。そのことは、ユキには内緒である。
「アレには散々不自由をかけたからな」
老人は負い目を感じていた。
リュートにはわからなかった。猫をかわいがる穏やかなこの老人の、どこがそれほど憎いのか。
「洗濯物はありますか。これから川まで参りますが」
「ありがとう。間に合っておる。それにしても、そなたの手はこんなことをするためにあるのではあるまいに」
リュートは自分の手を見た。年不相応に大きな手。手入れのための油もなく、爪の周りはささくれだち、指はあかぎれで腫れている。
「暮らしのために働くことは、悪いことではありますまいに」
「すまぬな。わしがしっかりしておれば、そなたをこんな目に遭わせはすまいに」
「私は感謝しております。ここにおれば冬を越せ、博士に教えを乞えます。そもそも私には行き場がないのです」
「母君が生きておられたらな」
老人は悲しげに肩を落とした。
「こんなに幼い我が子を残して、どんなにか心残りだったろう」
ストーブの周りでは、満腹になった仔猫たちが母猫に身を寄せ、丸くなっていた。リュートはチラリとそれを見た。
「では、今夜またうかがいます」
老人がうなずくのを見て退室した。
台所で冷え切った汁ばかりのスープの残りをすすると、母屋の部屋を回って洗濯物をかき集め、洗濯袋に詰めこんだ。ユキの衣類は寝室中に脱ぎ散らかされており、どれが洗濯物か見分けがつかなかった。シズカは鼻を押しつけ『臭いで嗅ぎわけるのよ』と言ったが、リュートには区別がつかなかった。洗うべきものを洗わず、そうでないものを洗い、幾度もユキに怒鳴られながら、ようやく頻繁に洗うべきものを覚えだしたところだ。
袋に詰めこみ終わると、台所のストーブからポットを取りあげ、洗い桶の中に湯を張る。洗濯袋を腕にさげ、洗い桶を抱えて小川へ向かう。小川まではおよそ一五〇歩あまりの距離である。夏ならばたいした距離ではないが、この季節には容易ではない。雪に埋もれないよう、踏み固めた細い道だけをたどる。踏み外せば、やわらかく深い雪の中に身が埋まってしまう。
ようやく小川にたどりつくと、打ち石で小川に張った氷を割った。洗い桶に雪を入れ、ぬるま湯をつくる。洗濯物を洗い桶に浸し、小川のほとりの平たい岩の上に広げて打ち石で叩く。
最初、このやり方を習った時、リュートは驚いた。衣類が傷むであろうことは明白だったからである。洗濯板や石鹸は用いないのかとの問いが喉元まで出かかったが、飲みこんだ。ミヤシロ家では、診察室以外で石鹸を見かけたことはなかった。彼らにとっては高価なものなのかも知れないと、リュートは思った。
打ち石で叩いた後は、川の水につけて汚れを洗い流す。揉みだしては絞り、絞っては揉みだしをくり返した後、洗い桶にたまった汚水を川に流して終わりになる。
かじかんで言うことをきかない手を、途中で何度もぬるい汚水につけた。汚水は冷気で急速に冷えていく。それでも川の氷のような冷水よりはマシだった。
母屋へ戻り、台所の片隅に衣類を干す。ストーブの火は落ちていたが、室内はまだ暖かかった。リュートは両手を首筋に当てた。首から伝わる冷たさで、思わず身震いをする。
次は薪割りだ。少しでも手の感覚を戻しておかなければ。
台所の裏手、湯屋と厩の間が薪割り場だった。握力が戻ると、リュートはしばらくそこで手斧を振るった。薪割りは楽な仕事だった。物思いに耽ることもできたし、体も温まった。
昔々、名もなき国に気弱な王さまおりました
気も小さければ体も小さい
間尺の足りない小さな仔馬にまたがって
小さな沼を散歩しました。
吟遊詩人がキタラの音にのせて語った物語を、リュートは思い出していた。詩のリズムに合わせて、斧を振るう。
空は黒くかき曇り大きな雨粒落ちました
雷大きく轟いて大きな木の根に落ちました
雲の中から黒龍がまっすぐ地上に降りました
美わしい姫に姿を変えました
姫の髪は黒馬のよう
姫の眼は黒炭のよう
姫の肌は真珠のよう
姫の唇は朝日のよう
姫の瞳は遠くを見ます
見えない翼うち振って
たちまち世界へ飛びだしました
小さな王さま追いかけました
山も谷もひとっ飛び
川を渡り虹を越え
ぐるりと世界を一回り
それでも王さま追いかけました
小さな沼にもどった美姫は
再び龍に姿を変え、空に昇っていきました
小さな王さま大いに嘆き、
あふれた涙でみるみるうちに大きな湖できました
小さな王さま気づいてみれば
気も大きければ体も大きい
仔馬もいまや大きな馬
国もいつしか大きな国となりました
黒龍の姫という昔話である。リュートはこの手の詩が好きだった。『昔々、神と人とが共に地上にあった頃』で始まる勇者セージュの冒険談や、遠い地方に伝わる伝奇物は心を躍らせる。
セージュか。今頃どうしているだろう。
勇者と同じ名をいただいた、同い年のいとこに思いを馳せる。
歳の割に体格がよく、広い肩に褐色の巻き毛が揺れていた。伯母似の暗褐色のまなざしは、短気でよく涙に濡れていた。泣き虫のセージュ。毎年、夏になると、野を走りまわった。勇者ごっこが好きで、棒をふりかざして弟のエドアルを追いかけまわした。
小さなエドアル。三つ下のもう一人のいとこ。走りまわるより、本を読んだり、花摘みしたりするほうが好きなおとなしい男の子。兄に追われると、きまってリュートの陰に隠れた。明るい栗色のやわらかな巻き毛が腕に触れると、おもはゆい保護者意識に見舞われたものだ。
二人のいとこと、伯父上に伯母上。私がもはや死んだものと思っているだろうか。
リュートは首を振った。
そのほうがいい。私に関わっては災いを招く。伯父上の母君がいい顔をせぬだろうし、あの男につけいられる隙を作ることになる。
――あの男。
振りおろした手斧が薪割りの台に深く突き刺さった。引き抜くには、渾身の力をこめなければならなかった。
あの男。母上の命を奪った憎い仇。
眼を閉じずとも、ありありと姿を思い浮かべることができる。
赤いなめし革のベストに、丈の長いモスリンの上着。袖はリボンで二カ所くくられ、色の違う布地がスリットからのぞいている。キュロットにもやはりスリットが入り、大きくふくらんでいる。派手で贅沢な衣装。
他人を嘲るように大きく見開いた茶褐色の眼。その眼は、母をおぞましくも嫌らしい目つきで眺めまわしたのだ。肉厚で大きな口。その口は髭の中から忽然と現れ、母を辱めては下品で高らかな笑い声をあげたのだ。
つば広帽を斜にかむり、その陰からはくっきりと左頬の刀傷が見える。あの男は隠しもしない。その漁色家の証拠を。
母上は亡くなったのに、あの男は生きている。我が世の春を謳歌している。
許せぬ。断じて許せぬ。
だが、今の私になにができる? たった一人、未熟な剣技と拙い知恵で。母上でさえ力及ばなかったというのに。
リュートは深くため息をついた。
仇討ちどころか、今日を生きるのに精一杯だ。生き延びることは、母上の遺言でもある。己の生とやらを見いださねばならぬ。
リュートは薪を割った。
さしあたっては、今日の糧を稼がねばならぬ。
昔々、神と人とが共に地上にあった頃
虹の清水の源に怪物ヘデロがおりました
吐きだす液ですべてを溶かし
手当たり次第に飲みこみました
再び、古き伝承の歌に合わせて斧を振るう。勇者セージュの冒険談の一つである。
野を飲みました
山を飲みました
川を飲みました
村を飲みました
いとむくつけき怪物ヘデロ
この世の果てまで飲み尽くす
神も人も為す術なく
天を仰いで怯えるばかり
怪物ヘデロをいかでか倒さん
勇者セージュ剣に誓う
天地を駆ける龍神よ
知恵と力を与えたまえ……
薪割りが終わると、診療室にユキを呼びに行った。
「おまえは仕事が遅いなあ。薪ぐらいまともに割れないのか。待ちくたびれたぞ」
薬草を鉢ですりつぶしながらユキは言った。
「ほら、早く着替えを出せよ」
往診には傷みのない新しい服を着ていく。ユキだけではない。鞄持ちのリュートも同じである。羊の革をなめした暗褐色のコートを羽織り、油をたっぷりふくんで水をはじく革の靴を履く。
「高かったんだからな、キズなんかつけるなよ」
ユキは決まり文句のようになった言葉を言いきかせる。
「まったく、助手ってヤツは金がかかってしょうがない。いいか、元がとれるぐらいには働いてもらうからな」
村までは細い踏み跡をたどっていく。冬の間じゅう往診の往復で踏み固めた道だ。体の幅ほどしかなく、踏み外せば深雪に埋まってしまう。降雪のあった日には、新雪に覆われて道を見失うこともある。
リュートは空のリュックを背負い、左手にはユキの医療鞄を持って先頭を歩きだした。道に足跡がつき、ユキはその後を悠々と歩く。さらに後ろから、葦毛の馬が一頭、尻尾をゆっくりと振りながらついてくる。
本来なら、馬車はおろか、馬一頭通ることもできない細い道である。だが、筋骨たくましい馬は、脚に馬用のかんじきを履いていた。浅く雪に沈みながらも、歩を進めることができたのである。だが、決して楽な歩行ではない。並外れた体力がそれを可能にしたものの、冬になって飼い葉の量が増えた。
「エサ代がかさむぞ。出歩かせるな」
とユキは渋い顔をしたが、できない相談だった。この忠実な馬を、乗り手と遠く離すことはできないのだ。もしムリにでも厩に閉じこめれば、器用に扉を開けるか、力強い足でぶち破るかしてしまうだろう。
では、自分が乗ろう、とユキは馬に近づいたが、威嚇のいななきにたじろぎ、あきらめた。
この馬は、自分と母以外は何者も背に上げないことを、リュートはよく知っていた。たとえ敵の手に落ちても、決して自分たちを追いつめる側にまわらぬよう、厳しく仕込まれたのだ。
馬は身を守るための術であり、パートナーであった。この世に生まれ落ちた時から生命の危険にさらされていたのだ。今、この時でさえ、あの男は追ってくるかも知れない。
![]()