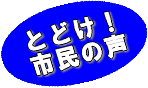 |
「市民が創る司法改革公聴会」 〜司法制度の大転換のとき〜 |
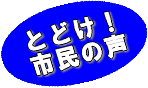 |
「市民が創る司法改革公聴会」 〜司法制度の大転換のとき〜 |
21世紀に向けて、日本の裁判・司法制度が大きく変わろうとしています。
市民が利用しやすい司法制度へ改革するために、昨年7月より内閣の司法制度改革審議会では、2年間という期限のなかで、司法全体の現状を総点検し、官僚裁判官制度の弊害をなくす法曹一元制度、市民参加の裁判制度である陪審制、現在はない被疑者段階での公的な弁護制度、法律家養成制度の改革であるロースクール(法科大学院)構想、不足している弁護士や裁判官の増員、など抜本的な改革方向を検討しています。
これまで遠い存在であった裁判や司法が、この司法制度改革審議会の答申いかんによって、市民本位の司法へと生まれ変わる可能性があります。
しかし、現状の問題のある制度のままを守ろうという動きも一部にあり、市民本位の改革の実現のためには、私たち市民がもっともっとこの問題に関心を持ち、働きかける必要が有ります。
今こそ、ひとりひとりが声をあげる最大のチャンスです。
この[市民が創る司法改革公聴会]で、司法改革について、みなさんそれぞれの想いを投げかけてみませんか。
![]() 意見発表者募集(司法制度改革に関するご意見を発表していただける方を募集しています。)
意見発表者募集(司法制度改革に関するご意見を発表していただける方を募集しています。)
|
司法制度改革審議会とは? 司法制度改革審議会設置法(1999年7月27日)で、「21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する」(同法2条)ため、内閣に設置され、2年間で審議を終え、内閣に意見を述べることになっている。司法制度改革審議会は、佐藤幸治氏(会長・京都大学法学部教授)、山本勝氏(東京電力(株)取締役副社長)、高木剛氏(日本労働組合総連合会副会長)、吉岡初子氏(主婦連合会事務局長)、中坊公平氏(元(株)整理回収機構代表取締役社長)ら13名の委員で構成されている。 昨年12月、審議会は今後審議すべき項目を「論点整理」として発表し、月2回程度のペースで審議が進められている。これまでに、民事法律扶助、法曹養成(法科大学院問題)、弁護士制度改革、民事司法改革、裁判所・検察庁の人的充実、刑事司法改革(被疑者弁護)などが審議された。今後、法曹一元、陪審制などを審議する予定である。11月の中間報告に向けて精力的に審議が続けれられている。 司法制度改革審議会の地方公聴会は、3月18日の大阪をかわきりに、福岡(6月17日、福岡国際ホール)、札幌(7月15日、ホテルライフォート札幌)、東京(7月24日<月>17時30分〜20時30分、日比谷公会堂)で行われる。東京の地方公聴会の傍聴申し込みは6月23日まで。詳しくは、司法制度改革審議会事務局総務係(電話:03−3519−7500)へお問い合わせください。 |
![]()