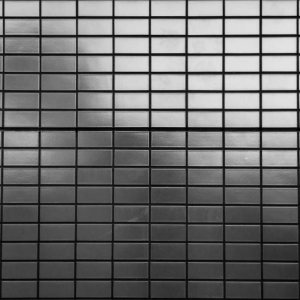 |
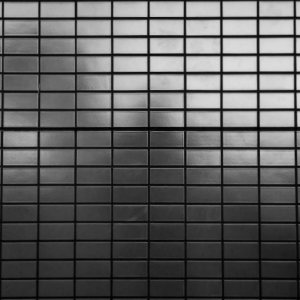 |
| Rolleiflex3.5F(Planar) f8, 1/250 |
Rolleiflex3.5F(Planar) f8, 1/250 |
| さて、このサイトを開いてから、多くの方に色々とご指導ご鞭撻をいただき、また「こんな比較も見てみたい」というリクエストも頂戴してまいりましたが、中でも今回は史上最大の難題とも言えます(いや、大した『史上』でもないんですが…(笑))、プラナーの、しかも3.5F同士の対決であります。 プラナー3.5Fは、1958年から1980年頃まで生産された(資料によってやや差あり)、ローライの数あるモデルの中でも、かなりの「長寿モデル」です。その為、途中数度の「仕様変更」を行っており、微妙にですが見た目、あるいは一部操作性も異なる「3.5F」存在します。 中でも今回取り上げるのは、名目上は全く同一の「ローライフレックス3.5F プラナー付き」。「何でそんなものの比較を?」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、実はこのプラナーf3.5のレンズ自体が、ある時期から仕様変更をしていた、という衝撃的(?)な事実があったのです。資料によれば、1965年頃から、プラナーのf3.5レンズは5枚構成から6枚構成に変更になっていたというのです。そこで、今回はそれらを比べてみようというわけです。 今回の比較もまた、当サイトの常連の方々のご協力を頂きました。ニコニコカメラさん、CARECAMさん、KOJIさん、本当にありがとうございました。 さて、まずは今回比較しようとしている2台が、本当にこの「仕様変更」をまたいでいるのかを確認しなければ意味がありません。今回比較できたのは、同じ3.5Fプラナーのシリアル227xxxxと、同じく284xxxxです。資料によって多少、「区切り方」が違うのですが、前者は1960年代前半に生産されたF3(またはタイプ3)で、後者は1970年代後半に生産されたF4ないしF5に入るようです。年代から判断するに、前者は5枚玉、後者は6枚玉と見て良さそうです。(注) さあ、どうでしょう。違いはあるのでしょうか? 注:後に、どうも必ずしもこの時代なら確実に5枚とは言えないらしいという情報があり、現在、F1の3.5Fとの追加比較を画策中です。 |
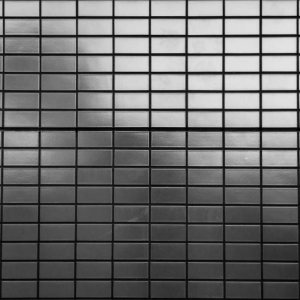 |
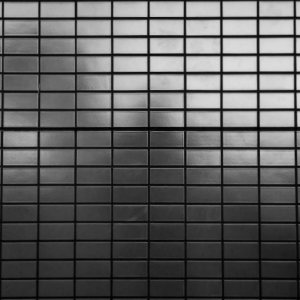 |
| Rolleiflex3.5F(Planar) f8, 1/250 |
Rolleiflex3.5F(Planar) f8, 1/250 |
| いつも通り、また歪曲具合から見てみましょう。微妙ですね。微妙ではありますが、やや改良型であるはずのF4の方が、F3に比べて糸巻き型が強めなような気もしなくもありません。しかし、いずれも言われなければ気が付かない程度のもので、こういう極端な被写体を撮った時やっと見えてくるかどうか、というレベルです。 |
 |
 |
| Rolleiflex3.5F(Planar) f8, 1/250 |
Rolleiflex3.5F(Planar) f8, 1/250 |
| スキャナーの性能の限界により、WEB上では多少違って見えるかもしれませんが、上の神社の山門の写真については、目立った違いは見当たりませんでした。今回の場合、微妙な違いになるであろうことが予想されたので(大違いだったら大変?(笑))、同じ被写体についても露出、絞り値などを変えながら何カットかづつ撮ってみたのですが、開放、F8、F22と撮ってみたこの写真でも、どの絞り値でも差は感じられませんでした。上の方に、「ハト避け」と思われる金網が張ってあり、もしかするとその辺りのボケ方に差が出るかと思ったのですが、それも確認できませんでした。 ここで1つ、色調、発色についてお話しておきます。以前、プラナーの2.8Fなどと3.5Fを比較した時に、その3.5Fについて、「他の個体よりもアンダー目に写るようです」と書きましたが、そればかりではないようです。どうやら、「プラナーのf3.5は、こういうセッティングがなされている」というのが正解なのかも知れないと、今回の比較を通じて思うようになりました。というのは、今回の2台の3.5Fでの撮影結果を見てみると、同絞り値、同シャッタースピードでは、違いを見出すどころか、気持ちの良いくらいに同じ感じの発色傾向だったからです。つまり、3.5Fとしては「これで合っている」ということなのでしょう。プラナー2.8F2台を比較してみた時も、そちらはそちらでほぼ同じ露出傾向を示していましたので、こういう傾向がそれぞれの「持ち味」と見て良さそうです。 こういう「濃い目」の発色を、ツァイスのレンズの特徴として好む方には、むしろf2.8系のプラナーよりも、f3.5系のプラナーの方がその雰囲気を楽しめるかも知れません。 |
 |
 |
| Rolleiflex3.5F(Planar) f5.6, 1/500 |
Rolleiflex3.5F(Planar) f5.6, 1/500 |
| この木の写真でもやはり、発色等は差を感じませんでした。木の実に反射した太陽光による点光源のボケ方、形状も似た感じです。奥の方の葉の輪郭のボケ方も差があるようには見えません。 やはり、このサイトの比較テスト史上最大の難題です。(笑) |
 |
 |
| Rolleiflex3.5F(Planar) f3.5, 1/500 |
Rolleiflex3.5F(Planar) f3.5, 1/500 |
| この花のカットで何を見ようとしたかというと、花の色がピントを合わせたところとピントを外れたところでどう表現されるかと、細かいところの描写に差があるかでした。 しかし、これでも差は分かりませんでした。絞り値を変えてみても同様です。ボケの形まで同じようです。「これってほんとに違うの?」という感じでした。 |
 |
 |
| Rolleiflex3.5F(Planar) f3.5, 1/500 |
Rolleiflex3.5F(Planar) f3.5, 1/500 |
| この樹木の写真は、右斜め前方から太陽が照らしているものです。逆光時の描写についても見てみました。 まず、基本的な描写についてですが、細部に渡って観察してみても、「ここがちがう!」と報告できるような違いは見当たりませんでした。葉の葉脈などまで観察みましたが、どちらも細かいところまできちんと出ています。ピントを外れたところのボケ具合も、同じに見えます。 半逆光ということで、わざとフードを外して撮影してみましたが、それでもこの角度ではどちらが特にフレアやハレーションが出た、というようなこともありませんでした。 |
 |
 |
| Rolleiflex3.5F(Planar) f3.5, 1/500 |
Rolleiflex3.5F(Planar) f3.5, 1/500 |
| 周辺解像度という観点からはどうでしょう? 10倍のルーペで細かく観察してやっと、「ややそうだと言えるかなぁ…」というレベルですが、このカットの比較で見ると、ややF4の方が、F3よりも周辺部においては解像度が高いかな?というところが見てとれました。そのわりに(?)、中心部においてはむしろF4の方が甘めな気もしないではないのですが…。しかし、ご覧のように中心部に対して画面上部は遠く、下部は近いわけですから、その両方がよりクッキリしている(ボケて行き方がやや緩やか?)ということは、やはり「やっとF4の改良型としてのアドバンテージが垣間見えたか?」という感じです。(拡大写真はこちら) もっとも、10倍のルーペでじっくり観察してやっと…、ということが、どの位問題になるかと言えば微妙な気がします。絞り込むような撮影では差も更に無くなるでしょう。ただ、「開放近くで撮影した作品を大伸ばしにしたい」というような場合になら、差が出てくるかも知れません。逆を言えば、「誤差の範囲かも…」という気もします。(笑) 今回の比較をするにあたって、「何故、同じモデルの製造期間中にレンズの設計変更があったのか?」について、私が予想したのは、実は「色収差の補正ではないか?」ということでした。名レンズとはいえ、モノクロ全盛の時代の設計であったプラナーでは、カラー撮影の機会が増えてきたユーザーのニーズに応えきれず、レンズを1枚足して補正したのではないか、と。 しかし、今回の比較の範囲では、そう思えるほどの違いは見つけられませんでした。「これは…」と思えた違いは、唯一、周辺解像度(というほどのものかはともかく)の違いだけだったのです。 ところで、何故このような「マイナーチェンジ」が行われたのでしょうか? 今回の比較にあたって読んだ資料の中に、ある人の「ローライはプロ、ハイアマチュア用カメラの王様だった。ハッセルやニコンに追い落とされるまでは…」というような記述がありました。70年代と言えば、ハッセルの地位を不動のものにした「500C/M」が出現した時期です。もしかしたら、「6枚玉プラナー」は、生き残ろうとするローライが、そこに少しでも改善の余地があるなら挑戦しようとしたことの産物なのかも知れません。 …、もっと中古相場に影響を与えるような「大発見」があっても面白かったかと思うのですが…。 ちょっと残念!(笑) 追記: 「もしかしたら、今回の2台は両方とも6枚玉では?」という情報をいただきました。 そう言われてみると、完全に否定し切れない感もあります(ちょっと酷似し過ぎ?)ので、今回のテーマの結論を断じるのは、もう少し先になりそうです。機会に恵まれましたら、追加報告いたします。 補足: 今回の2台をそれぞれ「5枚玉」「6枚玉」と見込んだのは、A.Evansの著書に「元ローライの担当者から、「65年頃に、確かに6枚玉に変更した』との証言を得た」という記述がある他、いくつかの資料によって比較的後期に6枚玉への変更が行われたやに解釈できる記述があったためですが、一方、当サイトの「談話室」に通りすがりさんからお寄せいただいた情報などに寄れば、もっと早い時期から6枚になっていたということになりそうです。しかし、KOJIさん所有の3.5F、かつて某有名カメラ雑誌でテストされた3.5Fの本体のロット番号と、プラナーの製造番号が順番としてスッキリと符合しないなどの点も指摘され、謎は深まるばかりです。(笑) 何はともあれ、と、今回の2台を改めてよく観察してみましたが…、結論としては、残念なことに、どうも前面から見ても、背面から見ても、レンズの枚数という意味では、同じような感じで、「6枚玉のロット違い」という雰囲気です。せっかくいろいろ撮ったのに…。(一応こちらも) (T-T) しかしながら、今回の試写を行ったからこそ、これまで個体差だと思っていたアンダー傾向の発色が、3.5Fの特徴であることや、ロット違いによるコーティングの違いがあることも確認でき、また一般にある、何となく6枚玉が希少であるかのような認識に対する疑問を持つ事も出来たわけですから、私としては無駄骨だったとは思っていません。むしろ、新たな課題に燃えて(?)おります。 というわけで、今回のレポートは今回のレポートとして、残しておこうと思います。 また機会に恵まれたら、ぜひ「どう見ても5枚」のものと、「文句なく6枚」のものを比較してみたいと思います。 とりあえず、今回は「前編」ということで、ご容赦ください。 |