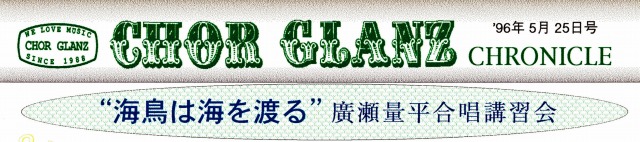|
|
♯ あなたも外国へ行けば本場の歌手 ♯
|
|
一 同:
|
乾杯! 今日はご苦労さまでした。
|
|
H先生:
|
今日の講習会についてのご感想はいかがですか? わかりやすかったですか?
|
|
K:
|
ちょっとわかりにくいところもありましたけど、先生の誠実なお人柄が出ていて親しみやすかったです。
|
|
H先生:
|
私は、音楽に転調が必要なように、お話にも彩りがあったほうがいいと思っているので、ずいぶん脱線してしまいましたね。
|
|
N:
|
全米の合唱指揮者の集まりが先生の曲を採り上げ、各地で合唱講習会を開くのでぜひにと招かれたという話にはさすがという思いがしました。また、受講者全員が指揮者というのもすごかったです。その時のビデオがあるというのでぜひ見せていただきたいですね。
|
|
H先生:
|
米国の合唱団では、外国の曲であっても出来るかぎりそれぞれの原語で演奏しようという姿勢があるから、私の作品も当然日本語でやっていました。
|
|
K:
|
ヘェー、大変な力の入れようですね。
|
|
H先生:
|
アメリカ人が妙な発音で日本語と格闘していたところはとても面白かったし、感心しました。だから、そこへあなた方のような日本人の歌い手が指導に行けば、さすが本場の演奏家はすごいなとなること請け合いですよ。
|
|
N:
|
われわれが外国人が英語で歌うのを感心して聞いているのと、ちょうど逆の関係という訳ですね。
|
|
|
♭ 作曲家には二通りのタイプがある ♭
|
|
H先生:
|
私は、楽譜にあまり書き込まない主義です。つまり演奏者に自由に解釈して欲しいし、思いもよらない解釈の演奏に出会うとドキドキしますよ。
|
|
N:
|
それはいいことを聞きました。われわれはいつもほとんど楽譜に従わずにのびのびやっていますので…。安心しました。
|
|
H先生:
|
!? まぁ、それは結構なことです。ところで、私とは正反対の立場をとる作曲家には、とにかく自分が書いた譜面どおりに演奏しろというタイプの人がいます。
その代表が高田三郎さんですね。彼は、自分の目の黒いうちは勝手な解釈による演奏は許さんというほど楽譜に忠実な演奏を望んでいますが、そうは言っても作曲家が死んでしまえばそれまでですから、どうですかね。
ところで、ジョッキのお代わりをもらいましょうか。
|
|
K:
|
そうしましょう。
エーっと何を話していたんでしたっけ?
そうそう、さっきのお話ですがそういう作曲家は、演奏会のたびに気がきじゃないでしょうね。
|
|
|
♪ 曲が生まれてくる背景も重要 ♪
|
|
N:
|
先生はモデル演奏を聴いたあと、解説されるときに先ず歌詩の解釈についてかなり時間をかけていましたけど、やはり歌詩は重要なものであるという認識からくるのでしょうか。
|
|
H先生:
|
そのとおりです。歌曲は詩からできているという原点を忘れてはならないと思っています。ところで、今日の最初の女声合唱曲「海はなかった」は、それまでの綺麗ごとだけで曲を作るのではなく、もっと人間社会の底にある問題も取り上げたいという観点から作ったものです。歌詩が持つ力をどこまで作曲家が活かせるかが重要です。
ここで企業秘密をひとつ明かしますと、この曲を作るに当って、そのとき流行っていた井上陽水の雰囲気も意識に入れたことは確かです。
|
|
K:
|
なるほど、そのような深い解釈が必要な曲を今日は中学生がやった訳で、ちょっと荷が重かったかも知れませんね。
|
|
H先生:
|
でも、よくやっていたと思います。しかし私は中学生だからとかいって変に妥協することはしたくないので、言いたいことは言わせてもらいました。
|
|
N:
|
やはりそうでしたか。中学生も必至にやっていましたね。
|
|
|
♭ 伴奏にも込められた意味がある ♯
|
|
H先生:
|
「オロロン鳥」は作詩家の更科源蔵さんが不遇の時代に作られた詩を使っているので、背景としては暗いものです。だからあまり遅すぎるテンポでやるとますます暗くなり過ぎるので注意して欲しいと思っています。
出だしの4小節から6小節にかけてのピアノ前奏は「荒々しい海岸の崖っぷち」、7小節目からはじまる三連符は対照的な「波の音」です。さらにDの部分のAgitato「水平の落日に」というところは、広々としたところに出て夕陽を見ているイメージです。そのあとの「アー、アー」は言葉にならない詠嘆とでもいうところです。
|
|
K:
|
なるほど、よくわかりました。
|
|
H先生:
|
また「エトピリカ」は子音をはっきりと発音し、鋭さを出すように心がけてください。盛り上がる部分ではブレスも素早くするといいですね。
|
|
N:
|
とても勉強になりました。でもそろそろ頭がグルグルしてきたんで、先生今日はこれで終わりにしましょう。
どうもご馳走さまでした。お先に失礼します。さようなら──。
|
|
H先生:
|
えーっ…! ? ちょいとー
|
| |
|
![]()
![]()