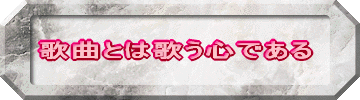昔から私淑する音楽評論家吉田秀和さんは、1913年9月23日生まれだから、もう95歳にもなろうというご高齢にもかかわらず今でもご健在である。30年にもおよぶ長寿番組となったNHK-FM『名曲の楽しみ』はまだ続けておられるし、執筆活動もますます旺盛で休まることがない。今年も新刊『永遠の故郷 夜』を出版された。この本は、歌曲について書いた小文を集めたもので、文芸誌「すばる」に連載中の《永遠の故郷》から再編集している。今回は「夜」の巻で、順次「薄明」「昼」「黄昏」と続く全4巻とする予定とのこと。吉田さんはあとがきで、「この全四巻というのは、まだ書いていないものも入れての皮算用で、神様が許して下さるかどうか。あとになってみなければわかりません。しかし、こうして始めた以上、シューベルト、シューマン、あるいはドビュッシー、ラヴェルなどなどにたどりつけたら、と夢みているのは確かです。」と意欲をのぞかせている。
この本には、吉田さんの若いころの淡い恋(失恋?)の話も載っている。これまでこの種の身の上話を読んだことがなかったが、5年前に最愛の奥様バルバラさんを亡くされ、もう気兼ねすることもなく公に口にすることができるようになったとでもいうのであろうか。出版直後の新聞につぎのようなインタビュー記事が載っていた。
「僕は中原中也に言われて仏文科に進んだようなもので、詩人の友人も多い。これまでは音楽は音楽の中だけで語りたいと思っていたので、文学には深入りしないようにしてきた。でも言葉に近づきたいという思いもどこかにあり、今回は素直に従ってみた。」
「音楽に姿を現してもらうためには、こちらも裸にならないといけない。」と考え、私的な体験も数多く盛り込んだそうだ。高校時代の淡い恋については「フィクションかもしれないので、事実かどうかの判断は読者にお任せします。」とぼかしている。
私が、吉田秀和さんに私淑しているというほど思い入れがあるのは、『名曲の楽しみ』での慎重に言葉を選んだ的確な解説ぶりに感心させられたり、格調高い文体で展開する音楽評論に触れたりしたことがあるからだけではない。かれこれ十年ほども前のことになるが、上野駅の構内でばったり吉田さんにお会いしたことがある。もちろん吉田さんは、私のことなどご存じない。そのとき、ほんとうにたまたまではあったけれど、私の鞄の中に吉田さんの著書『レコードのモーツアルト』が入っていた。このような巡り合わせはとてもめずらしいことではないだろうか。すくなくも私にとってはなんともいえず、うれしいことであった。私は意を決して吉田さんにお声をかけた。サインをしていただけますか、と。そして、鞄から取り出した『レコードのモーツアルト』の表紙裏にサインをお願いした。吉田さんは「あなた、お名前はなんと仰るの?」と、私の名前を確認しながらペンを動かしはじめた。そのときの品のよい問いかけの声はいまだに耳に残っている。
その『レコードのモーツアルト』は今でも本棚に納まっている。もうすこしくわしいことは、雑感欄2004年12月4日に「思いもかけぬこと」と題して記してある。ささいな個人的なことではあるが、忘れられぬ思い出となっている。
さて、『永遠の故郷 夜』のあとがきに、ちょっと気になることが書かれていた。フローリアン・ロダリのエッセーの中に、ハインリヒ・ハイネが「歌曲とは歌う心である。」と言っていたのを見つけたと書いてあった。
フローリアン・ロダリ(Florian Rodari)のエッセーを読んでいたら、ハインリヒ・ハイネが《Le lied est le Coeur qui chante》と言っていたと書いてあった。どこでみつけた言葉か知らないが、確かにその通りだ。
「歌曲とは歌う心である。」
だから歌曲をきき、歌曲について書くとは歌曲をきく心の働きを述べることが大切だ。ほかに書くことはないといってもいい。その歌曲を書いた人についての知識をふりまわしたり、作曲をめぐるあれこれの状況、事情について多言を弄するのは、本当なら、余計なことなのだ。
「心から出たものなのだから。そのまま、心に通じるように」とベートーヴェンも言ったではないか。
けれども、その心に通じたものを、そのまま、書くのは、やさしいようで、とてもむずかしい。シューベルト、シューマン、ブラームス、ヴォルフ、シュトラウス、マーラー、ベルクたちの数少ない歌曲の中に生きている「心」を書くに至っては、限りなく不可能に近い。
音楽、演奏の批評とか評論は、楽曲自体を解説することとはまったくちがう次元のことであろう。まして、歌曲となると、「歌曲をきく心の働きを述べることが大切だ」というが、「けれども、その心に通じたものを、そのまま、書くのは、やさしいようで、とてもむずかしい。」ことなのである。
ところで、吉田さんの文章はいろいろな意味で面白い。上に引用した短い文章だけでも、多くの特徴があることに気づかれないだろうか。まず目につくのは、言葉使いが平易ということ、まるで口語体のような語り口調であること。そして、句読点を多用し、短めのセンテンスで話を進めている。だが、書かれた内容は、批評の世界で生きてこられた方だけに、じつに深く考えられたもので、慎重に言葉を選んでいることがよくわかる。ふつうは、「けれども、その心に通じたものを、そのまま、書くのは、やさしいようで、とてもむずかしい。」などとは書かない。読点「、」は、本来は意味が変わる箇所で使用するのが通常だろうが、同時にそこにストレスが発生し、リズムも変わる。リズムが変わることで一種の強調効果も出てくるように思う。吉田さんは、そのあたりを睨んで書いているのではないだろうか。
吉田さんの文体は、いつでもこのように句読点が多く、ひらがなを多用しているというわけではない。昔の著作をみると必ずしもそうではないことがよくわかる。概してお歳を召されてからの文章にそのような傾向が強くなったかなという印象である。
吉田秀和全集第6巻、『ゴルトベルク変奏曲』によせて、ではつぎのような文章をつづっている。
グールドがバッハをひくのをきいていると、この「反応と即時性といろいろなタッチの微妙な決定の調節」がものすごく鋭敏に、しかも、際立って高度の知能的な態度と技術の水準と緻密な音楽性とがからみあいながら、演奏の進展するさまがよくわかる。それに一面では極度にスリリングな魅力の源泉になっているが、一面では聴後の全体の印象を統制のとれたものにする原因ともなる。
前述の文体と較べるとずいぶん雰囲気がちがうが、「音楽に姿を現してもらうためには、こちらも裸にならないといけない。」ということとどこかでつながっているのであろうか。
![]()