指揮者ローベルト・スント率いる、スウェーデン王立男声合唱団が1984年以来21年振り2度目の来日を果たした。正式名称は「オルフェイ・ドレンガー」ODである。「総勢90名の圧倒的な迫力で、世界随一の実力と人気を誇る男声合唱団」のコピーそのままに、日本ではまず聴くことができないほど柔らかなピアニッシモから、音程を崩さずに歌われるフォルテッシモまで、どこを取り出してもまさに一級品であり、噂に違わぬ演奏に思わず舌を巻いてしまった。王立とはいえ一応アマチュアの合唱団であり、定期的な練習は週に1回、3時間というからこれもまた驚異的である。
ODの創立は1853年、ストックホルムのウプサラ大学の合唱愛好家が集まって、ベルマンの「Hor i Orphei Dranger」を歌ったのが始まりとのこと。ちなみに「オルフェイ・ドレンガー」とは「オルフェウスのしもべたち」という意味である。オルフェウスは、ギリシャ神話に登場する吟遊詩人。アポロンから与えられた竪琴に合わせて歌うオルフェウスの歌は、鳥獣、山川草木をもひきつけたという。
今を去ること21年前、初来日したODのハーモニーを聴いた人々は、瞬く間にその魅力にとりつかれ、以来再来日を待ち望む声が高まっていた。このサイトにOD大好き人間としてたびたび登場していただいている菅野哲男さんもそのお一人であった。
今回の日本ツアーは、全国7都市で計8回開催されたが、第6回目の公演(10月13日東京オペラシティコンサートホール)を聴いた。ODを聴くのは初めてだったが、演奏レベルの高さに度肝を抜かれたというのが正直な感想である。
ステージは二部構成。前半は、アルヴェーンの「OD賛歌」で幕を開け、ブリテン、シューベルト、クシチカなどに続いて間宮芳生「合唱のためのコンポジション6番より第2曲」と池辺晋一郎の委嘱作品「東洋民謡集Ⅳ」の初演が行われた。日本の曲では、日本語の不自然さもさほど気になるものではなく、むしろそんなハンデを凌駕するくらい完成された発声に裏打ちされたハーモニーの素晴らしさ、そして90人で歌っているとは信じられないほど深く柔らかなピアニッシモ、ダイナミックレンジの広さが際立っていた。また、後半に展開された曲でもそうであったが、彼らのレパートリーの広さも大きな魅力のひとつである。
休憩のあとの第二部は、“Caprice!”(気まぐれ)と題されたお楽しみコーナーから始まった。客席後方から歌声が聴こえてきたので、振り向くと開け放たれたドアーの向こうのホワイエに集まって歌っていた。指揮者を先頭に歌いながら左右の入り口から会場に入り、客席のあいだを抜けてステージへ、と見る間にそのまま袖から出て行ってしまった。一人取り残された指揮者が困った顔をしていると、また戻ってきて整列となった。ところが、どうも様子が変なのである。全員が両手を後ろに回し、燕尾服の中に何かを隠しているのである。
指揮者がおもむろに指揮を始めると、一斉に白い大きな紙袋を取り出し、指揮に合わせて中に手を入れ、ガサガサさせながら、紙袋を広げ、ねじったり息を吹き込んだりしてじわじわと大きな紙風船に膨らませてゆくのだ。団員は生真面目な顔でやっているところが、いっそうおかしさを誘う。曲の結末はもう誰にでもわかるのだが、どのようにしてフィナーレへ持ってゆくのか、という期待感でワクワクする。そして、いよいよ頂点に達したそのとき、指揮者の一振りで90個の紙袋の大爆発。聴衆の悲鳴も加わった盛大なフィナーレとなった。曲名がついているとは思えないが、合唱と同じく一糸乱れぬパフォーマンス、じつにユニークで風変わりな曲(?)だった。このへんのユーモア感覚も洗練されたものを感じさせ、好感度抜群である。
アイデアの凄さはこれで終わらなかった。団員全員が会場を四角く取り囲むようにステージ前と壁際にずらりと並び、照明が完全に落とされた。目に入るものはわずかに天井の明り取り用の三角窓だけとなり、まったくの暗闇の中に会場が静まり返った。そこへ“Oh, Shenandoah, I long to hear you”懐かしいメロディが流れ始めた。アメリカ民謡「シェナンドー」である。真っ暗な会場に合唱のシャワーが降り注がれた。そのハーモニーの美しさ、男声の包み込むような柔らかさに、しばし我を忘れて聞き入った。暗闇では指揮者など見えない。どこかで合図を出している様子もないので、団員はお互いの「気」を感じながら歌いあう以外にないはずだ。そういえば、はじめに音とりもしなかったように思うが、果たしてそのあたりはどうなっていたのだろう。最初に歌いはじめるパートのところで、小さな音でピッチパイプでも鳴らしたのだろうか。
珍しいところでは、オーロラを声だけで表現したヒルボルイ作曲「ムオアイヨウム」という北欧らしい幻想的な曲があった。オーロラが大きく揺らめきながら輝く壮大な北極の夜空を、歌詞がまったくない声だけで作り出されたさまざまな音を交錯させて描いていた。8分ほどの長い曲にもかかわらず、歌詞がないまま各パートが入り乱れてゆくのだから、ちょっと楽譜から目を離したらどこを歌っているかわからなくなって、おそらく迷子になるにちがいない。指揮者のスント氏は、右手で4拍子を振りながら、ときどき左手を上げていたが、おそらくフレーズの区切りかなにかを示す記号がついた小節があって、そこを指し示していたと思われる。もっともフレーズといえるようなものはないに等しい曲だから、適当に区切りのいいところに記号があるのかもしれない。

ODの魅力とは何だろう。冒頭に紹介したコピーの「90名の圧倒的な迫力」がフォルテッシモを指すとしたら、それは必ずしも当たっていないが、あえて圧倒的な迫力で迫ってきたものは何かといえば、じつはピアニッシモではないだろうか。完成された楽器(身体)と鳴らし方(発声)が紡ぎだすそのアンサンブルの絶妙さは、まさに圧巻であった。機会があればもう一度聴きたい合唱団である。
ODには日本人がひとり加わっていた。その人はトップテナーのヤマダ・マキさん(写真左)で、ふつうに日本語を話す。写真右は、あんさんぶる「ポパイ」の行木
友一さん。ヤマダ氏はストックホルムで育ったとのことだが、日本に住みたいと言っていた。ODのアンサンブルに日本人が加わっているというのも、なにか嬉しい気持ちになるものだ。
 音楽・合唱コーナーTopへ 音楽・合唱コーナーTopへ 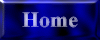 Home Pageへ Home Pageへ
|