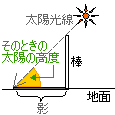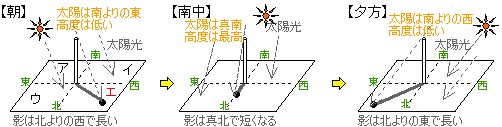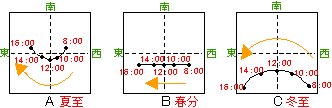|
(1)B (2)午前11時50分 (3)エ (4)ウ |
参考ページ…日の出日の入り南中時刻 太陽の日周運動の1年の変化
こういう透明半球の記録から時刻を求める問題は、透明半球上の太陽が1時間(分)に何cm動くか、または1cm動くのに何時間(分)かかるかが分かってしまえば大丈夫ですね。
(1)
観測地点は北緯36度の地点なので、北半球(日本)にあります。
北半球では、太陽は南を通っていきます。南はBですね。
(2)
透明半球上の太陽がP点(午後1時5分)からQ点(午後3時5分)まで進むのに2時間かかっています。
2時間で10.8cm進んだので、半分の1時間では
10.8(cm)÷2=5.4(cm) よって、1時間で5.4cm進むことになります。
この日の太陽の半球上の通り道全体は54cmなので、太陽が出ている時間を計算すると、
54(cm)÷5.4(cm/時)=10(時間)
この10時間のちょうど真中の時刻が南中時刻となります。日の出から5時間後、または日没より5時間前ですね。
この日の日没は午後4時50分なので、これより5時間前は午前11時50分となります。
(3)
太陽の道すじ(経路)は東西対称になるので、南よりにのぼったら北よりにしずむ、ということはありません。
イ・ウはこれで脱落です。この日(1月15日)の5ヵ月後なら、6月15日で、「もうすぐ夏至」というころです。
夏至の太陽は北よりの東からのぼり、北よりの西にしずみ、南中高度も最大になりますね。
これを表している図はエです。
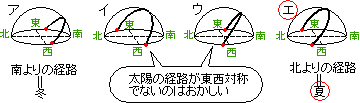
(4)
北緯が高いほど北にある地点、東経が大きいほど東にある地点です。
同じ日で考えると、北緯が高くなるほど、その地点の地平線と太陽光のなす角(太陽の高度)が小さくなりますね。
また同じ日では、東経が大きい地点ほど、先に太陽に一番近い点(南中)まで自転によって移動できます。
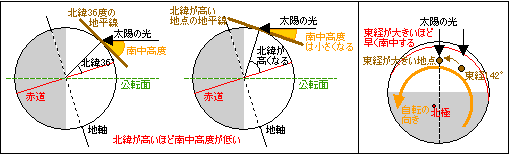
・北緯が高いほど南中高度が低い
・東経が大きい地点ほど南中時刻が早くなる
南中時刻が早いということは、日の出や日の入りも早いということです。
太陽は東のほうからのぼってくるので、東の地点ほど早く太陽に出会えるのは当然ですね。
北緯36度東経140度(東京付近)と比べると、北緯44度東経142度(北海道旭川付近)のほうが東にあり、北にあるので
太陽の南中時刻や日の出の時刻は早くなり、南中高度は低くなります。ウですね。