気温が0℃以下になると氷の粒もできる
↑
さらに上昇するとさらに
気圧が下がり、気温も
下がるので、上に向かって
雲が発達する
↑
気温が露点に達し、
水蒸気がほこりやちりを芯にして凝結し、水滴になる
↑
まわりの気圧が下がり、
空気が膨張し、
気温が下がる
↑
上昇気流によって
空気が上昇する
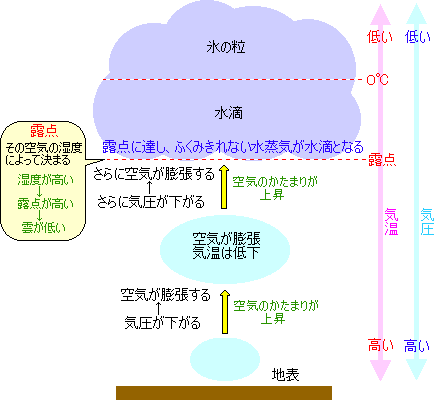
雲のでき方
雲は空気のかたまりが上昇してできます。
|
気温が0℃以下になると氷の粒もできる ↑ さらに上昇するとさらに ↑ 気温が露点に達し、 ↑ まわりの気圧が下がり、 ↑ 上昇気流によって |
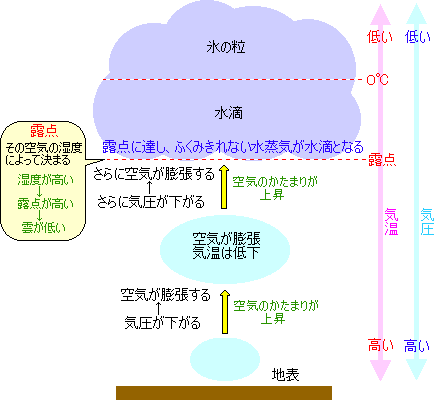 |
上昇気流ができるとき
①空気が山の斜面にぶつかって上昇
(山に風があたっているとき)
冬に日本海側で大雪が降る原因のひとつです。②太陽光によって地面があたためられ、
付近の空気があたたまったとき
あたたかい空気は軽いですね。③あたたかい空気が冷たい空気にぶつかって上昇
寒冷前線ができるときなどです。④あたたかい空気が冷たい空気の上にはい上がるとき
温暖前線ができるときなどです。低気圧の中心は上昇気流が起きていたり、上昇気流の原因はいろいろなものがあります。
雨と雪
雨…氷の粒が落ちてくる途中でとけて水滴になったもの
雪…氷の粒がとけないで地面まで落ちてきたもの
雨や雪の多さは降水量で表します。
降水量…ある時間内の降水の総量(雪の場合はとかして水にしたものの総量)
霧
霧も細かい水滴が空気中に浮かんでいるものです。
地表付近の空気の気温が露点以下になる→ちりやほこりを芯にして水蒸気が凝結し、水滴になります。
フラスコ内で雲をつくる
気圧が下がり、空気が膨張すると、気温が下がり、空気中の水蒸気が凝結して細かい水滴になります。
フラスコ内でそれを確認する実験ですね。※気圧が下がると気温が下がることはそのまま覚えてください。理由は覚えなくていいです(高校化学で習います)。
この実験のあと、ピストンをもどして空気を圧縮するとフラスコのくもりは消えます。
フラスコの中に風船を入れて実験すると、フラスコ内の気圧が下がったとき(ピストンを引いたとき)、風船はふくらみます。
フラスコ内の気圧が下がったことにより、相対的に風船のまわりの気圧より、風船内の気圧のほうが高くなるからですね。
こちらのページの「圧力のつり合い」の項目で確認してください。
top > 気象 > 気圧 > 雲のでき方