石岡マロンズ > 石岡マロンズ技術研究本部 > 電子式セミ/フル切替器 > セミ/フル切替器制御回路について
電子式セミ/フル切替器制御回路について
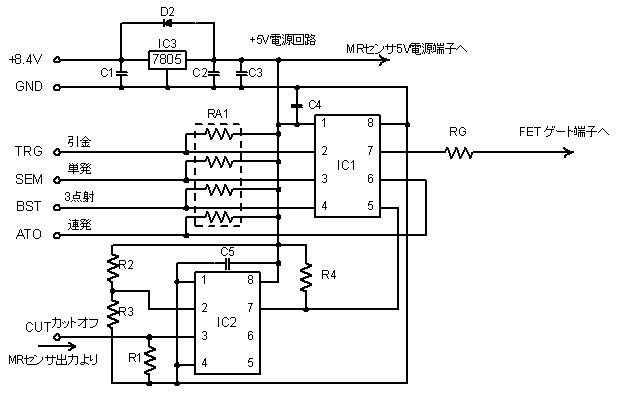 左図が、本システムの制御回路図です。
左図が、本システムの制御回路図です。
上方にある7805の回路が、+5V電源回路で、バッテリーの8.4Vから5Vを得ています。C1とC2は電解コンデンサ、C3は発振防止用のセラミックコンデンサです。またD2は、7805の入出力間に逆電圧がかかった時の保護用として入れておきます。一般の整流ダイオードで十分です。
IC1がPIC12F629で、5VとGND(0V)、それにFETへのオン指令に1ピンずつ使用し、残りの5ピンは全て入力ピンに割り当てています。クロック発振は、PIC内部のRC発振回路を使用しているので、発振回路用にピンを割く必要がありません。磁気センサからの信号を割り込みとしている関係で、後述するNJM311からの出力は、PICの5ピンに繋ぎます。
RA1は、10kΩの集合抵抗で、1チップに4個の抵抗が内蔵されています。PICへのスイッチ入力がオフの時は、PICの入力端子を+5Vに吊り上げるために入れています。集合抵抗を使うことで、配線が楽になるだけでなく、基板の小型化に貢献しています。
IC2はコンパレータIC(NJM311)で、センサからの出力と2.5Vを比較しています。センサが磁石を検知した時だけ、IC2の出力が0Vになります。NJM311はオープンコレクタ出力のため、出力と+5Vの間を1kΩのカーボン抵抗(R4)を介して接続しておきます。比較用の2.5Vは、電源の5Vを抵抗で半々に分圧(R2とR3)して得ていますが、この抵抗には精度が必要なのでカーボン抵抗ではなく、金属被膜抵抗を使います。
また、センサの出力とGNDの間を10kΩの抵抗(R1)で接続しておく必要がありますが、ここにも金属被膜抵抗を使用しておきます。
IC1の7ピンからは、FETのオンオフ指令(点弧指令)が出力されますが、FETのゲート端子との間には、抵抗(RG)を直列に入れておきます。これも金属被膜抵抗を使います。
最後に、C4とC5の役割ですが、これはバイパスコンデンサ(通称パスコン)と呼ばれ、ICの電源端子に流れ込むノイズを除去する役割を持っています。ICを使った電子回路には、ICの近くに必ずパスコンが設けられています。