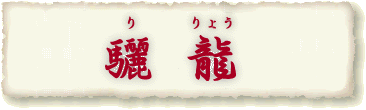
〜 リュウイン篇 〜
漆黒の闇である。
いや。
降り仰げば、東天に細い月が姿を現している。空は青く、地面は月明かりに白く浮かびあがる。
漆黒は、髪である。つややかな長い黒髪が、木陰に潜んでいる。白い細面の中で黒曜の瞳が光った。
甲高い鳥の声が、夜更けの静けさを切り裂く。時折起こる羽ばたきが、闇に潜む小さな息づかいと気配とを覆い隠した。
幾重にも重なった木々の葉が、月の弱い光を遮り、枝の下に不気味な闇を生みだしていた。
その闇の中、小さな炎が飛び交う。
人魂ではない。
なぜなら、沈黙していなかったから。
金属がぶつかる重々しい音が、とうに夜半を過ぎた森に響きわたっていた。
「いたか?」
人魂ならぬ松明の灯りに照らされたのは、軽鎧で武装した老兵だった。
訊ねられたほうも重い鎧を着こんでいたが、まだ年若かった。
「いえ」
「だが、まだ遠くへは行っていまい」
老兵の眼が松明の炎を反射した。
「探せ! 首をとれば、褒美は思いのままだ!」
兵は二人だけではなかった。森に木霊する物騒な音色は、少なくとも数十を数えた。
黒曜の瞳は、瞬きもせずにようすをうかがっていた。息を殺し、茂みの陰に、小柄な身を潜めていた。
兵士たちが探しているのは、彼らだったのかも知れない。
彼ら?
黒曜の双眸のすぐ傍らに、葦毛の馬がたたずんでいた。足は長いが細すぎず、胸や腹はひきしまり、筋肉が美しく盛りあがっていた。頭のてっぺんの小さな三角の耳が、小刻みに動いては辺りの音を拾っていた。
馬は一頭ではなかった。
その隣りに、若い葦毛の馬が並んでいた。体の線がいくぶん細く、落ちつかないようすで、黒い目を油断なくみはっていた。
松明がやがて遠くへ散らばると、白く細長い人間の手が、黒髪の頭に降りてきた。
「行くぞ」
かがんでささやいたほうも黒髪だった。
大人一人に子ども一人。
どちらも長い黒髪を背で束ね、粗末な汚れた木綿のチュニックにズボンを身につけており、これは町でごく当たり前に見られる成人男性の出で立ちであった。
けれども、一方は子どもであり、大人のほうは女である。きりりとした目もと、鋭い眼光は凛々しくあったが、胸や腰の丸みは確かに女のものであった。
かすかな月光のもとでも、眼をこらしてみれば、白い細面の中に、黒い柳眉と形のいいアーモンド型の目がはっきりと認められる。もし、町中で領主の目に留まろうものなら、声の一つや二つはかけられたに違いない。
だが、女が容易に承諾しないであろうことは想像に難くない。双眸の光は強く、その黒曜の瞳は尊ぶことはあっても媚びはしないだろうと思われた。
黒髪黒眼の女と子どもは、流れるような動作で馬上へ上がった。まるで、生まれた時から人馬一体であったかのように、それはあまりに自然であった。
女が馬を進めると、子どももそれに倣った。
闇は、彼女らの味方であったらしい。
黒曜の瞳に映るものは、常人とは異なるのか、何ら迷いなく、確かな足取りで木の密集地帯を抜けた。
一挙に、視界が開けた。
東のあなたには平原が広がり、細い月が道しるべのように浮かんでいた。青みを帯びた光が、道を煌々と照らした。夜空は蒼く冴え渡り、寒さがしんしんと身にしみた。
はあ。と、子どもが手綱を握る手に息を吐きかけた。
しかし、それだけだった。泣き言はもとより、声一つ立てなかった。
まだ一〇歳ほどの年端もいかぬ子どもである。ベソの一つもかくところであろう。
子どもは、まったく子どもらしくなかった。絶えず辺りに目を配り、この非常時にも落ち着き払っていた。腰に佩いた剣は大人の使う重い長剣だったが、いたって不自然さを感じさせなかった。並みの大人以上の手綱さばきで、女に遅れず馬を進める。
空が白みはじめた頃、東に街が見えた。
防風林に囲まれた小さな街。
リュウイン王国の東の果て、隣国パーヴとの国境に近いエスクデールの街である。
女は道をふり返った。
「追っ手は巻いたようだ」
細い月に照らされた蒼い道には、何の人影も、馬の影も見られなかった。
「もう一息で国境を越えられる。そうすれば……」
「伯父上が助けてくれるでしょうか?」
子どもが初めて口を開いた。
年齢にふさわしい甲高い声だった。
女は皮肉っぽい苦笑を、朱い唇の端に浮かべた。
「喜んで災いを呼びこむ者はおるまいよ。だが、この国に留まるよりは安全だろう。さすがに、あの男も隣国には手を出せまいて」
「我らはパーヴで暮らすのですか?」
子どもの表情は淡々としていて、感情が読み取れなかった。
「故郷を離れるのは淋しいか?」
女はニヤと笑った。
子どもは表情を変えない。
「いえ。この先どうするのか知っておきたいのです」
「そうだな」
女は考えこんだ。
「街に入り、人に紛れて暮らそうか。これからは食べ物にも衣類にも事欠くだろう。そなたには不自由をかけるな」
「寝首を掻かれる恐れが減るというもの。むしろ、なんの不自由がありましょうや」
子どもの表情はなおも変わらない。
そういう性質なのかも知れなかった。
「かも知れぬ。だが……」
女は眉をひそめた。
「これで終わったわけではあるまい。そなたの行く末を思うと、人知れず養子に出したほうがよかったのかも知れぬ。弟のように」
「母上の行かれるところ、どこへでも参ります。たとえ地獄の果てまでも」
きっぱりと子どもは言い切った。
女は自嘲的に苦笑した。
「では、風邪をひく前に国境を越えようか」
馬の腹を蹴った。
晩秋の夜明けに、チュニックとズボンという出で立ちはおそまつすぎた。しかし、外套を羽織る暇などなかったのだ。
葦毛の馬は、二頭とも、よく駆けた。
女の腰で長剣が揺れた。
見事な年代物で、鞘には金銀細工が施されていた。特に目を惹くのは大粒のサファイヤとルビーで、赤子のこぶしほどもあった。
剣の握りは、よく使いこまれてピカピカに光っていた。
刀身は鞘に覆われて見えないが、大振りの剣らしい。重く、両手で握る剣なのだろう。握りは、小物ならすっぽり覆ってしまえそうなほど太かったから。
その隣りに下がった短剣もまた、歴史を感じさせる年代物だった。鞘にも握りにも、長剣と同様の細工が施され、また使いこまれていたから。
街の入口にさしかかった。
防風林が道を囲み、月明かりをさえぎる。道だけが、白く芒と浮かび上がっていた。
「戻られよ! 母上!」
突然、子どもが馬首を翻した。
すばやく反転し、来た道を全速で駆け戻る。
ためらわず、女も後に続いた。
びゅう、と矢が風を切った。
一つや二つではない。雨あられのように降りそそぐ。
女は長剣を抜いた。刃がギラギラと光った。手入れの行き届いた、よく使いこまれた刃だが、それ以上の何かを感じさせた。それを殺気や妖気と呼ぶ人もあるかも知れない。
両手で振るうはずの巨大な剣を、女は細い片腕で軽々と振り回した。矢は紙つぶてのようにたわいなく地上に落ちた。
子どももまた、長剣を抜いた。女のものほど巨大ではないが、大人が振るうに足る大振りの剣を、子どもは揚々と振り回した。降り注ぐ矢の雨を、風車のようにはじき飛ばす。
馬はよく駆け、ようやく防風林を抜ける。矢の射程外まで来て、女は後ろをふり返った。追っ手の影は見えなかった。
二人は、歩を緩めなかった。
「モイラの森へ!」
女は叫んだ。
「今宵の敵は、人目をはばからぬ。地獄の底まで追って来ようぞ!」
ごう、と何かが轟いた。
うなりをあげ、矢が降り注いだ。
並みの矢ではなかった。風を切る音は薄暮に轟き、その大きさは音に見合うだけに巨大だった。鋭いやじりが、固い地面に突き刺さる。
弩である。地上に据えつけたバネ仕掛けから、巨大な矢が放たれるのである。その威力も飛距離も、通常の矢の比ではなかった。
二人は剣をかざし、矢をうち払ったが、先ほどまでのようにはいかなかった。重く巨大な矢は、二人の剣士の自由を奪った。そして、乗馬の自由さえも。道には無数の矢が突き立ち、進路を妨げていたのである。
女が一声低くうめいたが、矢の轟音にかき消された。
林立する矢の間隙を縫って、二人は道を外れて野を駆けた。弩の射程から遠く離れ、国境の町エスクデールが夜空の星のように小さな点になってから、子どもは後ろをふり返った。
空の一部が黄色に染まっている。多勢の軍馬が地面の土埃を天に舞い上げ、迫っているのだ。
「母上、手当を」
子どもは乗馬の歩調を緩めて、女の後ろへ回った。女のわき腹には、深々と矢が突き刺さっていた。また、女の乗馬の後ろ足にも、二本の矢が刺さっていた。
女は力をこめて矢を引きぬいた。
「猶予はない。一刻も早くモイラの森へ」
わき腹から血が噴き出した。女は腰ひもを使って止血をしたが、手当と呼ぶにはお粗末すぎた。
子どもは後方を振り返った。
空のけぶりは、いっそう濃さを増したようだ。
「モイラの森まで半日。追いつかれる前に入らねばならぬ」
冷酷にも女は傷ついた馬の腹を容赦なく蹴った。
子どもは黙って後に従った。
モイラの森は、リュウイン王国の都ロックルールから南へ一日くだったところに広がる樹海である。沼地に囲まれ、いたるところに底なし沼が口を開けている。中では磁界が乱れ、方角を失う。
罪人の判定地として名高い。被疑者を森の中で解き放ち、出てこられれば無実、そうでなければ有罪と処す。が、ひとたび足を踏み入れ、ふたたび日の目を見た者は、この世に誰一人としていないのだった。
その話を聞いた時、子どもは形のよい唇にうっすらと笑いを浮かべた。
「合点がいかぬようだな」
女はにやと笑い、訊ねたものだ。
「何を考えておる」
「合点はいっております」
子どもは女の目をまっすぐに見た。
「森を出た者は、一人としてあってはならないのですね。被疑者はすべて有罪でなければならないのでしょう。くだらない国の威信とやらのために」
「なぜ、そう思うのだ。根拠は?」
子どもはつまらなさそうに答えた。
「森から出た者が一人もおらぬなどとはウソです。おおかた、道案内の者でもおるのでしょう。そうでなくて、どうして罪人を森の中に連れていけましょう。では、どうしてウソをつくのか。得をするのは誰か。考えれば、おのずとわかります」
女はうなずいたものだ。
「では、その道案内の者とやらを探そう」
子どもは不審げに女を見た。女は笑った。
「話というものは、真意をくみ取るだけではなく、利用しなければな」
あれから一年。
よもや、役立つ日が来るとは想像だにしなかった。
モイラの森の奥深く、かつて道案内の者から教えられた道を進むと、小さな広場に行き当たった。
女は崩れるように、馬から降りた。粗末な衣服は大量の血液で変色し、それでもまだ吸いきれずに雫をしたたらせていた。
子どもが駆け寄り、布を当てたが、みるみるうちに真紅に染まった。
女の乗馬が膝を折り、横ざまに倒れた。矢傷は深く、馬はあきらめたように目を閉じた。子どもの乗っていた若い葦毛の馬が、鼻面をこすりつけた。
「追っ手は血の跡をつけてくるだろう」
女は肩で息をついた。わずかに身動きするたび、赤いものがどっと噴きだした。
「母上、話してはなりません」
子どもは眉を寄せ、真紅の布を未練がましくあてていた。
「道を踏み外せば底なし沼ゆえ、追っ手の勢いも多少はそがれようが、じきに追いつめられよう。ここより先は、そなた一人で行け」
子どもはかぶりを振った。
「どこまでもお供いたします。今、傷口を縫い合わせましょう」
子どもは馬の鞍にくくりつけた小袋を取りに行きかけた。
女が、ぐいと、子どもの腕を引いた。
「ムダだ」
子どもはハッと女の顔を見た。
血の気の失せた顔には死相が現れていた。両肩を死神に押さえられながらも、強靱な意志がなお、女の魂をこの世に引き留めているのだった。
「母の大小をとれ」
子どもの息が止まった。胸を突かれたように表情がこわばった。
どこに行こうとも、愛剣は手放せない。死出の旅に向かわぬ限り。
形見を残していこうというのか。
「誓って、あの男めを地獄へ送ってご覧に入れます」
子どもは女の手を強く握りしめた。
女はかすかに首を振った。
「母の仇を討とうとしてはならぬ」
子どもの眉根が深い皺を刻んだ。
女は深く息を吸いこみ、くり返した。
「母の仇を討ってはならぬ。そなた自身の生を生きよ。よいな?」
子どもは答えなかった。ひき結んだ唇から血がにじんだ。
「リュウカ!」
瀕死の目が大きく見開き、死神をも退けるような一喝が轟いた。
子どもの長い睫が心の惑いを表すように震えている。ガタガタと奥歯が鳴った。露わになった細腕にはたちまち鳥肌が立った。全身が、応諾を拒んでいた。
女の手が、子どもの手を握りしめた。普段の力強さはなかった。死神が徐々に魂を蝕んでいる。時間はもう残されていない。
子どもは臍下に力を込めた。持てる精神力をすべて奮い、己の感情を水面下にねじこんだ。
「はい」
喉に重い塊がつかえたかのように、子どもは震える声で弱々しく諾した。
女は満足げに唇の端をあげ、子どもを愛おしそうに見やった。
「では、母の馬を楽にしてやれ。苦しみが長引いてはかわいそうだ」
子どもがうなずくのを、女が見ることはなかった。急速に黒い瞳の光は失われ、子どもの両手の中でその手は重く沈んだ。ついに死神は、高貴な生命を手中に収めたのだ。
子どもは嘆かなかった。
すくと立ち上がり、女の乗馬の傍らに寄った。すでに馬はこときれており、子どもの乗馬がいつまでも鼻先をすりつけていた。
子どもは子ども離れした力で、馬の亡骸を引きずった。大人の背丈の倍ほども動かすと、そこは底なし沼だった。馬は沼に沈んだ。
引き返し、子どもは女の遺骸から大小の剣を抜き取った。そして、手際よく、馬と同様の処置を施した。軽い分だけ、事はあっさりと済んだ。
時間を浪費したりはしなかった。迷わず子どもは乗馬に飛び乗り、森から姿を消した。
生き延びるために。
![]()