貧乏人のラリー車制作方法
 Poor Man's Rally Car Making
Poor Man's Rally Car Making
このページは安くラリー車を作る為の情報です。学生時代それに結婚してからラリーを続けるのは経済的にとてもしんどいと思います。そこで皆さんでアイデアを持ち寄っていかに経済的に競技車を作り、維持するかの情報ページにしたいと思います。
ついでといってはなんですが、一見めんどうなユーザー車検の方法もご紹介しましょう。
(他にもこうするといいよといったご意見大歓迎です。)
安くあげるラリー車づくりの原則
- 自分でできることは自分でする。継続検査(車検)や整備も。。。
- この装備が無ければ勝てないといった概念を捨てる。(例えばLSD)
- 車でも部品でもできるだけ安く購入する。
1.Do It Yor Self! Part 1
ラリー車を作るのにはガード、足周り、安全装備などいろいろ必要です。 普通はラリーショップにやってもるう人が殆どではないでしょうか? ラリーショップや整備工場は自分でできないところをやってくれるところと理解し、他はパーツだけ購入するのが車への理解を深める上でもいいのではないでしょうか。自分で分解したことのあるところは、部品さえあれば壊れても次から自分で直せるからです。
まずは、工具が必要です。ラリーストなら少々の工具はもっているでしょうが、初心者の方の為にそろえる工具の順番を列挙しますので、必要なものからそろえて下さい。
- ジャッキ(フロアージャッキかシザースジャッキ)パンタジャッキでやっているとイヤになってきますから。 2980〜10000円
- クロスレンチまたは、電動インパクトレンチ 980円〜10000円
- ソケットレンチ、メガネ、スパナ、ドライバー(持っていない人はセットで買いましょう)
- ドリルと刃(電源の取れない人はドリル&ドライバーも便利) 3980〜8000円
- 六角レンチ(アンダーガードの脱着に必要) 500〜8000円
- スプリングコンプレッサー 10000円〜
- リジットラック(通称うま) 最低2ケ 5000円/2ケ
- バイスグリップ(ネジで口の大きさを変えてロックできるプライヤー状のもの) これはアンダーガードのネジがはずれない時や貫通穴にボルト&ナットで物を固定する際にとっても便利 980円〜
- トルクレンチ 10000円〜 高価なので必要な人だけ買いましょう。
- フレアーナットレンチ 980円〜 ブレーキフルードの交換時に必要(必須では無い)
- オートメカニック別冊や自動車メーカーの発行している整備マニュアル (初心者のうちは頼りになります。教えてもらえる人がいなくても安心)
一番、多いのは消耗品であるショックアブソーバーとブレーキパッドの交換でしょうか。フロントは、スプリングコンプレッサーが必要ですが、リアは不要な車もあります。スプリングコンプレッサーは購入したとしても1万円程度です。油さえ塗っておけば一生使えますから購入されてはいかがでしょう。ストラットアッパーマウントの中心にあるセルフロックナットがはずれないときには電動インパクトではずすかガソリンスタンドではずしてもらいます。ブレーキパッドも恐れることはありません。キャリパーを止めてあるボルトを1本または2本はずしてパッドをはずしてピストンを押し込みまたパッドをはめこみボルトを締める。これだけです。 ブレーキやサスペンションは片側づつ交換しましょう。もし組み込む順番が分からなくなっても反対側にサンプルがあるのでそれをみればいいのです。一度やってみるとなんや簡単やんか。ということになります。
<バンパーの補強>
私がギャランVR−4でやっていたバンパー補強方法をお教えしましょう。バンパーの下部はダートを走るとすぐにもげてしまいます。そこで、バンパーの裏面に発泡ウレタンスプレーを吹き付けます。これは塗布すると発泡して10〜20倍に膨れてスポンジ状になります。おまけに表面にはスムーズな層が形成されるので、吸湿もそれほどありません。これは効果絶大で少々下部をこすってもバンパーそのものは割れてきますが、もげたりはしません。 また、これをタンクガードを組むときに少量全面にのばして塗布しておけばタンクのへこみも無く、石も入りません。 ただし、熱に弱いのでオイルパンのように熱くなる部分には使わないほうがいいでしょう。また、失敗談ですが手に付着すると2日は取れません。ビニール手袋をして作業しましょう。
<バケットシートの自作>チーム・ファーストプライズの米谷展生さんより頂いた情報です。
バケットシートが買えない人は、自分で作りましょう。
ノーマルシートの表面生地を止めている針金をニッパーで切ってしまうと簡単に剥がれます。
すると、中にスポンジと鉄板のリーンフォースが入っています。
次に自分の体格に合わせてφ8mm位の鉄棒を曲げて腰と太もものサイドサポートを作りリーンフォースに溶接します。溶接は整備屋さんか板金屋さんでやってもらうと良いでしょう。
また、ノーマルのスポンジでは柔らか過ぎると言う人はホームセンターで硬めのスポンジがあります。それか、お風呂マットでも良いでしょう。このスポンジを適当に切って形を整えます。
これで、オリジナルのバケットシートの完成です。
あとは、表面の生地を被せるだけですが、分解するときに針金を切っているので、組立の時は針金の代わりに配線などを止めるタイラップを使うと良いでしょう。
<舗装用足周りのセッティング>チーム・ファーストプライズの米谷展生さんより頂いた情報です。
今年から車高を4cmまで下げて良いことになりましたよね。
大体のラリー車はスプリングを交換してダート用に車高を上げているので舗装用にもう1セットスプリングを買わないといけません。
こんな時はノーマルスプリングをサンダーでカットすると良いでしょう。ばねレートはコイルの巻数(上下1巻づつは数えない)に反比例するのでカットするとその分ばねレートが上がるので丁度都合が良いですね。一度にたくさん切らずに1/4巻づつ切って実際走行テストしながらセッティングすると結構いけますよ。
2.Do It Yor Self! Part 2 車検にチャレンジ
ユーザー車検(ここで言うユーザー車検は自分でライン検査を通すことで代行屋に依頼することではありません)はかなりの節約効果があります。簡単ですから是非皆さんもトライして見ましょう。最初は不安なものですが、ダメならディーラーに出せばいいくらいの軽いノリで行きましょう。
ちょうど私も先日、車検を受けてきました。デジタルカメラで写真も撮ってきましたので、順を追って車検の取り方を説明しましょう。
1.点検と車検の予約
まず自分で、整備点検記録簿に従って点検を行います。(’95.7月から点検項目が大幅に減っています。本でチェックしましょう。)チェックリストは、陸運支局(車検場)で継続検査書類一式頂戴と言って買うと1枚ついてきます。もちろん旧書式でやってもOK。大部分の項目は普段乗っている時にちゃんと走ればOKにしていいでしょう。ただしブレーキパッドとタイヤの残り溝くらいはちゃんとチェックしましょう。
予約は各陸運に問い合わせましょう。大阪の場合ですとユーザー車検専用の24時間自動受付システムがあります。プッシュ音の出る電話機から06−613−1300に電話して指示に従って入力すれば予約できます。
2.当日の準備
朝下回りをコイン洗車場で洗車していきます。(必須ではありませんがマナーです。)自動車税支払い時の領収書と車検証、整備点検記録簿を忘れずに持っていきます。
3.陸運支局での手続き
まず、書類を売っている建物で継続検査の書類一式を買います。自賠責に加入し、重量税の印紙を購入して所定の用紙に張り付けます。また、OCRシートに鉛筆で車種などを数字で記入。
次に大阪の場合ですとユーザー車検専用のプレハブ小屋へ行って予約確認と受付印を押してもらいます。これがすめばいよいよライン検査ですが、その前に歩いて見学用ラインを見学して手順を見ておきましょう。
4.ライン検査
いよいよライン検査ラインにチャレンジです。ボンネットのロックを開けて最後列に並びましょう。
 入口はこんな感じです。女性も一人で来ていましたヨ。入り口のところの係官が外観、ライト、ウィンカー、ワイパー、ハザード、ブレーキランプなどのラリー車検みたいな感じの検査を行います。指示される通りにやればOK。忘れやすいのが発煙筒の期限です。もし切れていたら赤色灯を見せればOKです。霧灯も取り付けてあるなら法規に合致していることが必要になります。(光量検査はありません。)車両の外側から400mm以内、地上から800mm以下250mm以上の高さで、全長から±30mm以内であることが必要です。個数は2個のこと。
入口はこんな感じです。女性も一人で来ていましたヨ。入り口のところの係官が外観、ライト、ウィンカー、ワイパー、ハザード、ブレーキランプなどのラリー車検みたいな感じの検査を行います。指示される通りにやればOK。忘れやすいのが発煙筒の期限です。もし切れていたら赤色灯を見せればOKです。霧灯も取り付けてあるなら法規に合致していることが必要になります。(光量検査はありません。)車両の外側から400mm以内、地上から800mm以下250mm以上の高さで、全長から±30mm以内であることが必要です。個数は2個のこと。
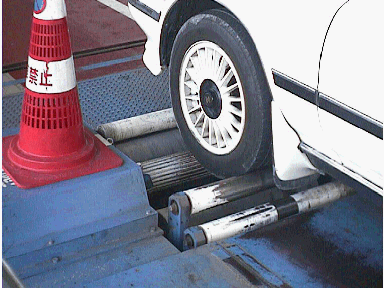

次にサイドスリップ検査がありますが、通過すればOK。その次がブレーキとスピードメーターのチェックです。電光掲示板の指示に従って操作すれば簡単です。
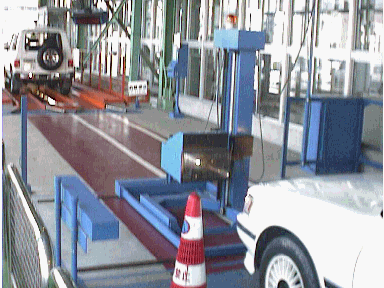
ライトテストはこんな測定器が横から自動的に出てきます。4灯式の車はハイビーム側(インナービーム)にダンボールでふたをしておきます。すんだら忘れずに機械に差し込んで検査票に記録します。
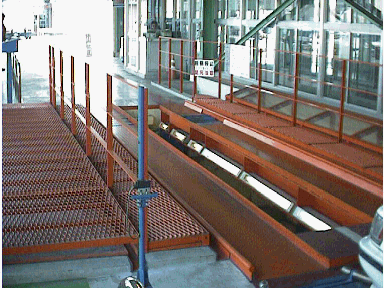
ここでは、下から検査官がボルト類の緩みがないかをチェックします。それがすむと振動テストがありますからハンドルから手をはなして待ちます。OKになると電光表示に進めの表示が出ます。
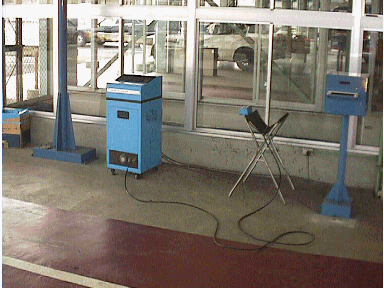
次が排ガス検査です。終わるまでじっと待ちます。このラインはユーザー車検用ラインでしたので係官が差し込んでくれました。最後に検査票に記録して、係官に合格印を押してもらいます。これで無事終了です。

最後に事務所に行って検査票と旧車検証、OCR用紙、重量税用紙を提出して数分で車検証とステッカーがもらえます。
これで無事、2年間の車検が取れたわけです。行ってみると多分こんな簡単でいいの?と思ってしまうのではないでしょうか? 車検は現時点でOKかどうかを判定しているだけですから競技車ともなれば消耗も激しいですからくれぐれもメンテナンスを怠らないようにしましょう。

皆さんからの貧乏人の苦労話、情報をお待ちしております。是非アイデアを共有しましょう。

 ホームページに戻る
ホームページに戻る
 入口はこんな感じです。女性も一人で来ていましたヨ。入り口のところの係官が外観、ライト、ウィンカー、ワイパー、ハザード、ブレーキランプなどのラリー車検みたいな感じの検査を行います。指示される通りにやればOK。忘れやすいのが発煙筒の期限です。もし切れていたら赤色灯を見せればOKです。霧灯も取り付けてあるなら法規に合致していることが必要になります。(光量検査はありません。)車両の外側から400mm以内、地上から800mm以下250mm以上の高さで、全長から±30mm以内であることが必要です。個数は2個のこと。
入口はこんな感じです。女性も一人で来ていましたヨ。入り口のところの係官が外観、ライト、ウィンカー、ワイパー、ハザード、ブレーキランプなどのラリー車検みたいな感じの検査を行います。指示される通りにやればOK。忘れやすいのが発煙筒の期限です。もし切れていたら赤色灯を見せればOKです。霧灯も取り付けてあるなら法規に合致していることが必要になります。(光量検査はありません。)車両の外側から400mm以内、地上から800mm以下250mm以上の高さで、全長から±30mm以内であることが必要です。個数は2個のこと。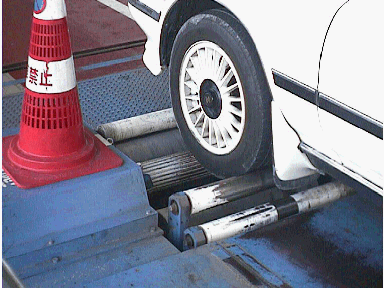

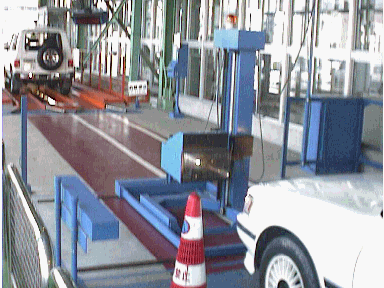
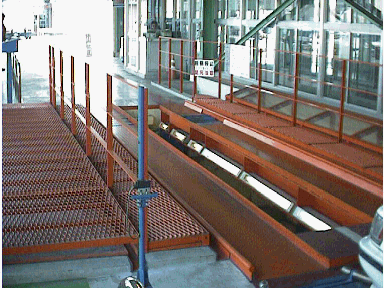
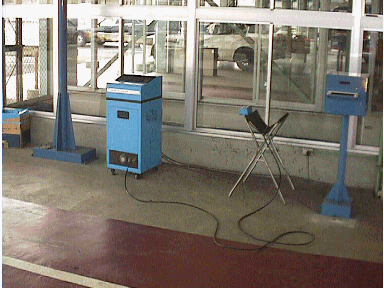



 ホームページに戻る
ホームページに戻る