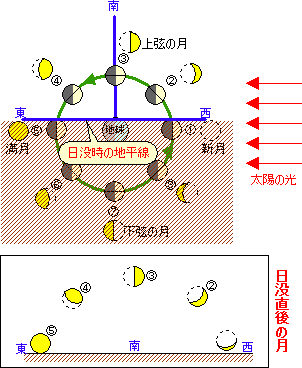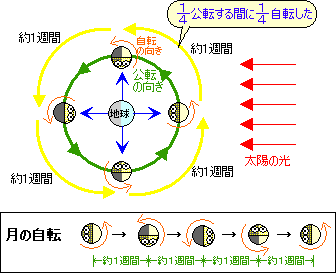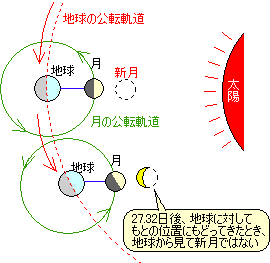月は地球のまわりを約4週間で1周公転します。
月はみずから光らず、太陽の光を反射しているので、「光のあたっている部分をどの向きから見るか」で見える形が決まります。
月の公転によって、月の位置が変わると地球から見た月の明るい部分の見え方が変わります。
満ちる…明るい部分がふえていく 欠ける…明るい部分が減っていく
|
月の満ち欠けの原因 ・月は太陽の光を反射している |
①から順にボタンを押して確認してください。
観測者の位置と地球の自転の向きから、その形の月のおよその南中時刻も想像してみてください。
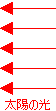 |
|||
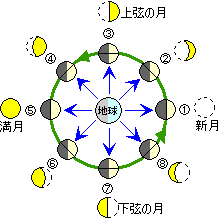
| |||
月は約4週間でこのような形に変化していきます。新月からは右から満ちて、満月になるとまた右から欠けていきます。
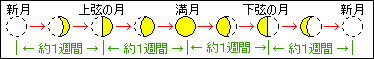 ※南中時の向き
※南中時の向き
|
月は右から満ち欠けしていく |
月の呼び方(参考)
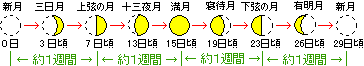
いっぱんにいう「三日月」は、新月から3日目くらいの月の見かけの形をいいます。
覚え方…凸面が右(みぎ)を向いていたら、(み)がつくから、三日月(北半球)
凸面が左を向いているときは「逆三日月」とも呼ばれます。
上弦の月について
|
月も地球の自転によって東から西へ日周運動をします。 西にしずむときの半月を「弓」の形に見たてて、 | 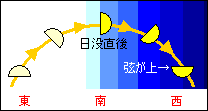 |