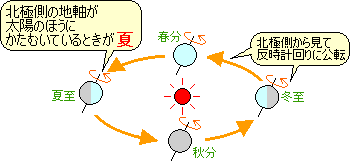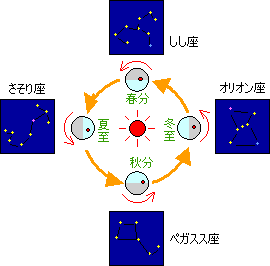太陽や星座はその位置を変えているわけではありませんが、地球から見ると動いて見えます。
これは地球の自転や公転による見かけの運動でしたね。
まず、観測者の1日の位置の移り変わりを理解しましょう。これはとても重要です。
地球が太陽に対してどの向きになっていても、
地球の太陽側が昼、太陽の反対側が夜です。
1日の観測者の位置は4か所おさえましょう。
迷うのは「明け方」と「夕方」だと思いますが、地球が太陽に対してどの向きになっていても、
「太陽がどちらにあるか」
「地球の自転の向き」
から判断しましょう。
| 正午…太陽にいちばん近づいた場所 太陽の観測では重要な位置です。 星は太陽の光で見えません。 |
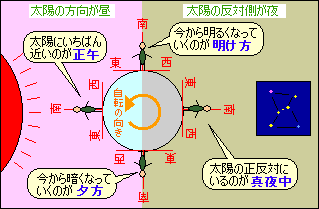
※これは北極星側からおもに北半球を見ています。 |
| 夕方…自転によって太陽から 遠ざかる場所 |
|
| 真夜中…太陽からいちばん遠い場所 星座の観測では重要な位置です。 太陽は地球の裏側なので見えません。 |
|
| 明け方…自転によって太陽に 近づいていく場所 |
特別な指定がなければ、正午を午後0時、夕方を午後6時、真夜中を午前0時、明け方を午前6時と考えて問題を解きましょう。
日本(北半球)での観測者にとっての方角は
・観測者は南を向いて立っている
・観測者にとって右が西で左が東(天体は左から右へ日周運動をする)
・観測者は地球の中心を下にして立っている
ことを理解していれば大丈夫です。