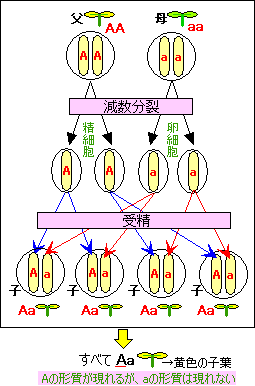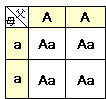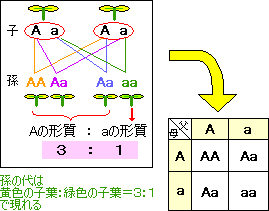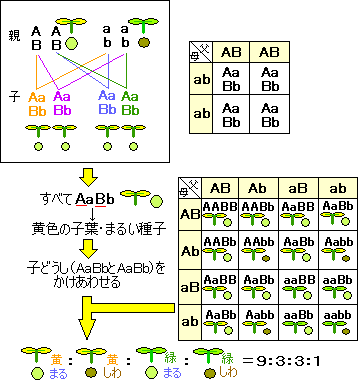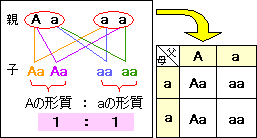遺伝には規則性があります。子の代には出なかった親の形質が孫の代で現れることもあり、その比はほぼ一定しています。
メンデルの法則
メンデルはエンドウを使って遺伝の研究をしたオーストリアの教会の司祭です。
のちにメンデルの発見した法則は3つの法則にまとめられました。
これらは遺伝子が2個対になってはたらくことから導くことができます。
ことばだけではわかりにくいですね。具体的な例を見ながら、それぞれがどんな法則かつかんでいきましょう。
優性の法則 子に関する遺伝の規則性
例として代々黄色の子葉のエンドウと代々緑色の子葉のエンドウをかけあわせます。
緑色の子葉のエンドウのめしべに黄色の子葉のエンドウの花粉を受粉させたとします。
※毎年栽培しても形質の変わらない純粋なものを純系といいます。
2つの遺伝子が対になってはじめてひとつの形質を現します。
|
A…黄色の子葉を現す遺伝子
a…緑色の子葉を表す遺伝子
代々黄色の子葉のエンドウがもつ遺伝子は
AA(純系)
代々緑色の子葉のエンドウがもつ遺伝子は
aa(純系)
対になっていた親の遺伝子は、精細胞・卵細胞
がつくられるときに半数になります。
受精によって、遺伝子は再び組み合わされ、
対になります。
子の遺伝子の組み合わせを考えるとき、
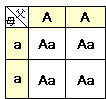
↑このように表で調べるとすっきりしますね。
|
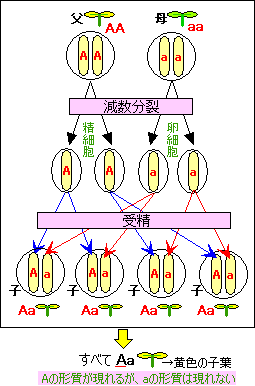 |
できた子はすべてAaの遺伝子をもっていますが、Aの形質(黄色の子葉)しか現れません。
このときの子に現れた形質(A=黄色)を優性の形質、かくれてしまった形質(a=緑色)を劣性の形質といいます。
※優性・劣性は「すぐれている」「おとっている」という意味ではありません。
分離の法則 孫に関する遺伝の規則性
例として先ほどのエンドウの子(Aa)どうしのかけあわせを考えます。
|
A…黄色の子葉を現す遺伝子
a…緑色の子葉を表す遺伝子
親はすべてAa(雑種)で黄色の子葉です。
Aaどうしをかけあわせると、
AA、Aa、aaの3種類のエンドウができます。
AA・Aa…Aの形質が現れる(黄色の子葉)
aa …aの形質が現れる(緑色の子葉)
よって、黄色:緑色=3:1の割合で
祖父母の形質が分離して現れます。
|
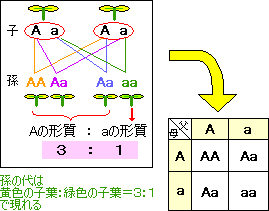 |
独立の法則
2種類の形質を例にしていきます。
大文字の遺伝子が優性だと考えてください。
黄色の子葉でまるい種子のエンドウの花粉を、緑色の子葉でしわの種子のめしべに受粉させたとします。
| 形質の種類 |
形質を現す遺伝子 |
| 子葉の色 |
A…黄色の子葉を現す遺伝子
a…緑色の子葉を現す遺伝子
|
| 種子の形 |
B…まるい種子を現す遺伝子
b…しわのある種子を現す遺伝子
|
|
2つの観点から見ていきますが、
考え方は同じです。
代々黄色の子葉でまるい種子
のエンドウがもつ遺伝子は
AAとBB
代々緑色の子葉でしわの種子
のエンドウがもつ遺伝子は
aaとbb
できた子はすべてAaとBbの
遺伝子をもつので、
Aの形質(黄色の子葉)と
Bの形質(まるい種子)
しか現れません。
その子(Aa・Bb)どうしを
かけあわせて孫をつくります。
16通りの組み合わせが
できますね。
|
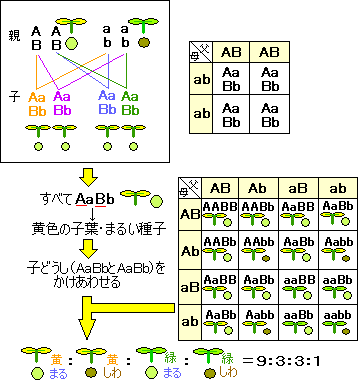 |
ひとつずつ現れる形質をまとめると、(黄・まる):(黄・しわ):(緑・まる):(緑:しわ)=9:3:3:1の割合になります。
ここで、「子葉の色」だけの形質に注目して数えてみると、黄色:緑=12:4=3:1です。
また、「種子の形」だけの形質に注目して数えてみると、まる:しわ=12:4=3:1です。
それぞれの形質は、結局孫の代で3:1の割合で現れているので、2種類の形質はそれぞれ独立して遺伝したことになります。
遺伝の規則性
親が純系以外の例としてAaという対の遺伝子をもつ個体とaaという対の遺伝子をもつ個体のかけあわせを考えてみましょう。
(Aは優性の形質を現す遺伝子、aは劣性の形質を現す遺伝子とします)
|
この場合の組み合わせを考えると、
Aaとaaの遺伝子をもつ子が
それぞれ同じ数だけできます。
形質が現れる比は1:1になりますね。
子の半数はAの形質、
残りの半数はaの形質
をもっていると予測できます。
|
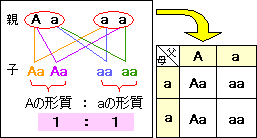 |
top
> 生物のつながり > 生物のふえ方と進化 > 遺伝の規則性(参考)