|
地層のでき方…川に運ばれた堆積物がおもに海で下から順につもってできる
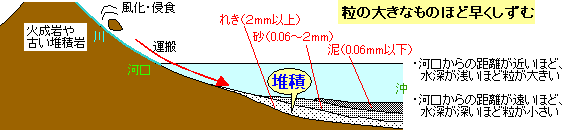
堆積岩…堆積物がつもって重みによる圧力で押し固められた岩石
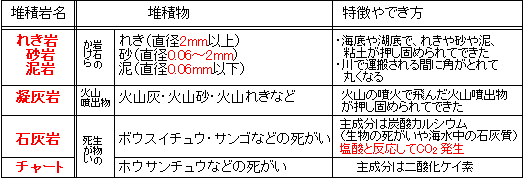
※火成岩(マグマが冷えて固まった岩石)は粒が角ぱっている
地層中の化石…示相化石と示準化石
示相化石…その地層が堆積した当時の環境を示す化石
アサリ・カキ→浅い海 サンゴ→暖かくきれいな浅い海底
シジミ→河口or湖(淡水) シュロ・ソテツ→暖かい気候 マンモス→寒い気候
示準化石…その地層が堆積した地質年代を示す化石
サンヨウチュウ・フズリナ→古生代 アンモナイト・シソチョウ→中生代
ビカリア・メタセコイア→新生代(第三紀) マンモス・ナウマンゾウ→新生代(第四紀)
地層の読みとり…露頭の地層を観察して過去に何が起こったかを読みとる
露頭…がけや道路の脇など、地層の断面が地表に露出しているところ
かぎ層…広い範囲に分布した、特徴のある岩石の層
(凝灰岩層、化石をふくんだ層、チャートの層など)
・ふつう、下にあるほど古い層(下から順に見ていく)
・下から堆積物の粒が細かくなっていく→海が深くなっていったことがわかる
・下から堆積物の粒が大きくなっていく→海が浅くなっていったことがわかる
・示準化石で堆積当時の年代を、示相化石で堆積当時の環境を知る
・凝灰岩の層→堆積当時、近くで火山活動があったことがわかる
|