|
オシロスコープやコンピュータなどを使うと、 波形の見方をつかみましょう。 |
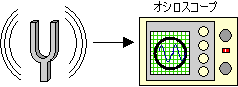 |
|
振幅…もっとも大きく振動した幅
振動数…1秒間に振動する回数 ※グラフの縦軸は振幅、横軸は時間を |
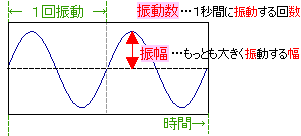 |
※ふつうの音の波形はこのようなきれいなカーブを描いていません。音叉(おんさ)で出した音はほぼこの形になります。
身のまわりにはさまざまな音があります。「大きさ」・「高さ」・「音色」で音は決定され、これを「音の三要素」といいます。
ここではその中の音の大きさや高さについておさえましょう。
音の波形
オシロスコープやコンピュータなどを使うと、
音の波形を目で見ることができます。波形の見方をつかみましょう。
振幅…もっとも大きく振動した幅 振動数…1秒間に振動する回数
単位…Hz(ヘルツ)※グラフの縦軸は振幅、横軸は時間を
表しています。※ふつうの音の波形はこのようなきれいなカーブを描いていません。音叉(おんさ)で出した音はほぼこの形になります。
「弦のようす」「音の大きさ」「音の高さ」と振幅・振動数の関係
モノコードで弦のようすを変えながら音の大きさや高さを調べ、波形との関係をつかみます。
もとの音の波形(上のほうの図)と比べながらラジオボタンをクリックしていってください。
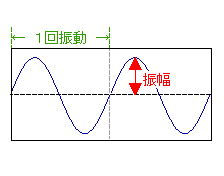
音の大小
振幅で決定弦を強くはじく→振幅が大きい→音が大きい
弦を弱くはじく→振幅が小さい→音が小さい音の高低
振動数で決定弦を強く張る・弦が短い・弦が細い→振動数が多い→音が高い
弦を弱く張る・弦が長い・弦が太い→振動数が少ない→音が低い波形の振幅の大きさを見れば音の大きさが、波の数(振動数に比例)を見れば音の高さがどうなったのかわかりますね。
![]()
モノコードで弦の状態をいろいろ変えてみて、6つの波形を観察した。
アは弦におもりを1個つり下げて弦をふつうにはじいたときである。
top > 身のまわりの現象 > 音 > 音の性質