気体の性質によって集め方が違います。3種類覚えましょう。
| 水上置換 | 上方置換 | 下方置換 |
| 水に溶けにくい気体 | 水に溶けやすい気体 | |
| 空気より軽い気体 | 空気より重い気体 | |
| 酸素・水素など 二酸化炭素も可
|
アンモニアなど
|
塩素・二酸化硫黄など 二酸化炭素も可
|
酸素や二酸化炭素が身近にあるといっても、空気に混ざってしまっています。
水素はあまりに軽いので、地球上にとどまれず、おもに宇宙空間に存在しています。
純粋な気体を得るにはどうしたらいいのか、おもな気体の発生方法と集め方を覚えましょう。
気体の集め方
気体の性質によって集め方が違います。3種類覚えましょう。
水上置換 上方置換 下方置換 水に溶けにくい気体 水に溶けやすい気体 空気より軽い気体 空気より重い気体 酸素・水素など
二酸化炭素も可
アンモニアなど
塩素・二酸化硫黄など
二酸化炭素も可
代表的な気体の発生方法
薬品を使って化学変化で気体を得る方法を覚えましょう。
刺激臭のある気体を扱うときは、換気をよくして、直接吸い込まないようにしましょう。
気体の発生装置
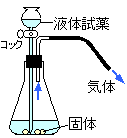
水素・酸素・二酸化炭素などを発生させるときのように、固体と液体の試薬を混ぜて気体をつくる場合、左図のような装置をよく使いますね。 ・三角フラスコに固体の試薬を入れる
・2穴のゴム栓でふたをする
・1穴を通したガラス管から液体試薬を少しずつ滴下して反応させる
・発生した気体を、もう1穴を通したガラス管から採集する2本のガラス管の長さが違う理由を考えてみましょう。
液体を滴下するガラス管は長く、気体を通すガラス管は短い そのまま気体を発生させると、どうなってしまうのか想像してみるといいです。
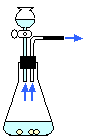
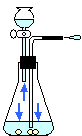
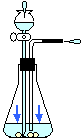
発生した気体が
両方のガラス管から
出てきてしまう気体が発生し、フラスコ内の気圧があがり、液面を押すので、気体採集用のガラス管から液がもれ出し、液体滴下用のガラス管から気体が出てくる 気体が発生し、フラスコ内の気圧があがり、液面を押すので、両方のガラス管から液がもれ出す もし、液体滴下用のガラス管が短いと、高い位置から液体を滴下することになります。
この場合、まわりに試薬が飛び散り、効率よく反応させることができないということも考えられますね。
フラスコの底のほうに液体滴下用のガラス管の先がくるようにしましょう。
気体発生用のガラス管につないだゴム管が折れたりした場合のために、実験中はコックを開けておきます。
top > 身のまわりの物質 > 気体 > 気体の発生方法