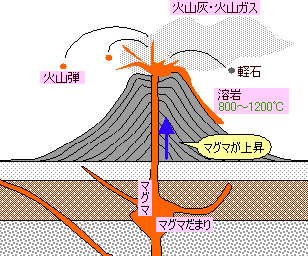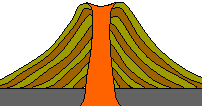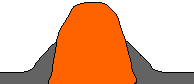火山と火成岩
日本は「火山国」と言われるほど火山の多い国です。
全国の温泉を楽しめるのも火山があるからこそ、とはいえ、ふき出す噴出物や、噴火による地殻変動などで、いろいろな被害も出ています。
ここでは火山について理解し、火山がつくる岩石の種類や特徴をおさえていきます。
マグマと溶岩
火山や火成岩を理解するために、まずマグマのことを知りましょう。
|
マグマ…地下にある高温のどろどろにとけた物質
(火山ガスをふくむとけた岩石)
|
※マグマのでき方が気になる方は、「プレートテクトニクス」の項目を参考にしてください。
マグマが地下深くでできて、上昇し、一度マグマだまりにたまります。
さらにマグマが上昇し、地表が近づくにつれてまわりの圧力が小さくなり、マグマにふくまれていた火山ガスが急に膨張します。
そしてマグマ内の圧力が大きくなり、噴火口めざして飛び出します。これが噴火です。
|
溶岩…マグマが地表に流れ出たもの
どろどろのものも、冷えて固まったものも「溶岩」といいます。
|
マグマと溶岩は同じものですね。
「マグマ」は地表に出る前の名前で、噴火口から地表に出たとたん「溶岩」という名前に変わります。
参考:マグマはねばりけによって「玄武岩質」「流紋岩質」「安山岩質」があります。流紋岩質と安山岩質はいっしょに扱われることもあります。
火山噴出物
火山噴出物は、以下の5つのものを覚えておきましょう。
|
火山ガス
主成分は水蒸気で、
二酸化炭素などもふくまれる
溶岩
マグマが地表に流れ出たもの
火山灰
マグマが粉々になった
灰のようなもの
火山弾
固まりきっていないマグマが
ちぎれ飛んだもの
軽石
溶岩が固まってできた
穴の多いもの
|
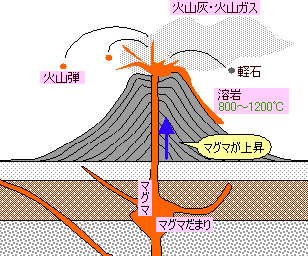 |
******参考******
・火山噴出物は火山ガス・溶岩・火山砕屑物に分類されます。
火山砕屑物は大きさによって、火山灰・火山砂・火山れき・火山岩塊などがあり、穴の多いものを軽石といいます。
・噴煙となった火山灰や火山ガスなどが重いと、山の斜面を勢いよく流れてくるときがあります。
これは「火砕流」といって大変危険です。溶岩が流れてきたものは「溶岩流」と呼びます。
マグマのねばりけと火山の形
火山は、噴火のときに流れた溶岩や火山灰が積み重なってできていきます。
だから、マグマのねばりけは火山の形を決める大きな要因となります。
次の3種類について、マグマのねばりけが、火山の形や噴火のようすにどう関係しているかつかんでください。
| マグマの粘性 |
分類(参考) |
火山の形 |
特徴と例 |
噴火のようす |
ねばりけが
弱い |
楯状火山 |
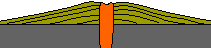
|
溶岩が流れやすいので
うすく広がり、平らな形をしている
マウナロア山・キラウェア山など
|
おだやかに
溶岩を流しだす |
ねばりけは
中間 |
成層火山
|
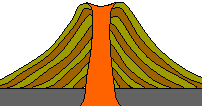
|
火山灰などと溶岩が
交互に噴出して、
円錐形をしている
溶岩ドームをともなうものもある
富士山・浅間山・桜島など
|
↑
中間
↓ |
ねばりけが
強い |
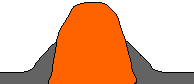
|
溶岩が流れにくいために
おわんをふせたような形になる
雲仙普賢岳・昭和新山など
|
はげしい爆発をともなう噴火 |
爆発的な噴火で火口がふき飛ばされたり、マグマが地下で移動してしまって火口が崩壊し、その後陥没した大きなくぼみをカルデラといいます。
日本の火山の大部分が成層火山です。マグマのねばりけが強いと火砕流が発生する可能性が高くなります。
火山灰による被害も甘く見てはいけません。
飛行機のエンジンをとめてしまうこともあれば、太陽光をさえぎって世界的な冷害を引き起こすこともあります。
top
> 大地の変化 > 火山と火成岩 > 火山の活動