各原子には結合の手の本数が決まっていて、原子は結合の手を残さないようにほかの原子と結びつくと考えます。
以下の原子の手の本数だけ覚えてしまうと応用ができます。
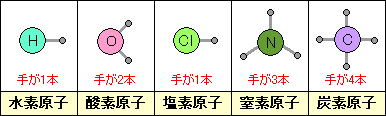
【例】分子のつくりも「手」を考えるとわかりやすいです。
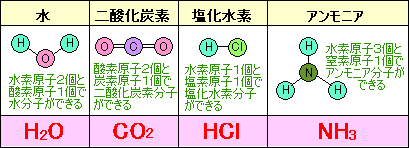
もっと原子の数が多い分子も見てみましょう。(今は以下の化学式やつくりを覚える必要はありません)
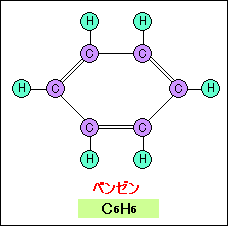 Cからは4本の手が、Hからは1本の手が出ています。
Cからは4本の手が、Hからは1本の手が出ています。
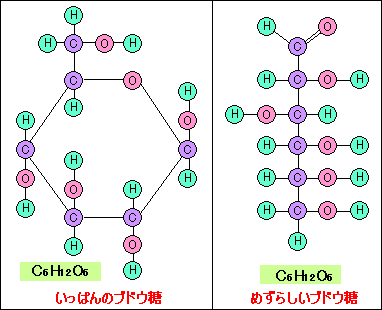 Cは4本、Hは1本、Oは2本の手がありますね。
Cは4本、Hは1本、Oは2本の手がありますね。
化学式は中学では覚えるべき「暗記もの」ですが、原子どうしの結びつきの割合はある程度きまりがあります。
それぞれの原子には結びつくための「手」があるという考え方で原子の結びつきを説明できます。
それぞれの原子の結合の手
各原子には結合の手の本数が決まっていて、原子は結合の手を残さないようにほかの原子と結びつくと考えます。
以下の原子の手の本数だけ覚えてしまうと応用ができます。
【例】分子のつくりも「手」を考えるとわかりやすいです。
もっと原子の数が多い分子も見てみましょう。(今は以下の化学式やつくりを覚える必要はありません)
Cからは4本の手が、Hからは1本の手が出ています。
Cは4本、Hは1本、Oは2本の手がありますね。
モデルを並べて物質を作ろう
どんな原子何個ずつでどんな物質ができるか実際に確認するための教材をFlashで作りました。(約178KB)
周期表と手の関係(参考)
周期表の上に1〜18の番号があります。 周期表を見る 確認が終わったら×で閉じましょう。
18の列の原子は特別で、希ガス・不活性ガスなどと呼ばれ、原子のまま気体で存在できます。「手」はないと考えます。
17と1の列の原子は「手」が1本と考えます。(H Cl Na Kなど)
16と2の列の原子は「手」が2本と考えます。(Mg Ca O Sなど)
15の列の原子は「手」が3本と考えます。(Nなど)
14の列の原子は「手」が4本と考えます。(Cなど)
※例外は多いです。厳密にいうと、結びつきの種類がちがう「手」もありますが、本数だけで考えることにしましょう。
top > 化学変化 > 原子記号と化学式 > 原子の手