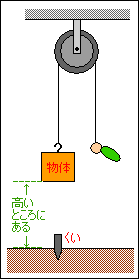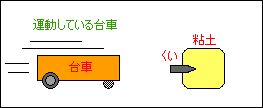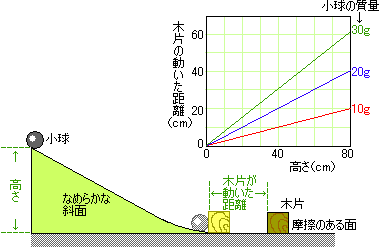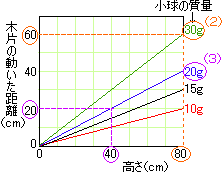エネルギーということばはよく聞きますね。理科ではどんなことをエネルギーというのか、しっかりおさえていきましょう。
エネルギーとは
エネルギーにはいろいろな種類があります。
|
エネルギー…他の物体を動かしたり、変形させたりできる能力
|
ある物体がほかの物体を動かしたり変形させたりできる状態にあるとき、その物体はエネルギーを持っているという言い方をします。
まず、力学的エネルギーと呼ばれるものを覚えましょう。
位置エネルギー
|
順番にラジオボタンをクリックしてみてください。
高い位置にある物体は重力で落下し、
他の物体を動かしたり変形させたりすることができます。
|
位置エネルギー…高い位置にある物体が持っているエネルギー
|
位置エネルギーの大きさは
物体にはたらく重力の大きさとその位置の高さに比例します。
|
位置エネルギー=物体にはたらく重力の大きさ×物体の高さ
|
|
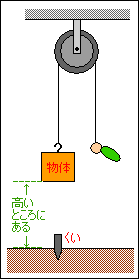
|
※その物体が重いほど、また、高い位置にあるほど位置エネルギーが大きいので、ほかの物体を動かす距離も変形のようすも大きくなります。
ふつうは基準点(地面など、その物体がいちばん低くなれる位置)からの高さを考えます。
2個の物体を比べたとき
|
同じ質量の場合
|
高い位置にあるほうが位置エネルギーが大きい
|
|
同じ高さの場合
|
質量が大きいほうが位置エネルギーが大きい
|
※同じ質量で同じ高さの位置にあるときは、位置エネルギーの大きさは同じです。
|
弾性エネルギー…変形した物体が持っているエネルギー(位置エネルギーの一種)
弾性とは変形した物体がもとの形にもどろうとする性質でしたね。
ばねやゴムだけでなく、一見固そうな物体にも弾性はあります。
縮めたばねはこの先、弾性でもとにもどろうとしています。
もとにもどるときに他の物体を動かしたり変形させたりできますね。
変形した物体はエネルギーを持っています。
たとえばばねなら、どんな位置まで縮めたか(またはのばしたか)によってエネルギーの大きさが決まるので、弾性エネルギーも位置エネルギーのひとつです。
|
運動エネルギー
|
順番にラジオボタンをクリックしてみてください。
|
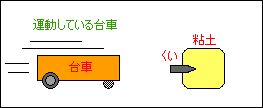
|
運動している物体は
他の物体を動かしたり変形させたりすることができます。
|
運動エネルギー…運動している物体が持っているエネルギー
|
運動エネルギーの大きさは物体の質量に比例し、速さの2乗に比例します。
その物体の質量が大きいほど、また、速ければ速いほどエネルギーが大きいので、ほかの物体を動かす距離も変形のようすも大きくなります。
2個の物体を比べたとき
|
同じ質量の場合
|
速さが大きいほうが運動エネルギーが大きい
|
|
同じ速さの場合
|
質量が大きいほうが運動エネルギーが大きい
|
※同じ質量で同じ速さの物体は、運動エネルギーの大きさは同じです。
【例題2】
なめらかな斜面に小球を転がして木片に当て、木片を動かした。小球の質量や小球の高さを
変えて木片の動く距離の変化を調べたのが右のグラフである。摩擦力はつねに一定の大きさ
で木片にはたらいたとする。
|
|
(1)80cmの高さにある30g
の小球が持っている位置エ
ネルギーは、40cmの高さに
ある10gの小球が持つ位置
エネルギーの何倍か。
(高さが0のときの位置エネルギーを0とする)
(2)15gの小球を高さ80cm
から転がして木片に当てる
と、木片は何cm動くか。
(3)40gの小球を高さ40cm
から転がして木片に当てる
と、木片は何cm動くか。
| 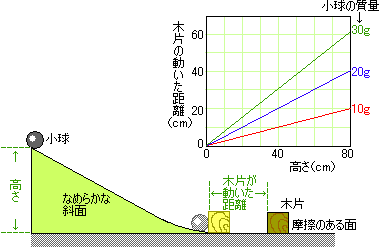 |
|
小球の持つ位置エネルギーで木片に仕事をした問題ですね。小球は摩擦力にさからって木片に仕事をします。
この場合、摩擦力はつねに一定なので、木片がされた仕事は木片が動いた距離だけに比例することになります。
仕事を比べるときは動いた距離を比べればいいですね。
(1)
高さ80cm・30gの小球は重さだけでも10g(重さ10g重)の小球の3倍あります。
さらに高さが2倍あるので、 3(倍)×2(倍)=6(倍)
6倍の位置エネルギーを持っているので、6倍の能力がありますね。
(2)
高さが同じなら、木片の動いた距離は小球の重さに比例します。
重さ15g重の小球は重さ30g重の小球の半分の重さなので、木片の動く距離は、同じ高さ(80cm)の30gの小球の場合の半分になると考えられます。
|
高さ80cm・30gの小球の木片の動いた距離を
グラフから読みとると60cm。
60(cm)÷2=30(cm) 答えは30cmですね。
(3)
40g重は20g重の2倍なので、(2)と同様に
高さ40cm・20gの小球の場合を読みとると便利で
す。高さ40cm・20gの小球の場合の木片の動いた
距離はグラフより20cm。
20(cm)×2=40(cm) 答えは40cmです。
| 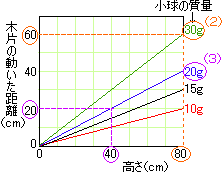 |
エネルギーの定義(参考)
以前は「仕事」というものを習っていました。前項目、前々項目を参考にしてください。
ここでは「仕事」ということばのかわりに「動かしたり変形させたりできる」と表現しています。
これから仕事ができる状態の物体は「エネルギーを持っている」といえます。
また、物体に仕事をしてその物体にエネルギーを持たせることもできます。
物体の持っているエネルギーの大きさは、その物体ができる仕事の大きさで表すので、エネルギーと仕事の単位は同じものを使います。
top
> 運動とエネルギー > 仕事とエネルギー > エネルギー