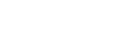レンズ構成概説
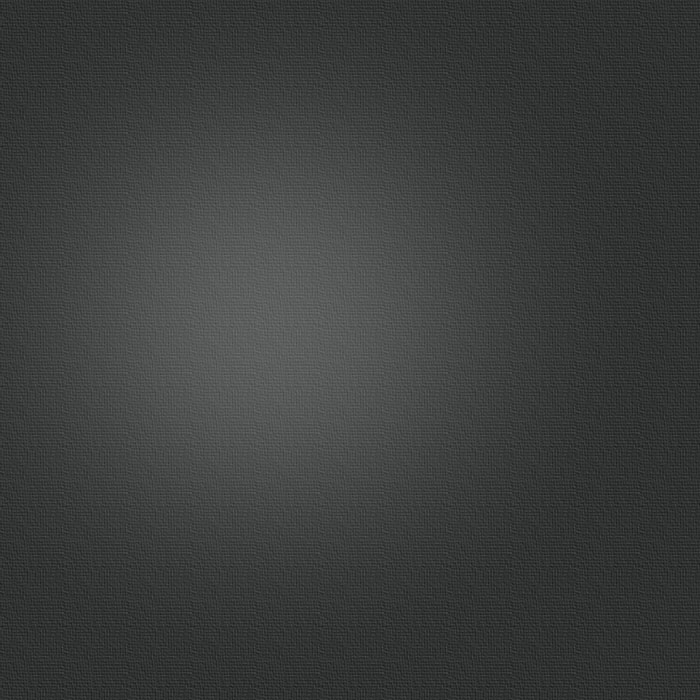
エルノスタータイプ(Ernostar type)
homepage2.nifty.com/MINOX/phase12.htm
トリプレットタイプレンズの1枚目と2枚目の間に凸メニスカスレンズ(群)を配置したレンズ。エルネマン社のルービット・ベルテレ(L.Bertele)が 1924年に開発したレンズで、エルノスターは「エルネマンの星」を意味する。この改良によって球面収差を抑えながらトリプレットレンズの限界を超えた明るさを達成できたが、コマ収差や非点収差の補正の点ではまだ十分ではなかった。これをレンズの構成枚数を増やすことで解決しようとすると、レンズの表面反射が増加して画像のコントラストが低下してしまう。このジレンマにベルテレはツァイス・イコンへ移籍後も精力的に取り組み、エルノスターを発展させたゾナータイプを開発した。
オルソメタータイプ(Orthometar type)
homepage2.nifty.com/MINOX/phase14.htm
1926 年にカールツァイスのウィリー・ウォルター・メルテ(Merte)が設計したオルソメターからこのタイプ名が生まれた。この4群6枚・対称構成のレンズは、焦点距離の割に薄型で、あまり明るいものは作れない反面、画角は相当大きく取れる。また歪曲収差が少ないため、大判カメラや引伸し用レンズなどとして使われている。
ガウスタイプ(Gauss type)
4群6枚の例
www.praktica-users.com/lens/mlenses/morp1.8_50.html
5群6枚の例
www.praktica-users.com/lens/mlenses/czjpan1.8_80.html
現在の一眼レフ用標準レンズの型式としては最もポピュラーなタイプ。ガウス(K.F.Gauss)の望遠鏡対物レンズ(凹凸2枚の組み合わせ)を、絞りをはさんで対称的に向かい合うように配置したものがガウスタイプの基本型である。この4群4枚構成のレンズは、ダブルガウスタイプと呼ばれ、1889年にイギリスのクラーク(Alvan G.Clark)がポートレートレンズとして設計した。その後カールツァイスのパウル・ルドルフ(Paul Rudolph)が1896年にプラナーF3.6(4群6枚)を設計し、現在のガウスタイプの基礎となった。しかし、現在一般的なガウスタイプ(対称性のくずれた、いわゆる変形ガウスタイプ)の始祖は1920年にテーラー・テーラー・ホブソン社のリー(W.Lee)が設計した画角46度のオピック F2である。色収差のほか、球面収差、像面湾曲がよく補正され、バックフォーカスも長くとれるなどの優れた特徴を持っていた。しかし当時はレンズコーティングの質があまり良くなく、またレンズ枚数が多く、表面反射の影響を受けやすいガウスタイプはコントラストも低くなるため、それほど普及していなかった。しかしコーティング技術が確立されると一眼レフカメラ用レンズとして広く用いられるようになり、大口径化が進んだ。
ゾナータイプ(Sonner type)
www.praktica-users.com/lens/mlenses/morp2.8_135.html
エルノスタータイプの2番目の凸レンズと3番目の凹レンズとの間を低屈折率のレンズでつなぎ、貼り合わせたレンズ。ツァイス・イコンのベルテレが開発したエルノスタータイプのレンズは構成(群)枚数が多く、それと比例して表面反射によって失われる光量が多かった。彼はこの欠点を改良し、1929 年にゾナー F2が発売された。ゾナーはさらに大口径化され、距離計連動カメラ時代には標準レンズとしてガウスタイプを圧倒していた。1950年に来日したライフのカメラマンD・D・ダンカンによって評価され、日本製写真レンズの名を世界に知らしめたニッコール標準レンズ(SマウントのNikkor 50mmF1.4)は、このゾナー・タイプである。しかし、バックフォーカスの短いゾナータイプは一眼レフと適合せず、やがて姿を消していった。
#注:ニッコール(Ai AI-S 50mm)のボケは本当にゾナーに似たボケを出しますね。
テッサータイプ(Tesser type)
www.praktica-users.com/lens/mlenses/czjtess2.8_50.html
1902 年にカールツァイスのルドルフ(Paul Rudolph)とヴァンデルスレブ(Wandersleb)が設計した3群4枚構成のレンズ。4群4枚のウナーの前群と2群4枚構成のプロターの後群を組み合わせたものだが、トリプレットの3番目のレンズを2枚の貼り合わせとしたものと考えることもできる。構造上あまり明るいレンズはできないが、すべての収差が良好に補正されるため、当時としては非常にシャープなレンズだった。万能レンズと呼ばれ、日本でもヘキサー、タクマー、シムラー、セレナー、ニッコール、ズイコー、セコール、ロッコール、フジナーなど、ほとんどのカメラメーカーのレンズとして採用された。
テレフォトタイプ(telephoto type)
homepage2.nifty.com/MINOX/phase15.htm
凸レンズの後ろに凹レンズを置き、凸レンズの焦点距離を延長した光学系で、レンズの第一面からフィルム面までの長さ(レンズの全長)が焦点距離よりも短いものをいう。テレフォトタイプにすることによってレンズの全長を1〜2割短くすることができ、焦点距離が数百mmのものでは3割以上の短縮が可能である。 1600年頃、天文学者ケプラーによって見出され、1847年にイタリアのポローが写真用のレンズとして初めて採用した。35mm判では200mm以上の望遠レンズに使用される場合が多い。
トポゴンタイプ(Topogon type)
homepage2.nifty.com/MINOX/phase14.htm
70 度以上の画角をカバーする4群4枚構成の対称型レンズ。1933年にカールツァイスのロベルト・リヒター(R.Richter)が開発したトポゴン 100mm F6.3からこの名がついた。このレンズは100度以上の画角を持ち、18x18cmをカバーする航空写真測量用レンズとして開発され、歪曲収差もごくわずかだった。ガウスタイプの変形といわれ、湾曲の強い凹メニスカスレンズが向き合い、その外側に凸メニスカスレンズを配置した構成をしている。
トリプレットタイプ(Triplet type)
homepage2.nifty.com/MINOX/phase11.htm
www.praktica-users.com/lens/mlenses/mdom2.8_50.html
1894 年、英国のテーラー・テーラー・ホブソン社のテーラー(H.D.Taylor)が発明した2枚の凸レンズの間に1枚の両凹レンズが入った形のレンズ。このレンズは発売元のクック社(Thomas Cooke & Sons)と3群3枚構成であることからクックトリプレットの名称が名づけられた。それからこのタイプのレンズをトリプレットタイプと呼ぶようになったのである。トリプレットは、設計上の自由度の数(6面)と、写真レンズとして必要な要求の数(球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、ディストーション、色収差)とが、ほぼ一致する。つまり無理な明るさや焦点距離を求めなければ、実用的に満足できるレンズが設計できる。このように簡単な形式でありながら、一応、全ての収差が補正されているため、トリプレットタイプは現代写真レンズの一つの基礎形式となった。 Nikkor Q 105mm f4に見られる。この構成を持つものにツァイス社のトリオター、シュナイダー社のラジオナー、メイヤー社ドミプランがなどある。
ビオゴンタイプ(Biogon type)
www.cosina.co.jp/seihin/co/c-b-21/index.html
前後に凹レンズ(群)、そして中央に凸レンズ(群)を配置した超広角レンズ。第二次世界大戦の1951 年、新生カールツァイスのベルテレが開発したビオゴン21mm F4.5は典型的なビオゴンタイプの構成をしている。明るいレンズを作れない半面、ディストーションが少なく、広い画角をカバーできる。また前部の強い凹メニスカスレンズの効果で周辺光量の落ち込みが少ない。バックフォーカスが短いため、一眼レフカメラとの相性はよくないが、レンジファインダーカメラや大判カメラのレンズとして採用されている。
レトロフォーカスタイプ(retrofocus type)
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9
テレフォトタイプとは逆に凹レンズを前群に、凸レンズを後群に配置したレンズ型式。距離計連動カメラの時代、レンズはバックフォーカスの影響を受けなかったが、一眼レフカメラが実用化されるとレンズ最後部がクイックリターンミラーにぶつからないような設計が要求され、焦点距離をバックフォーカスより長くしたレトロフォーカスタイプが開発された。これによって画面の周辺光量をあまり低下させずにすむといった利点もある。1950年にフランスのアンジェニュー社から発売されたレトロフォーカス35mm F2.8からこの名称が生まれた。